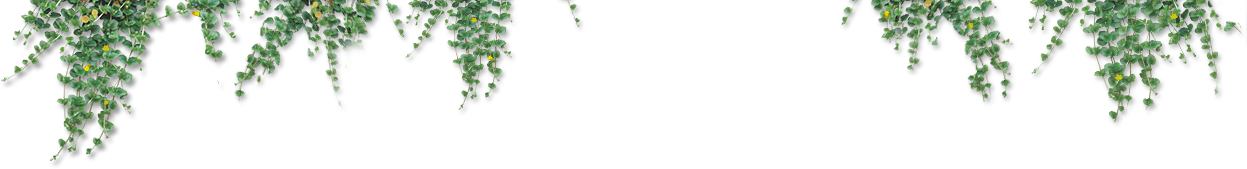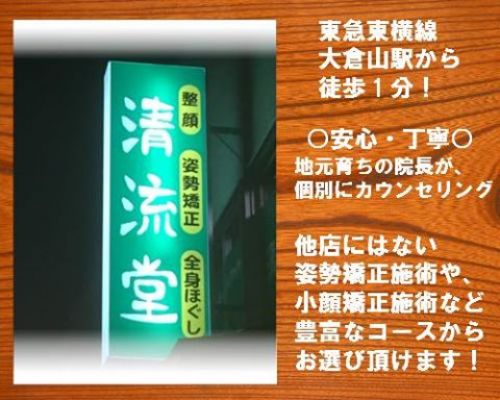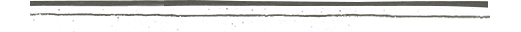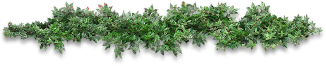
日記
滾法という基本技
「滾法(こんぽう)」という拳を軽く握って手を転がしていくという技があります。
東洋医学、特に推拿においてはまず真っ先に習う基本手技の一つであり、この習得だけで3か月近くひたすら練習するような重要な技術でもあります。
拳底を使えば背中や肩の裏側、腕や足に面打棒を転がしているような軽い刺激を与えることが出来、拳の表側を使えば足の付け根や肩の付け根などの柔らかくて強く押しづらい箇所でも解す刺激を送ることが出来ます。
但し、うまく力を抜く練習をしないと手首を使って拳を転がす性質上、手を痛める可能性が高いです。これが、推拿において最初に時間をかけて練習する理由です。
最初から施術部屋に面打棒のような道具を置いておけばいいじゃないかという声もありそうですが、基本的に手を様々な形に変えて、道具を模して使っていければ、道具を持ち帰る手間もなく常に対象の筋肉に最適な施術を行えるのでスムーズです。
整体に興味がある人にしか伝わらなそうな文章ではありますが、このような技術を使っています、という紹介でした。
摘まむ技
家庭で例えば家族の誰かにマッサージするとします。
仕事で背中がガチガチに張っていて全く押してもびくともしない、という時どうするでしょうか?
指先で柔らかくなるまで根気よく円を描くように押しまわしていく「円柔法」のような技もありますが、少々技術がいる為家庭でだれでも簡単にとはいきません。
もっと簡単に誰でも使用できる技として、「摘法」という技があります。
読んで字のごとく、軽く摘まみ上げるだけです。
背中の上の方から筋肉と皮膚を軽く摘まみ上げて、パッと話す、という動作を背骨に沿って腰の上まで行います。
特に硬いところは何度か同じ場所で繰り返します。
押してダメそうなところは、このように引っ張ってみると意外と簡単に解れる事があります。
また、それでも駄目そうであれば、先にご紹介した「叩法」なども併せて使ってみて下さい。
いづれも、対象面が硬いからといって無理に力を入れず、軽く、根気よく動作を繰り返す事が重要です。
胆経と頭部施術
内科などへ診療に行った際に言われて一番困ることが「原因はストレスですね」という文言だと思います。
その人の所属する環境が原因と言われれば対処のしようが無いし、それは誰にでも当てはまる無敵の言葉だからです。
どうすればいいのか聞きたくて診療に行っているのに「ストレスが原因です」では「そんなことはわかっているよ」で終わりです。
ストレスが原因であればそれでどこが疲労して、どうしたら対処できるのか?が重要です。
先ず臓器で一番ストレスの影響を受けるのが「肝(厥陰肝経)」と「胆(少陽胆経)」です。
足の肝経経脈は膝の内側から親指内側までを通りますが、指圧よりも足首や膝を動かす運動療法で血行を促進する方が身体への負担が少なく、効果も大きいと感じますのでここでは省きます。
個人で割と硬直が把握しやすく、対処も容易なのが頭部の胆経経脈です。
胆経とは頭部のどの辺を指すかというと頭骨の上半分の横側ほぼ全部です。耳そのものも含みます。
耳周りの皮膚に軽く手を当てて押しまわしてみて、動きが悪くて皮膚自体も硬ければ胆経が疲労している証拠です。自律神経の内、交感神経や副交感神経に関わる経穴が多い為、季節変わりの気温、気圧の変化の影響を受けやすいですが、外部ストレスなどの環境由来の影響も多く受ける場所です。
これだけの広範囲を一か所ずつ丁寧に解していたのでは施術時間は一日あっても足りません。耳の周りも含めて上記のように手の平全体でピタッと頭横全体を覆い、力は抜いて皮膚そのものをゆっくり動かします。
最初は微動だにしなくても、時間をかければ驚くほど簡単に皮膚が動き出します。硬直が多くても焦って強く押したりはしない事が重要です。
こめかみ周りが耳周辺ごと動くようになると血行が良くなり、ストレスの原因である物質も減少しますので楽になったことを感じ取れるかと思います。
筋肉の拘縮
整体など外部からの手技療法を行う際に、どうやっても取れない硬い筋肉が残ることがあります。
過去に事故などで不意の衝撃がかかった際に、身体を守る為に筋肉が自動でロックされた状態であることが推察されます。
この状態を「拘縮」といいます。
身体を守る為に無意識でかけ続けている力なので、「守る必要がない」と身体が認識を変えるまで10年でも硬直したまま残り続けることもあります。
整体で完全にこれを軟化させるためには、拘縮箇所を探し出して外部から縮め、力のかかっていない状態を作り出して少しの間そのまま待ちます。力を入れなくても大丈夫、と認識が変わればその場では拘縮が緩みます。
ただし、硬直していた期間が長いと、後で動かしているうちに「その部分に力が加わっていないことがおかしい」と脳が判断してしまい、また勝手に功夫直することがあります。
この場合は気長に、何度も拘縮を解除した時間を作り出して「もう力まなくてもいい」と完全に理解してもらうまで脳と向き合う必要があります。
また、外部から触れられる位置であれば上記のような対処法が取れますが、触れられない深層部で拘縮している場合にはそれを取る為の特殊な運動療法が必要になる場合もあります。
何度やってもあまりに力んだ感じが取り切れないようであれば、こういったリハビリを検討するのも手かと思います。
フェイスラインを構成するもの
当院では「整顔」というメニューを採用していますが、あまり他では聞かない名称かと思います。
どのようなものかといいますと、簡単には顔に対する整体です。
姿勢矯正清流堂という看板を掲げている通り、顔、および頭部全体にも姿勢が影響しますので、これを整える事が目的となります。
当院に見えられる多くの方の主訴に多い「フェイスライン」が気になるという点ですが、先ずはどの筋肉がどう影響するのか知ることが対策を立てるのに重要です。
フェイスラインを構成する筋肉の内、顎横最大のものが「咬筋」です。首の横にある胸鎖乳突筋と繋がっており、肩から繋がって首が張りますと咬筋にも力が入りやすい状態になります。ここに、噛み締め癖や、硬いものを食べるときに左右の力の差が加わる事で「顎関節症」や「フェイスラインの歪み」の発生原因となります。
咬筋は頬骨下に神経が集中している箇所の近辺を通る為、外側から強く指圧すると激痛が走ります。指圧による解しは出来ませんが、首を上にあげると胸鎖乳突筋から引っ張る力が弱まりますので咬筋も柔らかくなります。
従って、普段前傾姿勢によって上を向きにくくなっている方が多い首の関節を、どう安全に緩めて上を向けるようにするか、という点が施術するうえで最も重要な点になります。
もう一つ、たるみの原因になるのが顎下にある舌骨筋です。事務仕事などで下を向き続ける姿勢が多いと、舌を動かすためのこの筋肉に常に力が入った状態になり、その横側にある胸鎖乳突筋と連動してお顔全体を下方向に引っ張る力に変わってしまいます。
すぐ近くに唾液腺や耳下腺などの重要なリンパ腺もあるのでここも強い指圧はNGです。仰向けで顎の下に手を置き、軽い力で上方へ引きながら動きの限界地点ですぐに手を放す、という動作を数回繰り返す事でこの硬直を解除することが出来ます。
最低限上記二つの筋肉の緊張がほぐれた状態であれば、頬骨などは意外と可動性がありますので手を軽く乗せておくだけで本来の位置へ戻っていきます。また、この時点で首回りの血行が良くなっていますので、ローションなどで摩擦対策をしたうえで「推法」などの、老廃物を代謝の流れに乗せる種類の技が使用できるようになります。