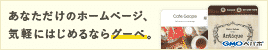インフォメーション
心理的安全性が「強い会社」を作る!具体的な取り組み方やコツとは?NO1
部下やメンバーと話す中で「じゃあそれ、やっといて」や「なんでできなかったの?」と言ってしまったことはありませんか?実はそれ、心理的安全性を下げてしまうNGな言動です。
心理的安全性とは、簡潔に言うと「恐れることなく、安心してなんでも言える関係性」のこと。心理的安全性がない会社は、離職が止まらず次世代リーダーが育たなかったり、次の事業の柱を作ることが難しかったり、大きなトラブルになるまで問題が放置されてしまいます。いずれ大きな損失を被ったり経営危機に陥ったりする可能性すらもあります。それくらい、心理的安全性は良い組織の形成と、会社の発展のために大切な要素なのです。
心理的安全性を高める方法やメリットなどを記載しました。心理的安全性を下げてしまうNG言動についても紹介しています。自分がNG言動を行っていないか、確認してみましょう。
最近「心理的安全性」という言葉をよく耳にします。「心理的安全性」とは、どのようなものなのでしょうか?
心理的安全性とは、地位や経験にかかわらずだれもが率直な意見や素朴な疑問を言える、あるいはお互いに言い合える組織やチームの状態のことです。
心理的安全性が欠ける組織では、小さな問題が報告されず、大事になるまで気付かれないリスクが高い組織です。例えば、従業員が小さな問題を上司に報告しないため、事態が悪化し、顧客からのクレームがあってはじめて問題を認識する事例などが挙げられます。場合によっては、自社工場が火事になったという事実を、社内の情報伝達より先にニュースやマスコミからの連絡で社長が把握するというケースすらあります。
心理的安全性があれば、問題が小さなうちに、あるいは発生して即座に情報が共有されるため、危機回避や損失削減が可能です。さらに、ネガティブな出来事の防止だけではなく、組織・チームで気づきやアイデアが活発に交換されるため、優れた工夫や新しい事業のタネが生まれます。要するに、心理的安全性は情報共有を促進し、経営上のトラブルを未然に防ぎ、そして未来を作るために不可欠です。
なるほど。心理的安全性の有無は組織に大きな影響を与えるのですね。上記の他にも、心理的安全性を確保することのメリットはあるのでしょうか?
⇒
はい。まず、心理的安全性はチームのパフォーマンス向上につながります。心理的安全性の高い環境では、メンバーが進んで間違いや失敗をチーム内で共有しますから学びの機会が増え、チームの成長が促進されます。一方、心理的安全性が低い環境ではメンバーは叱責を恐れて個人の失敗を隠すようになり、結果としてチームの成長も制限されます。
また心理的安全性の向上は、離職の抑制にもなります。1万人近くを1年以上追った研究の結果、離職者の心理的安全性は勤続者のそれと比べ、どの年代でも低いことが分かりました。つまり心理的安全性が低い状態を放置すると、従業員の離職につながってしまうといえます。
最後に心理的安全性の高まりはイノベーションの促進にも一役買います。従業員が積極的にアイデア、意見や新しい発想を出しあえる状態が、心理的安全性の高さです。さまざまな視点から出し合う多様な意見が、イノベーションや次の事業の柱を導きます。
設備投資における補助金活用事例
補助金などを使った設備投資によって、実際にどのような効果が得られるのでしょうか。ここでは、設備投資に補助金などを活用した事例をご紹介します。
事業再構築補助金の活用事例:ホテルのシステム構築に活用し業務効率化
ホテルを経営していた事業者が、人材不足で苦戦しやすい労働集約型から脱却し、さらに業務効率化を図るため、事業再構築補助金を受けて設備投資を行いました。
補助金を使って構築したのは、予約管理や客室の備品の管理、清掃手配などを自動で行うシステムです。この補助金とシステム構築により、業績の向上につながっています。
小規模事業者持続化補助金の活用事例:不動産内見のVRシステムで顧客利便性向上
不動産業を営むスモールビジネス事業者は、小規模事業者持続化補助金の採択を受け、VR(バーチャルリアリティ)で内見ができるシステムやWebサイトを制作。顧客の利便性を向上させました。
ものづくり補助金の活用事例:急速冷凍機導入で販路拡大につなげる
地域特産品の金柑を密閉冷凍するための急速冷凍機を導入した事業者は、機械導入にものづくり補助金を活用しました。
おかげで、生とほぼ同じ品質、鮮度での長期保存が可能になったほか、全国・海外に販路拡大を図ることにも成功しています。
補助金・助成金などを積極的に活用して設備投資を行おう
設備投資の目的として挙げられるのが、業務効率化や生産性向上です。労働人口の減少により、業務効率化や生産性向上は大きな課題になっており、今後もこれらを目的とした設備投資への補助金・助成金制度などは継続されると考えられます。積極的に活用し、設備投資を行っていきたいところです。
ただし、補助金・助成金は魅力的ですが、「補助金・助成金を受給するための設備投資」になっては本末転倒です。事業計画を策定し、事業継続や事業拡大などのために設備投資の必要があるかを見極め、それにマッチする補助金があるかどうかを調べて申請するのが適切なアプローチといえます。
自社に必要な設備投資かどうかをよく考え、そのうえで適切な補助金・助成金制度があれば、活用を検討しましょう。
設備投資に役立つ税制優遇制度
税制優遇制度とは、一定の条件を満たす場合に、税負担が軽減される制度です。設備投資を行うことで、税負担の優遇措置を受けられる場合があります。
スモールビジネス事業者や中小企業は赤字決算となっているケースも多いので、一定の税負担が生じていなければ税制優遇の効果は望めないものの、黒字決算で税負担を負っている事業者は、設備投資によって税の軽減が図れることを知っておきましょう。ここでは設備投資に役立つ税制優遇制度について解説します。
中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制は、中小事業者が2017年4月1日~2025年3月31日の間に中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に沿って生産性向上やデジタル化につながる設備投資を行った場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除が受けられます。
即時償却をすれば経費を多く計上でき、法人税(個人事業主の場合には所得税)の軽減と手元資金の確保に役立ちます。
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例は、設備投資によって労働生産性が向上することを後押しする制度です。市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者の設備投資については、償却資産に係る固定資産税の特例措置が講じられます。
導入した設備には固定資産税がかかるものの、導入当初3年間は固定資産税が2分の1に軽減されます。
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、中小事業者が新たに1台160万円以上の機械や、70万円以上のソフトウェアなどを導入した際、取得価額の30%の特別償却ができる優遇措置です。
資本金3,000万円以下のスモールビジネス事業者や個人事業主は、特別償却に代えて7%の税額控除を受けることもできます。
設備投資の補助金・助成金申請の注意点
設備投資に際して補助金・助成金を申請する際には、いくつか気をつけたいこともあります。ここでは、設備投資の補助金・助成金申請の注意点を押さえておきましょう。
申請や準備に一定以上の労力がかかる
補助金・助成金を受けるためには、規定された申請書類を作成、提出する必要があります。補助金によっては事業計画書などを提出したり、一定額以上の経費について相見積もりを取ることが求められたりするものもあります。
細かな申請ルールは制度によって異なるものの、どのような目的で、どういった設備投資を行うか、設備投資によってどのような成果が期待できるかなどを具体的に示さなければなりません。
さらに、厚生労働省管轄の助成金では、就業規則や労使協定などを提出するものもあり、それらの策定から着手しなければならないこともあるでしょう。申請には計画性とさまざまな準備が必要な点に注意してください。
要件を満たしても必ず採択される保証はない
補助金の場合、要件をすべて満たせば必ず支給されるというわけではなく、採択を受けて選ばれなければ補助は受けられません。採択を受けるためには、「わかりやすく、具体的な内容で申請書類を作成する」「補助金に設けられている加点項目を漏れなく申請する」といった工夫も重要です。
不安な場合は、専門家によるアドバイスを受けた方が、確実性が高まるといえるでしょう。なお、弥生の「資金調達ナビ」では、資金調達に関して相談できる税理士・会計事務所を無料でご紹介しています。
途中で導入したい設備が変わるときには追加手続きが必要
補助金・助成金の申請では、どのような設備を導入するか、生産機械や会計ソフトなどを具体的に決めて、費用などを記載します。申請して採択を受け、設備投資を実行するまでの間にある程度の期間を要しますが、その期間内に導入する機械を変更したくなったり、別のシステムを導入したいと考えたりといった事情が生じることもあるでしょう。
そのような場合には、導入設備の変更をしても補助金・助成金受給に影響しないかどうかを問い合わせ、必要に応じて追加の手続きを行わなければなりません。
補助金は後払いなのでキャッシュフロー悪化のリスクがある
補助金を受け取るタイミングには注意が必要です。補助金は、採択を受けたらすぐに受け取れるわけではないからです。補助金を受け取れるのは、実際に設備投資を行い、経費などについて報告し、その内容が審査された後となります。
設備投資にかかる費用はいったん、全額を自己資金で支払います。補助金を受け取るまで、一時的にキャッシュフローが悪化するので、資金繰りに問題がないかを確認しておきましょう。借入が必要な場合には、金融機関などに設備投資と補助金受給の旨を伝え、それを前提に融資を受けるようにしてください。
事業実施期間内に設備投資を行い、終了後も報告の必要がある
補助金は事業実施期間が定められており、その期間内に設備投資を実行し、終了後に費用などを整理して補助金の給付を受けることになっています。これを怠ると、補助金を受けられないので注意が必要です。
昨今は人材や資材の不足が起きることも多く、何らかの理由で設備投資が遅れて事業実施期間に影響を及ぼす場合には、補助金の事務局に相談する必要があります。年度内に事業実施できれば認められることもあるので、状況がわかり次第、すみやかに相談しましょう。
過剰な設備投資、不要な設備投資をすると経営が傾くおそれがある
「補助金を受けられる」からといって、過剰な設備投資や必要性が低い設備投資を行ってしまう事業者もいます。ですが、補助金で経費全額がカバーされるわけではありません。かかった経費の3分の1や2分の1は自己資金を投じることになります。
設備投資による利益増大や販路拡大などにおいて投資額を上回る成果が得られない場合、急激な資金繰りの悪化など、経営や財務に大きく影響することも。設備投資の範囲には注意が必要です。
設備投資の補助金・助成金申請のメリット
設備投資にあたって補助金・助成金を使うと、事業者にとって得られるものが数多くあります。ここでは、設備投資時に補助金・助成金を申請するメリットについてご紹介します。
業務改善、生産性向上による売上や利益の増大につながる
設備投資で補助金・助成金を使うことで第一に挙げられるメリットが、売上や利益の増大が期待できることです。
通常、売上や利益を増やすためには、生産性を上げて生産量を増やしたり、効率化によってコストを抑えたりする必要があります。それには新しい設備の導入やシステムの刷新といった設備投資が必要になることが多いですが、補助金・助成金を使えば設備投資が実現しやすくなります。結果的に、売上や利益の増大につながるのです。
返済の必要がない
設備導入には一定以上の費用がかかります。その費用負担の面から、設備投資をためらう事業者も少なくありません。
補助金・助成金は国や地方自治体などから支給されるもので、返済の必要がないのがメリットです。経費の一部を補助金でまかなうことができれば、設備投資が大幅にしやすくなるでしょう。
ただし、予定していた設備投資ができなかった場合、あるいは思ったような成果が得られなかった場合などは、返還を求められるケースもあるので注意してください。
設備の故障やシステム障害などによる機会損失を防げる
使用していた機械やシステムが古くなって故障したり、想定していた稼働量を確保できなかったりすると、事業自体が止まってしまうおそれもあります。事業が行えないことは売上や利益を得る機会を失うことになり、取引先からの信用にも影響するでしょう。
補助金・助成金による設備投資をして、機械やシステムを刷新すれば、販売機会を失うリスクを減らすことも可能です。
設備投資の必要性を見直すきっかけになる
事業拡大するために設備を導入したい、販路拡大するためにシステムを更新したいなど、設備投資を望んでいる中小事業者も多いことでしょう。しかし、資金繰りに四苦八苦するスモールビジネス事業者では、費用の大きさを考えて二の足を踏んでしまったり、日々の忙しさから導入を先延ばしにしてしまったりしがちです。
補助金・助成金制度があることで、設備投資について具体的かつ客観的に考えることができ、改めて導入の必要性を再認識したり、あるいはまだ不必要な投資であることに気づいたりできます。