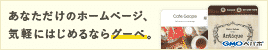インフォメーション
共感したお客さまをゾクゾク集める方法?オンライン集客のコツを集客のエキスパートに聞いた
集客に苦慮している中小企業は多いでしょう。しかしSNSやネットが活用できる昨今では、やり方によっては中小企業でも効率よく情報発信し、集客につなげることが可能です。
オンラインで集客する方法やコツなどについて、『共感したお客様だけがゾクゾク集まる! ひとり起業家のためのオンライン集客の教科書』の著者である鈴木 ケンジさんにお話を伺いました。
目次
· コスパよく集客に結び付ける。中小企業こそオンライン集客をすべし!
· KindleとYouTubeで集客?自社に合ったSNSを選ぶ
コスパよく集客に結び付ける。中小企業こそオンライン集客をすべし!
従業員数が少なく知名度も高くない中小企業が、SNSなどを活用して効果的に集客できるものなのでしょうか?
オンライン集客は、基本的にどのような企業でも実施できます。
私のお客さまも、大企業ではなく小規模でやっている起業家の方が多いです。その方たちの多くが、実際にオンライン集客を実施しています。SNSやKindleといったメディアをうまく活用できれば、確実に集客効果が期待できるでしょう。
ただしオンライン集客を実施する際には、NG行動に注意しなくてはいけません。具体的には、対面での営業や集客とはしっかりと違いを出すことが大切です。
対面であれば、その場で顔を見ながら話ができるため、相手のようすを伺いながら商品の説明を行うことができます。そのため、その場で商談が成約することも多いでしょう。しかし、この手法をオンライン集客にそのまま応用するのはNGです。
もともとリアルな営業を行っていた方がオンライン集客を実施する場合、いきなり商品を売ろうとするケースが散見されます。例えば、広告やSNSなどで初めて見た商品を、すぐに購入する方は少ないでしょう。例えば、たまたま立ち寄った洋服屋で、店員に商品を売り込まれるのに、抵抗を感じる方は多いと思います。
このようにリアルで抵抗を感じていることであっても、オンラインではそれを実施してしまうケースが多いのです。
オンライン集客を実施する場合には、見込み客を集めることが第一段階として必要です。
つまり「集客=顧客を集めることではない」と認識しておかなければ、そもそも商品は売れないと考えてください。
オンライン集客を実施するメリットを教えてください。また、デメリットがあれば、そちらの紹介もお願いします。
オンライン集客の主なメリットは、以下の通りです。
· 市場が広がる
· コストパフォーマンスが高い
· 数字が見られるため効果検証がしやすい
· リアルタイムで情報発信ができる
オンライン集客の最も大きなメリットは「市場が広がること」です。例えばリアルの交流会などの場合、その地域の方しか来ないのが一般的だと思いますが、オンラインであれば日本人だけでなく海外の方にも告知でき、実際に参加してもらうことも可能です。私のセミナーにも、海外の方がたくさん参加されている状況です。
またコストパフォーマンスが高いことも、オンライン集客のメリットといえるでしょう。例えばチラシを何千枚も印刷するときには、印刷コストが高くなります。せんみつ(「千三つ」とも書かれる、1,000件のうち3件しか反応がないというマーケティング指標の1つ)という言葉からもわかるように、費用対効果が低い集客方法にコストをかけることは、非常に厳しいです。ハガキや封筒のDMを1万通発送するような場合も、多額のコストが必要でしょう。しかしメールやLINEを活用すれば、コストはほとんどかかりません。
加えて、集客にかかわる数値がすべて見られるため、効果検証がしやすいことも、オンライン集客ならではのメリットです。しかし残念ながら、ほとんどの方が効果検証をしていません。売上が上がっていない企業にヒアリングしてみると、数字を見ていないことが圧倒的に多いのです。見ていたとしても、売上やコンバージョン、PVなど、一部の数字だけというケースがほとんどです。詳しくは後述しますが、これはぜひ活用してほしいポイントです。
リアルタイムで情報発信ができることも、オンライン集客のメリットです。例えば飲食店において、いきなり団体の予約がキャンセルになった場合、料理などを無駄にしないためにお客さんを集めようとなれば、多くの方に電話をする必要があります。しかし、オンラインであればSNSなどで情報を発信するだけで、集客につなげることが可能です。LINEなどであれば、自分の届けたいタイミングでお客さまに届けることができるのも大きいですね。また、さまざまなメディアが存在するため、自社のターゲットに合うものを選べます。
オンライン集客を実施するデメリットを教えてください。
オンライン集客のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
· 競合が増える
· ITリテラシーが必要
· 広告費が高い
· 信頼関係の構築に時間がかかる
オンライン集客では、市場が広がる反面、競合が増えることはデメリットだといえます。新型コロナウイルス感染症の影響でオンラインが普及したことによって、その傾向はさらに高くなりました。したがってオンライン集客を実施する場合には、競合が多いことを見越しておく必要があります。
次に、オンライン集客を実施する場合には、ある程度の専門知識が必要です。そのため「パソコンがまったく使えません」という方は、実施することが非常に難しくなります。もちろんスマホでも実施できますが、一定のITリテラシーは必要です。
また、広告費が高騰していることも、オンライン集客のデメリットです。Facebook広告やInstagram広告も以前は安価でしたが、新型コロナウイルス以降、出稿する企業が増加したため高騰しています。時代の流れによって、広告費が変動することを覚えておく必要はあるでしょう。
オンライン集客は、信頼関係の構築に時間がかかることも念頭に置く必要があります。リアルの場合、対面で話せるため関係性を構築しやすいのですが、オンラインは顔が見えないため、どうしても信頼関係を構築しづらくなることは理解しておきましょう。
KindleとYouTubeで集客?自社に合ったSNSを選ぶ
オンライン集客を行う際に使用するSNSやWebサービスを教えてください。また、業種別、ターゲット別で適したサービスなどあれば併せて教えてください。
結論から言えば、どのようなメディアでも問題はありません。ただし、自分が続けられるメディアを選ぶことがポイントです。例えばTikTokやClubhouseなど、新しいメディアが話題となりましたが、今でも継続しているという方はほとんどいないのではないでしょうか。
私がおすすめしたいのは、KindleとYouTubeです。両者とも多くのユーザーベースがあるため、潜在顧客を集めやすいことが、おすすめする理由となります。書籍や動画を最後まで読んでくれたり、見てくれたりしたユーザーは、自分のことを知らなくても見込み顧客になってくれる可能性が高いでしょう。
Kindleは見込み顧客の集客と教育を同時にできるツールです。例えば、文字を書くメディアにはブログなどもありますが、文字数は多くても2,000~3,000文字程度が一般的でしょう。
しかし、Kindleであれば2万文字などで伝えられるため、情報量が10倍になります。SNSなどに比べ、信頼関係を構築しやすい点もメリットです。
TikTokやTwitterなどの場合、とにかく文字数や秒数が短く、内容を正確に、すべてを伝えきることが困難です。そのため集客につなげるためには、よほどの能力があるか、実績やブランドがなければ困難でしょう。一般の方が会社のアカウントで始めても、大きな効果は期待できません。
したがって、内容をしっかり伝えられるKindleやYouTubeなどのメディアを、集客の軸に持つことが非常に重要です。これらのメディアから自社のターゲット層に合わせ、見栄えがよいものであればInstagram、キャンペーンを実施したい場合はTwitterなどへ顧客を誘導することによって、集客効果を高められるでしょう。また、ビジネス系であればFacebookも十分活用できます。
「共感」がもたらす効果とは
なぜ共感したお客さまが集まるのか、その理由を教えてください。
近年は、昭和のモノ消費や平成のコト消費に代わり、ヒト消費の時代になったことが大きな要因と考えます。「共感」が集客にとって非常に重要なポイントとなったのです。ヒト消費とは「その人がやっているから、見たい」「その人が売っているから、買いたい」といった、特定の人が紹介、おすすめするものを消費する行動です。
しかし、最近ではTwitterやFacebookなどでオンライン集客をするだけでは、高い効果を得ることは難しくなりました。特に実績やブランドがない企業が、高い集客効果を上げることは非常に困難でしょう。
1億総メディア時代といわれる現代においては、非常に多くの情報が溢れています。ただし人々による情報の消費量は、依然として変わっていません。そのため、顧客が商品やサービスを決めるときには、有名人やブランドを持っている方、専門家などのわかりやすい指標で選ぶ傾向が高くなっているのです。それが信用へと繋がり、さらには「好きな人や会社から買いたい」という時代になり、好きになってもらうためのきっかけになるものが共感です。インフルエンサーが、これほどまでに増えた背景には、ヒト消費の広がりがあります。
したがって、一般の方や企業がゼロから実績を積むのは、非常に困難になったといえるでしょう。例えば飲食店の場合、廉価なチェーン店などにおいても、普通においしいものが食べられるようになっています。店ごとの商品力の差も、以前に比べ、それほどなくなりました。また、オンラインが浸透したことによって、地域ごとの情報格差もほとんどありません。このような時代においては、価格で商品は選ばれない傾向にあります。
普通の方や企業がインフルエンサーを目指すのは難しいため、まずは「意味のある人や会社」になることが重要です。「役に立つ」ではなく「意味のある」という点が大切なポイントといえます。
例えば、普通のペンが1,000円で販売されていた場合、多くの方は購入しないでしょう。100均などへ行けば、3本セットを100円で購入できるため、価格で選ぶ方はこちらで購入します。逆にトンボなど有名なブランドであれば、1,000円で購入する方もいるかもしれません。つまり価格か知名度で選ばれるため、この2つを満たせない場合、厳しい状況に陥ってしまうことが予測できるのです。
しかし、ある有名ミュージシャンが作詞に使ったペンの場合、ファンであれば1,000円どころか数万円出して購入する可能性もあります。サイン付きであれば、もっと高額になるでしょう。一般の方にとっては、まったく価値のない商品だったとしても、ファンの方にとっては非常に意味のある商品となります。
したがって、まずだれか1人でもよいので、その方にとって意味がある人や会社になることが、オンライン集客の第一歩と考えてください。そして、その最初のきっかけになるものが「共感」なのです。
共感によって得られる集客能力は、どの程度のものなのでしょうか?
具体的に効果を数字としてあげるとすれば、これまで私はKindleで何冊も本を出版し、実際に何千人の方を集客できています。
売上でいえば、セミナーの最後にいつもお話しするストーリーに共感してくれた方の中には、100万円以上の商品を購入してくれる方もたくさんいる状況です。
何か商品を購入する際、好きな人と好きでない人が売っていたとしたら、好きな人から購入したいと思うのは当たり前です。したがって、共感してもらえる能力を高めることによって、購入してもらえる確率が何十倍にも何百倍にもなる、非常にシンプルな話といえるでしょう。
ストーリーを重視したオンライン集客の実践方法
オンライン集客を実施する方法を教えてください。
まずはペルソナの設定を行います。ペルソナとは、サービスや商品のターゲットとなるユーザー像のことで、マーケティングにおいて活用される概念です。本当に実在しているかのように、年齢、居住地、年収、価値観など具体的な情報を設定します。
ペルソナを作る手順は、以下の通りです。
1. ターゲット層の決定:例えば40歳の女性など、大枠の顧客層を決める
2. リサーチ:ターゲットの悩みや、どのような未来を想像しているのかなどについて、インタビューを実施。ロイヤルカスタマーがいる場合は、必ずインタビューを実施すること
3. 理想のお客さまシートを作成:お客さまの写真や名前、年齢、身長、体重、会社名、役職、年収、お小遣い額、趣味、家族構成、よく読む雑誌、好きなTV番組などを細かく書いた履歴書のようなものを作る
上記理想のお客さまシートが完成したら、最適な訴求方法を検討します。これが、最もシンプルにペルソナを作る方法です。もちろん既に顧客がいて、この方というお客さまがいれば、その方をペルソナにしても構いません。
ペルソナは理想のお客さま像といえるものですが、多くの企業があいまいな決め方をしています。例えば「これは全員に買ってもらいたい」という商品は、ほとんどの場合大きな売上にはつながりません。
書籍の中でも触れていますが、以下3つのプレゼントのうち、最も喜ばれるものはどれかという質問があります。
· 旦那さんや奥さん、子どもや親、恋人など、だれか1人へのプレゼント
· 高校3年生のときの同級生30人全員に渡すプレゼント
· 東京都に住む年収500万円の男女100人渡すプレゼント
もちろん最も喜ばれるのは、1つ目の旦那さんや奥さんへのプレゼントです。
その人のことだけを考えて渡すプレゼントなので、喜んでもらえる可能性は非常に高くなります。しかし、30人や100人の方が対象になると、最大公約数のプレゼントになるため、当たり障りのないものになってしまう傾向にあります。
これはビジネスの世界でもまったく同じで、だれか1人のために作った商品であれば、その方に響きやすくなります。このとき「それでは大きな売上につながらないのでは?」とよく言われますが、そのようなことはありませんから、まずは試してみてください。
集客ではなく商品の話になってしまいますが、中小企業に多いプロダクトアウトからスタートするケースは、失敗する可能性が高い傾向にあります。自分の売りたい商品を訴求しても売れないため、ペルソナが求める商品を作ってから売る必要があると考えてください。
もしくは、既に商品がある場合は、ペルソナに響く商品に変えなくてはいけません。ペルソナに響く見せ方へ変えることによって、それまで売れなかった商品が売れるようになったケースは多くあります。例えば、制汗剤のシーブリーズはペルソナを「マリンスポーツをする20〜30代男性」から「部活後に好きな男の子のために制汗剤を使う女子高生」に変更し見せ方も変えたことで、わずか1年で低迷期の8倍の売上を記録しました。
このようにペルソナを明確化することで、ターゲットにメッセージが届きやすいように工夫しやすくなり、画期的な商品も生まれやすくなるのです。
ペルソナ設定後に行う施策について教えてください。
次は、商品に対するストーリーを作りましょう。ストーリーとは「だれが」という部分や、商品自体の開発秘話などを見せるものです。
先ほどお話した通り、商品だけで差別化することは難しくなりました。以前は、3M(Market、Media、Message)さえ留意していれば、ある程度は商品が売れる時代だったといえるでしょう。
しかし現在は、そこに「だれが・だれに・何を・どのように」売っていくかというように、「だれが」という部分が重要視されています。商品には、もともと機能的価値(商品自体の機能やメリット)と、情緒的価値(商品・サービスの利用後に顧客が感じる価値)があると言われていました。そして現在は、これらに加えて「だれが」「その会社が」という人間的価値と呼ばれるものが追加されています。
人間的価値を訴求する場合には、人や会社の価値をどのように見せるかが大事なポイントです。最も簡単に表現できる手法として、ストーリーが用いられます。
ストーリーを作るうえでは「ビフォー・きっかけ・アフター」を意識することが重要です。
例えば、商品開発秘話であれば「もともとはこのような状態だったが、ちょっとしたきっかけでお客さまからこのようなお声をいただき、この商品が生まれました」といった流れで作る必要があります。
会社を主役にする場合は「マイナスな状況だったが、社長や社員の想いを絡めた一言などがきっかけに、この商品が生まれました」のような形で作ります。
また、長めのストーリーにしたい場合は「谷」を2回作ることが、顧客の感情を動かすポイントです。
例えば、感情を表すプラス・マイナスの線があった場合、上が「嬉しい」「楽しい」、下が「悲しい」「悔しい」といった感情だとしましょう。フラットな0の状態からスタートした場合、プラス・マイナスの上限が10であれば、最大で感情は10まで動きます。しかし、1度悲しい思いをさせてマイナス4になった後、最大まで楽しさや喜びを与えられれば、14もの感情が動くわけです。
「感動」という言葉は「感情を動かす」と書きますが、この振り幅が大きいほど、ヒトは感動しやすくなります。ストーリーを作る際には、感情の起伏を作ることを意識し、2回「谷」を作ると効果が高まりますので、ぜひ試してみてください。
共感を軸にしたオンライン集客には、なぜストーリーが重要なのでしょうか?
ストーリーは顧客から共感を得るために、欠かせないツールです。ストーリーを語る企業側と、それを聞く顧客側に感情のギャップが生じないように、ストーリーで共感を得て、その溝を埋める必要があります。
近年においては、意匠登録や商標登録などをしない限り、どのような商品やサービスでも、模倣されると考えてください。私も最近、自分の商品を丸パクリされましたが、調べればいくらでも情報が出てくるため仕方がないと思っています。
以前は、マーケティングにおいて、USP(Unique Selling Proposition)やUVP(Unique Value Proposition)をいかに確立するかが重視されていました。しかし現在は、それだけでは弱いと感じています。
USPの事例で最も有名なものが、ドミノ・ピザでしょう。1960年代のアメリカで「熱々のピザを30分以内に届けます。届かなかったら全額返金します」という打ち出しを行ったことで、大きく売上を伸ばしました。しかし現在、宅配ピザのサービスは多くの種類があるため、自宅から近いといった理由で選ばれることが多く、差別化は難しい状況です。
そのため多くの商品やサービスは、ストーリーを活用して、人間的価値による差別化を行う必要が出てくるのです
例えば、映画の「タイタニック」を例にお話しすると、史実としては豪華客船が流氷にぶつかって座礁し、沈没した事件だといえるでしょう。この事実を聞いただけで、心を動かされる方は少ないと思われます。
しかし、これが映画になることによって、まるで自分がその事件を体感しているように感じてもらうことが可能です。映画の観客は、船上で演奏している人たちの姿や、主人公の2人が海に沈んでいく姿を見て、感動し涙を流します。事実がストーリーに代わることによって、両者のギャップが埋まるわけです。
ストーリーを話している側は、語るという行為をしながら感情が動きますし、聞き手側はストーリーを通して、話している側と同じ気持ちを共有することができます。このように共に感じながら、両者のギャップを埋めることができるのです。
もちろん、すべての方がストーリーに共感するわけではありません。しかし、共感してくれた方々には「この会社いいな」「この会社の商品が欲しい」「この会社から教わりたい」といった気持ちの変化が現われるでしょう。
顧客に共感してもらえるストーリーを作るコツがあれば教えてください。
まずプロダクト面においては、作る側の感情をしっかりと入れることが大切です。そのとき発した言葉や、どういう状況で生まれたのかといった「なぜ(Why)」を含める必要があります。「なぜ」という部分がない場合、ストーリーが弱くなってしまいます。
「なぜ」は先ほどお話した「きっかけ」に該当する部分で、谷を作って山にしてあげることを意識することが重要です。
サービス面についても、プロダクトとまったく同様で「なぜ」が重要なポイントだといえます。しかし「なぜ」を伝えていない商品やサービスは、非常に多いです。商品やサービスの良さを伝えるだけで終わっているケースが、ほとんどだと思います。
「なぜ」を作るためには、お客さまに合わせたストーリーをきちんと作ることが大切です。例えば、私のセミナーであれば、参加者の属性に応じて毎回話し方を変えています。コンサルタントが参加している場合は、コンサルタントの事例をお話ししますし、整体師が参加している場合には、必ず整体師のお話を事例に含めています。
一方、自社のストーリーを作るとき、社長や従業員の多くが悲惨な話を書かなくてはいけないと思われるそうです。紆余曲折のストーリーにしたいと思っていても、自分の人生が平坦だったため、おもしろい内容を思いつかないというお話をよく聞きます。
しかし、紆余曲折のストーリーを考える必要はありません。最も重要なポイントは、お客さまが体感できるストーリーを書くことだからです。
例えば、液体洗剤のメーカーであれば、このようなストーリーが考えられるでしょう。
昔は粉の石鹸を使っていたのですが、いつも白い塊が洗濯物に残るのが嫌でした。
ある日、これをなんとかできないかと思い、水に溶かした後で洗ってみたところ、白い塊が残らないことが分かりました。
そこで「液体の石鹸を作れば、問題が解決するかもしれない」と思い、液体洗剤の開発に着手しました。
即興で考えたストーリーなので、本当かどうかはわかりませんが、このような顧客目線のストーリーであれば、共感してもらいやすくなります。
オンライン集客を成功させるポイントは「継続」と「改善」
オンライン集客を実施しても、すぐに期待した成果は上がらないと思います。集客を増やすために、重点的に実施するべきことを教えてください。
オンライン集客を成功させるためには、以下の2点に留意しましょう。
· 続けること
· 顧客の一番目の前にくる部分に注力すること
やはり、続けることが最も大事と考えてください。これまで、多くの法人を見てきましたが、やはりなかなか継続できないのです。とにかく成果が出るまで、続ける必要があります。
どの程度の期間続ける必要があるかについては、会社や個人の能力によって異なりますが、最低限1か月は続けなければ効果は見えないでしょう。そのことを説明したうえで「メルマガやLINEをやりましょう」と伝えても、1か月続くケースは非常に少ないというのが実情です。
普段からインフルエンサーのようすを見ている若い世代の方は、比較的続けてくれる傾向はありますが、30代後半から40代以上の方になると継続できなくなります。したがって、現在は「続けた企業が勝てる」という、非常にシンプルな状況ともいえるでしょう。
次に重要なポイントは、集客できない方の多くが、自社の商品力が弱いと思い込んでいることです。商品力はユーザーには見えないため、実際に購入して使ってみなければわかりません。しかし、ほとんどの企業が商品に注力しています。
最も注力する必要があるのは、顧客の一番目の前にくる部分です。例えば、商品のパッケージや小売店で販売する場所をどうするかのほうが、商品より何倍も重要だといえます。
そのうえで商品が良ければ、よりファンになってくれたり、リピートをしてくれるのです。具体的には、コンセプトをいかにブラッシュアップするかが大切なのですが、そこに気付いている方は非常に少ないのが実情です。Twitterであれば、ツイートよりも一番目の前にくるプロフィールの内容が企業コンセプトを含む部分となりますから、まずはそこを充実させることが集客には効果的となります。
プロフィールを充実させたら、続いて二段階の集客を行います。まず見込み顧客を集め、集まった人たちに対して継続的な情報発信を行い、その中でさらに興味を持ってくれた方に商品を販売する流れです。遠回りに見えるかもしれませんが、この方法が効率的となるのです。
一定の集客が実現できた後は、収益向上を目指す必要があります。オンライン集客で売上やリピート率を向上させるために実施するべき施策を教えてください。
オンライン集客で、売上やリピート率を向上させるためには、以下のポイントを押さえる必要があります。
· 数字を見ること
· 常に顧客と接触すること
· 顧客の成長に併せた商品を作ること
オンラインの場合、売上は以下のように算出することが可能です。
「売上=アクセス数×登録率×成約率×商品単価×リピート率」
そのため、まずはこれらの数字を把握する必要があります。しかし、法人のコンサルをする際「数字を見せてください」とお願いしても、すぐに出せるところはほとんどありません。売上を上げるためには、これらの数字を分析して、悪い部分を改善していく必要があるため、まずは数字を把握することからはじめましょう。
例えば、集客はできていても売上につながらない場合、アクセス数と登録率以外の数字を改善する必要があります。売上を2倍にするためには、それぞれの項目を1.15倍すればOKなので、実はそれほど難しい課題とはいえません。
売上やリピート率を上げるためには、顧客に忘れられないよう、常に接触を図ることが重要です。顧客に忘れられた瞬間に、商品を購入してもらえる可能性は非常に低くなります。
顧客が「これが必要」と思ったときに、すぐ自社の商品やサービスが頭に浮かばなければ、購入や利用にはつながりません。リピートしてもらうためには、顧客と最初に接点を持つ段階から、印象に残るような発信をする必要があります。
顧客の成長に合わせた商品作りをすることも、売上やリピート率を上げるためには大切です。顧客が商品を購入するときには、なんらかの必要性が存在します。しかし、商品を購入して問題が解決すると、また別の悩みが発生するため、解決するための他の商品が必要になるでしょう。顧客の成長に合わせ、段階的に商品を開発することによって、継続的な購入や利用につなげることが可能です。
単発商品の場合は、成長型ではなく、リピートしてもらいやすいしくみを作らなくてはいけません。生活の一部に溶け込む商品にしたり、通販などに見られる「月に〇回届きます」といったしくみを作ったりすることによって、リピート率が上がりやすくなるでしょう。
集客した顧客に商品を購入してもらうためにはLP(ランディングページ)も重要だと思いますが、効果的に作成するコツがあれば教えてください。
LPの作成は「こういう順番に書いていけばよいですよ」という型があるため、その通りに記述していくことがポイントです。有名なものは、マーケターである神田 昌典さんが提唱したパソナの法則でしょう。
· P(Problem:問題):ユーザーが抱えている欲求や問題を提起
· A(Affinity:親近感):問題の中身を掘り下げてユーザーに共感し、親近感を醸成
· S(Solution:解決策):問題解決につながる具体的な方法を提示
· O(Offer:提案):解決策を導入してもらうための提案を実施
· N(Narrowing Down:絞り込み):期間を絞り込み今すぐ購買すべき理由を提示
· A(Action:行動):購入行動を促進
この他にも、さまざまなLPの型はありますが、パソナの法則だけ覚えておけば十分でしょう。顧客の知りたい情報の流れになっているため、使いやすくなっています。
まず、一番上にキャッチコピーを配置し、その後はパソナの法則に従って内容が網羅されていれば、売れるLPを作成することが可能です。
オンライン集客を実施する際、注意する必要がある点があれば教えてください。
商品を作る前に集客をしてみることです。ほとんどの企業は、商品を作った後、集客を始めますが、私からすれば「失敗が怖くないのか」と思います。売れるポテンシャルがない商品の場合は、赤字になるリスクが高くなり、それを回避するために安売りなど、無理やり売り込む形となる可能性が高いでしょう。
例えば「こんな商品を作りたい」と思った場合に、集客をしないまでもアンケートをとってみたり、体験会を実施してみたりすることによって、顧客の反応を見てみることが大切です。その結果を見たうえで、具体的な商品化を進めるのが賢明だと思います。
また、完璧を求めないこともオンライン集客では重要です。やはり、早く実施できることがオンライン集客の良さだと思うので、完璧を求めると売上につながらない可能性が高くなります。
例えば、iPhoneは新しい端末が発売されると高確率で不具合が発生します。しかしAppleは完璧なプロダクトを出すよりも、ユーザーからフィードバックをもらって改修したほうが早いことをわかっているのでしょう。あれほどの大企業でも、完璧を求めていないわけです。
オンライン集客についても、完璧に準備できなければ実施しないというマインドではなくて、やってみなければわからないというテストのマインドを持つ必要があります。「これは絶対にいけるだろう」と思っていても、まったく売れないことはよくあることです。また反対に「これでも売れるんだ」というケースも、よくあります。
何度もテストを繰り返すことによって、徐々に施策の精度が向上するため、集客効果を高めやすくなるでしょう。数値もすべて確認できますので、さまざまな方法を試してみることが大切です。
【2024年1月1日までに対応必須】紙での保存はもう許されない?会社への影響は?中小企業の電子帳簿保存法対策術
近年、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、多くの企業がペーパーレス化を推進しています。しかし、一部業種や中小企業においては、いまだに紙を使った業務が多く残っているというのが実情です。
とはいえ、2022年1月より電子帳簿保存法の大幅な改正が実施され、企業におけるペーパーレス化の重要度は高まりをみせています。また2023年度税制改正大綱にも、電子帳簿保存法の改正内容が盛り込まれました。「電子帳簿保存法って何?」「何から手を付けたらよいかわからない……」「自社への影響は?」という状況の企業は、まずは具体的にどのような対策をとるべきか、理解する必要があります。
そこで今回は『改正電子帳簿保存法対策のための経理DXのトリセツ』の著者である、株式会社 経理がよくなる 代表の児玉 尚彦(こだま たかひこ)さんに、電子帳簿保存法の改正ポイントなどについて具体的に解説してもらいました。
· 2024年1月1日までにすべき準備【電子取引のデータ保存】
· スキャナ保存【紙をスキャンして画像データで保存する場合】
そもそも電子帳簿保存法とは?改正が中小企業に与える影響
そもそも電子帳簿保存法とは、どのような法律なのでしょうか?
電子帳簿保存法は、帳簿書類の電子保存を目的として、1998年に施行された法律です。会計ソフトの普及にともない、帳簿書類も紙ではなく電子化することで、企業の業務効率を高めることを目的として策定されました。
電子帳簿保存法は、所得税法や法人税法の特例法として設けられているため、紙の保存が原則であり、特例として電子での保存が許容されるようになった背景があります。しかし当時の電帳法は、事前に税務署に申請・承認をもらう必要があるなど複雑な手続きが課題でした。そのため、電帳法を利用する事業者が少ない状況が続いていたのです。その電帳法が2022年1月大幅に改正され、経理業務のペーパーレス化は急速な広まりをみせています。
2022年1月の電子帳簿保存法の改正内容を簡単に説明してください。
2022年1月に施行された電子帳簿保存法の改正内容で、特に重要なものは以下の3つです。
· 事前承認制度の廃止
· スキャナ保存制度の要件緩和
· 電子取引のデータ保存が義務化
まず、最も大きな変更点は、事前申請が不要となったことです。2022年1月から、電子帳簿保存の事前承認制度が廃止されました。これまで帳簿や証憑書類を電子的に保存するには、原則的に保存する時期の3か月前までに、税務署へ所定の書類を届け出が必要でした。しかし改正によって事前承認制度が廃止されたため、事業者がペーパーレス化を開始するハードルは確実に下がったのです。
2つ目に、スキャナ保存制度の適用要件が大幅に緩和され、利用しやすくなりました。読み取り機器もスキャナに限らずデジタルカメラやスマートフォンでも可となり、スキャナ保存するための運用管理体制やタイムスタンプ付与の要件なども緩和されました。
3つ目として、紙の書類ではなく最初から電子データでやりとりされる電子取引について、2022年からはオリジナルの電子データ保存が義務化されました。これが、中小企業にとって大変な問題となっています。すべての事業者が2022年から対応必須となっているものの、対応が難しい状況もあるため、急遽2年間(2022年1月1日~2023年12月31日)の猶予期間が設けられました。
電子帳簿保存法の改正によって、中小企業にはどのような影響があるのでしょうか?
電子帳簿保存法の対象となる帳簿書類の区分には、「会計帳簿」「スキャナ保存」「電子取引」の3種類あります。基本的には電子帳簿保存法は特例法ですから、紙が原則で電子が特例です。したがって、会計帳簿は今までどおり紙のまま保存しても問題ありません。請求書や領収書も紙で届いたものは、紙のまま保存し続けてもよいのです。ただし電子取引の場合は電子データが原本となるため、原本保存が義務化されます。
中小企業においても、2023年中に電子取引のデータの保存の仕方をルール化して運用をスタートする必要があります。そして、2024年1月1日からは電子取引の電子データの保存が義務化されるため、注意してください。
取引を電子化するメリット・デメリット
ペーパーレス化を推進することによって得られるメリットを教えてください。
経理部門がペーパーレス化を推進することによって、時間短縮、経費削減、品質向上の3つのメリットが得られます。
紙の書類の場合、処理や保存が必要です。それをペーパーレス化によって入力が自動化され、高速化されるため、従業員の負担や工数を軽減し、時間短縮につながります。
次に、紙は安いものだと思われがちですが、月に数百枚程度使う場合などは、かなりのボリュームとなります。工数も増えるため、その分経費が増します。ペーパーレス化は、紙代と人件費といった経費削減につながるでしょう。
またヒトが紙を見て判断すると、入力ミスなどのヒューマンエラーが多発します。ペーパーレス化によって、これらのミスを減少できるだけでなく、不正行為も防止できるため、品質向上が期待できます。
ペーパーレス化を推進するうえで、デメリットはありますか?
ペーパーレス化を推進するためには、IT投資が必要であることが1つのデメリットです。ペーパーレス化を実現するためには、ハードウェアやソフトウェアにお金をかける必要があります。しかし中小企業では、IT投資に多くのコストをかけられないケースも多いでしょう。
また、ペーパーレス化を推進するためには、1人1台のパソコンが必要です。電子データの保存には、サーバーや通信ネットワークなどの準備も必要になるなど、さまざまなコストがかかります。さらに、ソフトのバージョンアップやITツールのクラウドサービス利用にも費用が必要です。
このような中小企業のIT投資を支援するために、IT導入補助金が用意されています。今後、インボイス制度も絡んでくるため、このタイミングで補助金を活用するのがおすすめです。
他方でペーパーレス化を進める過程で、紙の書類を電子化する作業が発生するため、その分の事務作業が増える可能性があります。さらに移行期間中は、紙の書類と電子データの両方を管理する必要があるため、2重管理になってしまう点もデメリットといえるでしょう。
中小企業のペーパーレス化が進まない理由
中小企業におけるペーパーレス化がなかなか進まないという話を聞きますが、その理由を教えてください。
中小企業において、ペーパーレス化がなかなか進まない理由は大きく2つあります。
1つ目は、法律で紙の保存が義務化されていたため、紙での伝票作業や書類のチェックが習慣化していることです。例えば、長年同じやり方を続けてきた会社ほど、紙による管理から脱却することが難しい傾向にあります。社内で紙の書類に何人もが押印しながら処理することが、一連の作業として当たり前になっているケースもあるでしょう。また、税務調査などで紙の保存が必要だったこともあり、会計事務所においても紙での監査に慣れ親しんでいる人が多く、デジタル化に対して抵抗感を持っている人もいます。
2つ目は、請求書などに角印を必須とされており、電子の請求書を正式な書類として受け付けない企業も一定数あることが挙げられます。
こうした理由から、中小企業においてペーパーレス化はなかなか進まない状況にあります。
電子帳簿保存法で最低限対応しなければいけないことを教えてください。
電子帳簿保存法においては、電子取引のデータ保存が義務化されています。2023年末までは電子取引を紙に印刷して保存することも許されていますが、2024年1月からは電子取引のデータ保存が義務化されるため、中小企業や小規模事業者も対応が必須となります。
電子メールで受信したPDF形式の請求書やインターネットでの購入履歴などは、必ず原本の電子データの形態のままで保存しましょう。電子取引の原本データは、紙の書類と同様に原則として7年間の保存が必須となります。
2024年1月1日までにすべき準備【電子取引のデータ保存】
これから電子取引のデータ保存を始める場合、企業側で準備するべきこと教えてください。
準備すべきことを5つのポイントに分けて解説します。
現状の電子取引の種類や形式を把握
まず、毎月発生する受発注書や納品書、請求書、領収書のうち、電子取引でやり取りしている種類を洗い出します。このとき電子取引を受信する媒体別に、電子メール、ネット通販サイト、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、決済アプリなど)などに区分しておくといいでしょう。また、電子取引のデータ形式には、PDF、CSV、XML、JPEGなどさまざまなものがありますので、電子取引の種類ごとにどのようなデータ形式のものがあるかを把握しておいてください。交通系ICカードの利用履歴やスマホのスクリーンショットも、電子取引に該当します。
次に、電子取引の種類や形式別にそれぞれ月間の発生件数を数えます。データ件数が少なければ社員がパソコンで管理できますが、件数が増えればデータ管理のためのシステムが必要になるでしょう。
電子取引のデータ保存方法を検討
電子取引のデータ保存にあたっては、取引内容をパソコンなどの画面に表示できる状態にしておかなければなりません。税務調査の際には、税務署の調査官が要求した取引を画面で閲覧可能な状態にしておくことが求められます。
また日付、金額、取引先名を指定してデータ検索可能な状態にしておくことも必要です。「7月の〇〇円以上の取引」といった日付や金額の範囲指定での検索や、複合条件での検索ができるようにしておきます。
税務調査において、電子取引のデータを画面に表示できなかったり、データ検索に応じられなかったりする場合には、電子取引のデータのダウンロード(データをコピーして提出)を要求されます。
電子取引のデータの保存場所などについては、電子帳簿保存法において規定はありません。社内で運用ルールを決めて保存・管理してください。
電子取引の件数が少ない小規模事業者は、社内のパソコンやファイルサーバーに電子取引専用のフォルダを設定してデータを保存管理するのが一般的でしょう。ただし、検索要件がありますから、ファイル名に「日付、金額、取引先名」を付けるなどの工夫をして、対応する必要があります(例:[20230731_¥110,000_(株)A商事.pdf])。
一方で、電子取引件数の増加が予測される企業においては、電子取引のデータを保管するためのITツールやクラウドサービスの利用を検討する必要があります。詳しくは、後述します。
(参考)
電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁
証憑管理クラウドサービスの利用
電子取引のデータをシステム的に保存・管理するには、専用のデータ管理ツールやクラウドサービスを利用することになります。専用のシステムを開発・購入するには高額なIT投資が必要ですから、中小企業の場合は初期投資が少ないクラウドサービスの利用が適しているでしょう。
また、自社で利用している会計システムとの連動性も重要ですので、弥生会計ユーザーは、スマート証憑管理のようなクラウドサービスを利用するのも1つの方法となります。 使い方は簡単で、受け取った電子取引のデータをそのままクラウド上にアップロードするだけです。経理担当者は、アップロードされたデータをパソコンの画面で確認しながら会計処理が可能となります。クラウド上に保存された電子取引のデータは、いつでもパソコンから検索できるだけでなく、会計伝票と相互に関連性が確認できるので、計上漏れや不正防止にも役立ちます。
電子取引の税務調査対応
スマート証憑管理のような電子帳簿保存法に対応したシステムを利用していれば、税務調査においても安心です。電子取引のデータが改ざんされていないことを証明する修正削除履歴がシステム管理されるだけではなく、複合的なデータの条件検索にも対応できるためです。
それに対して、データ管理ツールを使わずに、社内で電子取引のデータ管理を行う場合には注意が必要になります。中小企業では、PDFの請求書が電子メールに添付されて送られてきた場合、データは取引担当者のパソコンに保存したまま、紙に印刷して経理に渡していることがあります。このようなデータ保存方法では、 税務調査の時に必要な電子取引が提示できず、またデータ検索もできないため、税務調査官にデータのダウンロードを要求されるケースも考えられます。最悪の場合、データの隠蔽や仮装を疑われ、社員のパソコンや電子メールの中身まで調査対象が広がってしまう危険もあるということを、理解しておきましょう。そのような事態に陥らないように、電子取引の原本データを社内で管理する場合は、経理のパソコンやファイルサーバーに書類ごとにフォルダを設定して一元的に管理する必要があります。
経理規程の整備
経理業務において、電子取引での作業はこれまでなかった新しい手法ですから、社内における経理の手続きや処理の方法などを定めた経理規程も変更になります。
特に電子取引のデータの保存の仕方や、運用管理のルールについては新しく規定する必要があります。
国税庁のWebサイトに、法人用と個人事業主用の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな型がWord形式で掲載されていますので、ダウンロードして参考にしてください。内容を確認すると、電子取引のデータ管理においてやるべきことや決めておかなければならないことが明確になります。
スキャナ保存【紙をスキャンして画像データで保存する場合】
今後、紙で受領したものを電子化して保存する場合、企業側で準備するべきことを教えてください。
電子取引のデータ保存はすべての企業が対応すべき義務ですが、スキャナ保存はあくまで任意です。現状としては、経理業務のペーパーレス化を推進する企業が取り組みを始めています。
スキャナ保存を始める前に、準備すべきことを4つのポイントに分けて解説します。
書類をスキャンしてAI-OCRでデータ化
ペーパーレス化のみを目的にすると事務負担だけが増えてしまい、あまりメリットがないこともあります。書類を単純に電子化しただけでは、スキャンした後、画像データを見ながら再び入力して申請する必要があるため、手間もかかります。
そこで、スキャンした後に画像データから文字や数字をデータ化してくれる、AI-OCR(人工知能による光学文字認識機能)の活用がおすすめです。領収書や請求書を見ながら日付や金額などをキーボード入力する作業が不要になるだけでなく、AIが過去の取引履歴から推測して該当する経費に分類してくれます。
会計システムとのデータ連動
ペーパーレス化による業務効率化のポイントは、データ連動の仕方を常に意識することです。紙の書類をスキャンしてAI-OCRで抽出したデータを会計システムへ連動すれば、経理担当の方は会計仕訳の入力作業から解放されます。
さきほど紹介した「スマート証憑管理」にもAI-OCR機能があるので、弥生会計と連動して会計仕訳を作成することができます。
会計伝票と証憑書類との相互関連性
スキャナ保存に関しては、電子帳簿保存法の要件が厳しいため十分な準備が必要です。特に領収書・請求書のデータと、会計伝票との相互関連性を確保しなくてはいけません。スキャンして画像データを保存するだけでなく、領収書や請求書がどの会計仕訳伝票と関連しているのか、管理しておく必要があります。
中小企業が自社でこのような仕組みを構築するのは、コスト的にも難しいでしょう。対策としてはここでも、「スマート証憑管理」のようなツールの活用がおすすめです。スキャンした画像データをアップロードすると、会計仕訳に自動で連動されると同時に、領収書・請求書が会計伝票と紐付けられ、管理されます。このように会計システムと証憑書類データの相互関連性がしっかりと確保される作業環境が整っていれば安心です。
スキャナによる電子保存規程の整備
スキャナ保存を始める場合、電子取引と同様に経理規程の改訂が必要です。スキャナ保存の場合も国税庁のWebサイトに「スキャナによる電子化保存規程」のひな型がWord形式で掲載されていますので、ダウンロードして自社用に編集して活用してください。
(参考)
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁
ペーパーレス化の従業員への周知
ペーパーレス化を推進するにあたり注意することはありますか?
経理業務のペーパーレス化を推進する際には「経理だけ運用できればよい」という考え方はNGです。請求書や領収書は、社内のさまざまな部門を経由して最終的に経理部門に集まってきます。各取引の発生から計上、決済までの全体の流れを把握して、それぞれの部門への影響度を配慮することが重要と考えてください。
実際にペーパーレス化を実施する前には、各部門の社員を集めて説明会を行い、「紙の書類で作業していた仕事がペーパーレス化してこういう形に変わります」と業務フローの変更点について周知することが必須です。また経費精算業務などにITツールを導入する際には、実際の領収書などを使って1か月程度仮運用してみるといいでしょう。その間に社内で運用しにくい点などを改善し、その後に本番運用へ移行すると失敗しません。
インボイス制度も電子帳簿保存法と合わせて対応
2023年10月から始まるインボイス制度について、電子帳簿保存法に関連して考慮しておくことはありますか?
インボイス制度がスタートすると、インボイス番号の判別処理が経理担当者の負担となることが予想されます。すべての領収書や請求書を確認して、インボイス番号があるかないかの判定を行い、それが適格請求書かどうかの判断をする作業が新たに増えるためです。人手による作業の場合、非常に手間がかかるため、電子帳簿保存法を活用して電子化を促進し、ITによる自動化を検討したほうがよいでしょう。
経理が紙の書類を見ながら入力するスタイルで作業を行う限り、入力ミスの発生を抑制するのは困難です。これを解決するためにも、電子取引の積極的な利用やスキャナ保存によるAI-OCRの活用で、インボイス制度により煩雑化する作業をデジタル処理で自動化することをおすすめします。
弥生会計とスマート証憑管理を連動させれば、領収書や請求書からインボイスを自動で判別するとともに、消費税の課税区分処理も間違えなく処理してくれます。インボイスで複雑になる消費税の計算ミスを確実に防いでくれるでしょう。
カギは経営トップによる採用活動?中小企業が若年層を採用するためのポイント
「若年層の社員を増やしたいけど、募集をかけても人が来ない……」と頭を悩ませていませんか?
若年層の採用を課題に感じている中小企業は多いです。では、採用がうまくいかない原因は何でしょうか。そして、若年層を採用につなげるポイントはどこにあるのでしょうか。
実は、経営者が採用活動に参加しているか否かは重要なポイントになります。忙しい経営者が自ら採用活動を行うことで「この会社は自分を大切にしてくれそうだ」と若年層が感じるからなのだそうです。
今回は、就職・採用支援のプロフェッショナルとして多くの若年層と企業をマッチングしてきた、株式会社ジェイックの大野 達也さんにお話を伺いました。中小企業が若年層を採用するための方法などを、詳しく解説してもらいます。
· 採用をかけても若者が来ない?若年層の採用状況の現状を知る
· 若年層がこない企業にありがちな傾向は?正しい対策で人材の獲得を目指そう
· 良いエージェントを探すコツは?中小企業が採用にエージェントを活用する際の流れ
採用をかけても若者が来ない?若年層の採用状況の現状を知る
現在の採用市場において、中小企業の若年層(18~24歳)の獲得は難しい状況なのでしょうか?
中小企業の若年層獲得は、非常に難しい状況となっています。
採用市場は現在、完全な売り手市場です。求職者側が就職・転職先の企業を選び放題の時代に突入をしています。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、3年前あたりと比較すると、ここ半年で大きく状況が変化しているのです。
新卒の就職率は軒並み上がっていますが、その多くが大手の新卒採用枠から埋まっていきます。そのため中小企業が新卒を採用するのは難しく、第二新卒と呼ばれる大学を卒業して3年目ぐらいの方々の獲得に移行するケースが増えました。ただし大企業も第二新卒採用を実施していますから、状況はより厳しくなっています。
若年層の採用が難しくなっている要因を教えてください。
少子高齢化で労働人口が減少傾向であること、さらに採用市場が売手市場となった影響で、若年層の絶対数が少なくなっていることが主な要因です。
また、若年層の仕事に対する価値観の変化も理由として考えられます。例えば「自由に働きたい」「テレワークでなければ嫌」「転勤はNG」など、求職者側の要求が高くなっており、選ばれにくい業種が存在することも事実でしょう。
コロナ禍に学生時代を過ごした人は、どのような点が就職先を選ぶポイントとなるのでしょうか。
新型コロナウイルスの影響で対面での指導を受けにくい学生時代を過ごした学生にとって、直接フィードバックや指導を受ける場があるかどうかが、職場選びのポイントの1つとなっているようです。直接的なかかわりのなかでこそ、自分の成長を実感できると考える学生が増加傾向にあります。こうした学生の意識を念頭に置いた職場環境整備を進めてください。
中小企業は、忙しくバタバタしながら日々を過ごすことが多いとは思うのですが、こうした機会を設けていない企業は、離職率が高くなる傾向にあります。人材育成という意味でも、重要なポイントと考えてください。
業種によって、若年層の採用率に差があるものなのでしょうか?
業種による若年層採用率の差は、存在します。近年、ITエンジニアの枠で未経験者採用を実施する企業が増加傾向にあり、こうした企業は若年層にも人気が高く、応募者が殺到している状況です。
一方で労働環境がハードな業界においては、採用が困難な状況が続いています。最近、弊社にも建築業界の企業から依頼されるケースが増えており、人手不足の深刻な状況がうかがえます。円安の影響で、海外からの労働者が減少していることも影響しているでしょう。
若年層がこない企業にありがちな傾向は?正しい対策で人材の獲得を目指そう
採用をかけても若年層が来ない中小企業の特徴や傾向を教えてください。
求職者がWebで検索した際、そもそも発見すらされない企業は、採用に苦戦する傾向にあります。ホームページを見てもらえても、そのデザインや内容が古い企業は、求職者から敬遠される傾向にあります。ホームページの更新が2014年で停止しているような、メンテナンスが実施されていない企業も、若年層は候補から外しがちです。ぜひ注意してください。
また、ホームページの内容も重要なポイントです。例えば、福利厚生の箇所をクリックしたときに、詳細が記載されていない企業は、求職者からは選ばれにくい傾向にあるでしょう。「年間休日がどの程度あるのか?」などは、求職者が気にするポイントです。必ず明記する必要があると考えてください。ホームページにきちんと記載していれば、求職者に「社員を大切にしている企業である」と認識してもらうことができます。ホームページのように、比較的手軽に企業の姿勢をアピールできるツールはぜひ活用してください。
逆に、中小企業で若手を採用できている企業の特徴や傾向を教えてください。
若年層が利用している媒体を、活用できている企業は強いです。そのような取り組みを行っている企業は、求職者から見ても「今後成長が期待できそう」と判断されるため、応募者の質も高い傾向にあります。
時代に即したツールを活用し、求職者に未来や可能性を見せることによって、ホームページすら見つけてもらえない現状を打開しましょう。SNSを活用するなどして「自由な社風に見える」「自分の裁量で仕事ができそう」だと感じてもらうことが、重要です。
また、経営トップも参加すると「社長自らが採用活動をしている」ことを効果的に訴えることができます。経営トップが時間を割いて採用に顔を出しているということを、企業全体の姿勢の表れと受け取る傾向にあるため、採用には有利に働くのです。忙しいとは思いますが、ぜひ採用活動には積極的に参加するようにしてください。
求人サイトを利用するのも1つの方法かと思いますが、効果はどの程度期待できるのでしょうか。
求人サイトは出稿量に応じて上位表示される設定が一般的となっているため、大手企業がトップページに掲載されるケースが多く、中小企業は思うような効果が得にくい面もあります。ただ、情報を露出する機会を増やすことは、プラスに作用する面もあるでしょう。
若年層に刺さる中小企業のアプローチ方法
若年層の求職者へ効果的にアプローチできる方法を紹介してください。
若い求職者に「この会社に就職したい!」と感じてもらうためには、まず、自社のリクルートページの内容を充実させることが重要です。概要欄も含め、具体的に詳細を記載しましょう。福利厚生は特に具体的に明記します。
しかし、どれだけ内容を充実させても、求職者に見つけてもらえなければ意味がありません。中小企業を専門に扱っているエージェントなどを活用して、効率よくアプローチするのも1つの方法です。求める人物像をエージェントに伝えることで、自社に最適な人材の斡旋を受けることができます。
求人サイトを利用した場合、掲載料として多くの費用を支払っても、必ずしも採用できるとは限りません。その点、エージェントは完全成功報酬型ですから、手間と時間をかけず効率よく自社が求める人材を採用することが可能です。求職者側も自分と相性のよい企業を探している状況ですから、マッチする可能性が高いといえるでしょう。
面接を行う際の注意点があれば、教えてください。
面接は、社長と直属の上司に当たる方が行うのがベストです。中小企業の社長は、多忙な方が多いかもしれません。しかし「会社の成功は、採用が鍵である」と考えている社長は、初回から自分で面接を行うケースが多い傾向にあります。
弊社が実施した「就職するうえで大切にしたいこと調査」によると、1位は「職場の人間関係」でした。面接者の雰囲気や上司に当たる方の人間的な魅力は、就職するかどうかの意思決定につながる重要な要素になり得る、ということです。求職者の志望度を上げるためにも、将来自分の勤める会社の社長と、直属の上司になる可能性がある人と面接するというプロセスは、必ずプラスに作用します。
若年層を採用したい場合、避けるべきポイントがあれば教えてください。
採用条件の部分で、基本給がない完全歩合制のフルコミッションの企業は、敬遠されるケースが多い傾向にありますから、見直しの必要があると考えてください。近年、保険業界などにおいても大きな変化が見られ、固定給を付けるケースが増えてきました。
また飛び込み営業など、昔ながらの足で稼ぐといったやり方をしている企業は、若年層の求職者にとっては抵抗があるようですので、こちらも見直しが必要でしょう。
我々のようなエージェントの視点から見ると、定着率の低い企業は敬遠されやすい傾向にあります。就職・転職系のWebサイトにネガティブな口コミが多数ついている企業も、避けられる可能性が高いでしょう。例えば残業が多い、社内がギスギスしているといった口コミが多い企業はNGといえます。
そのような企業から「何とか若年層を採用したいのですが」と依頼されることはありませんか?
ありますね。そのような場合には、社長や組織の考え方自体を変革しなければ、何も変わらないとお伝えしています。残念ながら、いまだに人を駒のように扱う企業が存在するのも事実です。そうした企業には「まずは社内で教育を行い、風土を変えてから採用してください」と話すことからスタートします。
離職率の高い企業の場合、
· 求職者:採用してもすぐに辞めてしまう
· 企業:多くの費用を支払っているのに無駄になる
· エージェント:マッチングの労力が無駄になる
というように、だれも得をしない状態に陥るケースが多いです。
従業員数が5~15名程度の中小企業で、若年層を採用できた理由があればご紹介ください。
若年層採用の成功の鍵は「社長自らが採用活動を行う姿勢を持つ」ことです。
やはり、経営トップが自ら企業理念やビジョンをしっかり語り、共感してくれた仲間を採用したいという意思を、求職者に示す必要があります。若年層の求職者が持つ価値観に寄り添い、働き方・育て方・活躍のさせ方を理解している企業が成功しますし、長く働ける環境が整っているケースが多いです。
また、学歴ではなく人間性やポテンシャルを見て、採用している中小企業は採用率が高い傾向にあります。過去に囚われず未来をみてくれる企業なら、就職後も大切にしてくれて、成長できそうと思われるケースが多いです。自社の雰囲気を伝える動画やSNSを活用している企業も、採用率は高い印象があります。中小企業は採用しにくいという状況を理解したうえで、すぐにでもできることから取り組むことが大切です。
「事業再構築補助金」 ~新分野展開のため、マシニングセンタとパレット搬送システムを導入~
補助金は、国や自治体の様々な政策目標を達成するために、企業や個人事業主の取り組みを支援するための制度である。補助金の制度目的や趣旨、条件に適した事業であるか、事業計画書等の申請書類に基づいて審査し、採択された事業者を補助金の採択候補者として選定される。採択候補者に選ばれるには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要である。採択候補者は、事業計画に沿った事業の実施、経費の計上及び支払を行った上で、それら申請が確認後に補助金が交付される。
今回は、機械部品メーカーが支援を受けながら、事業計画書を作成し、新分野展開のためにマシニングセンタとパレット搬送システムを導入した事例について、実際の事業計画書を基に、作成のポイントなどについて伺った。
|
申請補助金 |
事業再構築補助金(第2回) |
|
事業計画名 |
高精度化と生産性向上による金属機械加工分野での新事業展開 |
|
支援機関 |
静清信用金庫(静岡県静岡市葵区昭和町2-1) |
|
支援企業 |
株式会社石橋鉄工所 |
|
企業概要 |
精密機械部品、工作機械部品の製造及び組立 |
|
所在地 |
静岡県静岡市清水区北脇268 |
|
URL |
もう一つの事業の柱をつくるために、新分野展開を模索
石橋鉄工所は精密機械部品の切削・加工・組立等を主な業務とする、従業員11名の機械部品メーカーだ。事業の柱は、大手機械メーカーの溶接ロボット部品の製造・組立。熟練した技術者と精密マシニングセンタ・三次元測定機等の生産設備により、高精度な部品加工ニーズに応えることで、大手機械メーカーから信頼され、安定した経営を続けてきた。
しかし新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年初頭から主要取引先である大手機械メーカーが溶接ロボットを減産。このことにより、同社の売上は大きく落ち込んだ。
「大手機械メーカーからの発注が売上の大部分を占めていたため、経営への影響は深刻でした。新型コロナを経験して、一社に頼る経営はリスクが高いと痛感しました(石橋社長)」
石橋教志社長(当時専務)当時を振り返りながら、このように語る。これから企業として持続的に成長し、従業員の雇用を守っていくために、もう一つの軸となる事業が欲しいと感じた石橋社長は、父親である先代社長と相談しながら、自社の強みを活かした新分野への展開を模索した。そのきっかけとなったのが、「事業再構築補助金」である。
「事業計画書の作成にあたっては、最初から文章にしようと思わずに、公募要領の『事業計画作成における注意事項』の項目ごとに、思いつくことを箇条書きで書き出すところから始めました。そして、アドバイスをいただきながら、事業計画をまとめていきました(石橋社長)」
対話することで頭の中が整理され、事業計画がクリアになっていったと石橋社長は言う。現状分析の整理で役立ったのが、「SWOT分析」だった。経営相談部のアドバイスを受けながら、会社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)をまとめた後、クロスSWOTの「強み×機会」の「高度な技術力、測定力を生かした機械部品加工に取り組む」を、新分野進出の方向性とした。
また、市場環境の分析については、取引先の大手機械メーカーが株主・投資家向けに公開している「IR資料」等を参考にしながらまとめ、事業計画書にも記載し見事採択に至った。
支援機関とともに「事業再構築補助金」 ~新分野展開のため、マシニングセンタとパレット搬送システムを導入~ | 経済産業省 中小企業庁 (mirasapo-plus.go.jp)
従業員の介護離職を防ぐために、事前に対策できることを教えてください
少子高齢化の進行により、近い将来、介護離職を申し出てくる従業員が出てくることを心配していますが、自分自身に介護の経験がないため、何から始めればいいのかイメージがわきません。
1.介護離職は年間10万人
急速に高齢化が進む日本。企業経営にもさまざまな影響が及んでいますが、その一つに介護離職の問題があります。
「平成29年就業構造基本調査」(総務省)によると、家族の介護・看護を理由に離職した人は年間で約9万9千人、平成24年の同調査でも約10万1千人となっており、毎年10万人程度が介護離職していると推測されます(※1)。一方、要介護・要支援認定を受けている人は、令和2年3月末現在で669万人、平成12年の介護保険制度発足当初の256万人から約2.6倍に増加しており(※2)、今後も増加が見込まれます。
介護はある日突然やってくることも少なくありません。しかも、親の介護の担い手になっているのは、多くは企業の中核を担っている働き盛りの世代です。彼らが介護していることを言い出せずに思い悩み、心身の負担が限界を超えて離職してしまったら、本人にとって不幸であるばかりか、企業にとっても大きな痛手となります。
2.介護離職にはこう備える
このような事態を招かないために、企業は今のうちに以下のような取組をしておきましょう。
(1)「介護離職をさせない」という発信
まずは、企業が「介護が必要になっても辞めてはいけない」と発信することが大事です。それがあってこそ、従業員は、仕事を続けるという発想が持てるようになります。
(2)相談窓口の周知
(1)と併せ、従業員が介護に直面したときに、相談できる体制を整備し、それを案内しておきましょう。それがないと、冷静に考えることもできずに退職を決めてしまいかねません。従業員に、いざというときに思い出してもらえるよう、「相談できる場所がある」ことを継続的に知らせましょう。
(3)介護に関する制度の案内
(2)の相談窓口は、介護をしながら働き続けられる制度を案内しましょう。支援制度として、主に以下の2つがあげられます。
①介護休業制度
育児・介護休業法には、介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度が定められています。この期間は、企業は給与を支払う義務はありませんが、雇用保険の被保険者が介護休業をした場合、一定の要件を満たすと、雇用保険から介護休業給付の支給(賃金の約67%)が受けられます。
もっとも、介護期間の平均は4年7ヶ月(※3)、そして先の見通しも立ちにくいものです。そのため、介護休業は、介護に専念することを前提に取得するのではなく、介護サービス利用に向けた準備や調整のための休みと捉えましょう。通院の付添いは介護休暇(対象家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで、1日または時間単位で取得可能)、夕方に見守りや手助けが必要な場合は短時間勤務等の制度や所定外労働を免除する制度などを活用すると良いでしょう。
②介護保険制度
介護をしながら働き続けるためには、一人で抱え込まずに、介護サービスを活用することも大切です。相談窓口では介護保険の利用を勧めましょう。介護保険とは、40歳以上が加入する公的な社会保険制度であり、65歳以上が主な制度利用対象者です。
介護保険を利用するには、市区町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。認定を受けたら、介護のコーディネータ役であるケアマネジャーと相談して作成したケアプランに基づき、サービスを受けることができます。
相談窓口では、サービスの詳細まで把握する必要はありませんが、従業員に、「地域包括支援センター」の存在は知らせておくことをお勧めします。地域包括支援センターとは、地域の高齢者などの相談対応や介護予防、サービスの連携・調整業務を行っている公的な相談機関のことを言います。
制度の詳細は、厚生労働省「介護休業制度 特設サイト」もご参照ください。
(4)実態把握調査の実施
介護は実態が見えにくいものです。「介護をしている従業員は我が社にはいない」と思っていても、実は人知れず介護をしている従業員がいるかもしれません。そのような従業員が本当にいないか、ぜひ調査をしてみてください。その調査そのものが「介護を打ち明けやすい雰囲気作り」に繋がるかもしれません。
実態把握調査の例は、厚生労働省「仕事と介護の両立支援実践マニュアル」に掲載があります。
3.「誰にも起こりうる」ことを認識しましょう
介護と仕事の両立に関する悩みは、いつ、誰が抱えることになるか分かりません。制約を持っても働き続けられると伝えていくことは、従業員に大きな安心感を与え、人材の流出を防ぎます。今から必要な制度を整え周知するとともに、困ったときに休みを申出しやすい職場風土を醸成していきましょう。