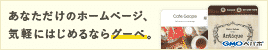インフォメーション
小さなお店のためのSNS活用術 ~0円でパート・アルバイトを10人採用、フォロワー 1. 5万人 八百屋コウタの成功事例~
Instagramの活用について、実例をもとにポイントを解説します。
経営の疑問を専門家が解決(経営Q&A) 売上増加経営資源(ヒト・カネ)
Question
人口の多くない地域で小さなお店を経営しています。より多くの顧客を獲得したり、人を採用したりすることにSNSの活用を検討していますが、あまり知識がありません。宣伝広告費をかけられない小さなお店でも始められるSNSの活用術を教えてください。
Answer
SNSは無料で利用でき、かつ幅広く発信できるツールであるため、費用をかけずに宣伝広告したい場合には検討すべきツールの一つです。ただし、やみくもに発信すればよいという訳ではありません。どう発信するか、しっかり戦略を立てて活用していくことが大事です。
神奈川県平塚市の「八百屋コウタ」はどこにでもある八百屋さんですが、SNSを活用することで「遠くからでもわざわざ八百屋コウタの商品を買いたい」という人を集めたり、百貨店への出店が決まったりと業績を拡大させています。同時に新たな店舗出店のためにパート・アルバイトを採用しましたが、その募集にもSNSを活用しています。広告などは出していないため、採用にかけた費用は「0円」です。八百屋コウタが何をしたか、実例をもとにSNSの活用術を本号と次号の2回に分けてお伝えします。
<八百屋コウタのSNS戦略>
八百屋コウタが使用しているのは主にInstagramです。徐々にフォロワー数が増え、現在、Instagramのフォロワーは1.5万人となっています。
Instagramの活用を機にSNS上で口コミが広がったことで、百貨店への出店が決まるなど事業展開にも影響しています。
そんな八百屋コウタの3つのSNS戦略を紹介します。
1.フォロワーがとにかく「おいしそう」「食べてみたい」と思う写真をアップ
八百屋コウタは新鮮な果物を活かして、フルーツパーラーも営んでおり、お店で作っているケーキなどの商品を、次々にInstagramにアップしています。
Instagram活用のきっかけはシンプルなもので、フルーツサンドなど食べ物を取扱うお店がInstagramに商品をアップし「いいね!」を集めて「バズる」ことで、来店客を増やしたり、商品の販売注文につなげたりしている様子を見て、うちの店でも同じことをやってみようと考えたことです。
また、Instagramは投稿を無料で行うことができるので、それで来店客や注文が増えるならば、行うだけでプラスだとも考えました。
ただし、お店の商品をアップするだけならば誰にもできそうですが、投稿に関しては徹底して高いクオリティを意識しました。特に重要なのは写真です。ピントがずれているものなど、適当に撮影した写真は絶対にアップしていません。また、お店が扱う商品と関係のないものも一切載せていません。
また、ただ商品の写真を載せるだけでなく、店舗名も写すようにし、「あのおいしそうなスイーツを作っているのは八百屋コウタ」と写真を見ただけで認識してもらえる構図を常に考えているのです。
2.ハッシュタグ戦略
ハッシュタグ(「#」)とはSNS上において、キーワードやトピックを分類するタグのことです。 「#」の後に任意のキーワードを入力すると、そのキーワードがタグとして投稿に加えられます。このハッシュタグによって、何についての投稿なのか端的に表すことができます。
ハッシュタグをつけることで「自店舗のブランディング」「興味のある人への拡散」「地域の絞り込み」「その他行いたいことへの訴求」へと繋がっていきます。
Instagramでは、購入した商品や料理の写真を投稿する方が多くおり、投稿時にはお店が使用しているハッシュタグを引用することがほとんどです。そのため、広めたいキーワードを決め、ハッシュタグをつけて投稿することが重要です。Instagramを見て来店した顧客が、お店のハッシュタグをつけて投稿してくれることで、「SNS上の口コミ」が発生しやすくなります。
例えば、ある顧客が八百屋コウタの商品を買い、「#八百屋コウタ」をつけてInstagramに投稿すると、フォローしている別の人が八百屋コウタの存在や商品を知ることに繋がります。フォロワーには学校の同級生など、商圏に住む人もいることが多いため、さらなる来店が期待できます。
八百屋コウタでは、Instagramで「フルーツサンド」と検索された場合に、自店の投稿が表示されるよう、取扱い商品の種類名でもハッシュタグをつけています。これにより、「フルーツサンドに興味がある人」という大きなマーケットに自店の存在を知ってもらうことにつながります。フルーツサンドに興味がある人にお店に気づいてもらいやすくなり、アカウントのフォロワーが増えるきっかけになります。多くのフォロワーがいるとInstagram上で検索時以外でも表示される回数も多くなり、一層拡散力が高まっていきます。
「#湘南」「#平塚」「#藤沢カフェ」「#湘南スムージー」など=地域の絞り込み
売上を伸ばしていくためには、商圏の人に来店してもらうことが重要です。その地域の人やその地域に来る人に多く見られそうなハッシュタグをつけることで、地域色を強し、近隣住民や観光客に「行ってみたい」と思わせる動機に繋がります。
3.採用に関する情報をアップ
八百屋コウタでは、「スタッフを募集している」と見てわかる写真と条件をできるだけ詳しく明記した記事を投稿しています。「まず問い合わせてもらった後に、詳細を説明する」のではなく「その条件で働きたい」人を集め、問い合わせ時はいつ面接に来てもらえるかなどの具体的な話につながるようにし、効率よく採用活動を進めています。
Instagramは多くの文字も投稿できるので、写真だけでなく文字で必要な情報を伝えるのにも向いています。興味関心のある人は長い文字数でも読んでくれるため、twitterのように短文での投稿に限定する必要はありません。また、Instagramでは、写真を複数投稿でき、過去の記事も同時に表示できることから、一般の採用情報誌や採用Webページよりも店の雰囲気をより伝えやすく、働く姿を想像してもらいやすいという利点があります。
実は、Instagramは採用活動に適した媒体となっているのです。こうして八百屋コウタは「0円」で、常に採用を可能にしています。
米原市から園芸作物生産振興事業補助金の採択を頂きました
7月28日付で、表記の補助金申請が採択されました。
具体的には、野菜の乾燥機を購入する補助金です。
昨年からイチジク栽培を始めました。
イチジクは日持ちがしませんので収穫したらすぐに販売しないといけません。
日持ちをするようにするためには、まだ固いうちに収穫しないといけません。
当然、樹上完熟した方が甘いです。
余談ですが、スーパーに売っているトマトは青い状態で出荷されています。
2週間ほどおいて赤くなってから陳列されています。
うちのトマトは樹上完熟です。
見た目は全く同じですが、味は全く違います。あと2か月ほどすると秋作ができますので、また試食してみてください。
さて本題に戻しますが、露地栽培のイチジクは見た目もイマイチなんです。
風による擦り傷や、色むらなどがあると、販売してもほとんど売れないのです。
なので、こういったイチジクは自家消費するか、知人に贈呈するかなんですが、量が多いと廃棄するしかありません。
とてももったいのです。
一方で、スーパーや土産物店には、ドライイチジクが販売されています。
調べてみると、ドライイチジクの販売には許可は不要とのことでした。
できれは野菜乾燥機が欲しいなあと思っていたのですが、かなりのお値段になりますので、なかなか投資に踏み出せませずにいました。
そういった中で、米原市から表記補助金募集が始まりましたので、応募したところ採択頂きました。
たいへんありがとうございます。
野菜乾燥機は大切に利用させて頂きます。
販売するには、試行錯誤が必要で、かつ、ロゴマーク、パッケージや販売ルート確立も必要です。
自分なりに考えて「加工品」として販売していきたいと思ってます。
企画会議の技法を取り入れて、新しいアイデアを商品開発や販路開拓に用いる
商品開発や市場開拓において、なかなかいいアイデアに恵まれないという企業では、新たな技法を取り入れてみてはどうだろう。ブレインストーミング、バックキャスティング、ファシリテーション、アイデアの評価、アクションプランの策定など、こうした企画会議の技法を試して社員の多様な意見が集まるようになれば、思わぬ活路が開かれるかもしれない。こうした技法を使い分けることで、商品開発や販路開拓のため、競合他社にはない新鮮なアイデアを取り入れられるようになる。また、消費者や取引先にとって新鮮に受け入れられることで、売上などの指標も向上するものと期待される。
1.企画会議に取り入れたい4技法
企画会議では、参加者から新しいアイデアが出されて、そうしたアイデアが商品開発や販路開拓のために使われるようにしなければならない。しかし、ただ単に会議の場を設けるだけでは、効果的な企画会議を進めることは困難だろう。そこで、効果的な企画会議を実現させるために取り入れたい5つの技法を紹介したい。
(1)ブレインストーミング
企画会議が成功するかどうかは、ブレインストーミングがうまく行くかどうかが鍵を握っているといっていい。ブレインストーミングとは、その場の参加者が自由にアイデアを出し合える「バズセッション」の雰囲気をつくることによって、個々の努力だけで思いつくことが難しい斬新な発想や解決策を導き出すための手法である。
大量の情報が常に流通し、類似する品質の商品が容易に出回るコモディティ化が促進され、他社の売れ筋商品を模倣することも難しくなくなった現代社会では、ビジネス上の優位性を確保するための「新鮮なアイデア」がますます求められてきている。
他社の成功例を模倣するノウハウは多いが、新しいアイデアを導き出すノウハウは少ない。その中でも有効なノウハウと考えられているのがブレインストーミングなのである。ブレインストーミングに必要なバズセッションの雰囲気を醸成し、革新的なアイデアを得るためには、次の基本ルールを守らなければならないとされている。
1.批判禁止
他人のアイデアに対して否定から入ったり、頭ごなしにバカにしたりするクセがある参加者もいるだろうが、ブレインストーミングの場では絶対禁止である。批判は参加者を萎縮させ、いいアイデアが出る可能性を縮小させるためである。アイデア出しの段階で、批判は百害あって一利無しといえよう。
2.質より量
できるだけ素晴らしいアイデアを出して、褒められようとして、頭の中で捏ねくり回している時間は、ブレインストーミングにとって無駄である。思いついたらすぐにアウトプットして、他の参加者からのさらなるアイデアを誘引した方がよほど生産的である。ひとつのアイデアの品質よりも、むしろ、たくさんのアイデアを出した参加者が讃えられるブレインストーミングの場にすることが望ましい。アイデアの品質については、後で評価すれば十分である。
3.アイデアの組み合わせも自由
他の参加者が出したアイデアに触発されて、さらに新しいアイデアへと膨らませたり、自分のアイデアと組み合わせて新たな価値を創造したりすることも、ブレインストーミングの場では自由でなければならない。複数のアイデアの相乗効果(シナジー)で、他社の追随を許さないほど新しい商品やアイデアが生み出される可能性にも期待できる。よって「それはパクリだ」「自分が先に出したアイデアだ」などと、他の参加者を非難することは禁じられるべきである。
4.一見して関係ないアイデアも歓迎
あらかじめ設定した企画会議の目的やゴールからは、一見すると関連しないアイデアであっても、ブレインストーミングの場では受け入れなければならない。アイデア出しをできるだけ制限しない態度を取っていれば、斬新な発想を誘発することにもつながる。
5.ダメなアイデアをあえて出し合う
「これはさすがに不採用だろう」と、それぞれの参加者が思うようなアイデアでも、遠慮なく出し合える楽しい場をブレインストーミングで演出できれば、最高のアイデアが生まれる可能性が高まる。斬新な発想は、どこに埋もれているかわからないからである。同じ理由で、自社の既存商品やサービスを逆に悪化させるアイデアを出し合うことも、凝り固まった思考回路から各参加者が解放され、より創造的なアイデアを導き出すチャンスになりうる。
(2)バックキャスティング
バックキャスティングとは、会社が目指したい商品開発や販路開拓の目標を達成するため、将来の自社にとってあるべき姿を想定し、その実現のために現在必要となる手段を、逆算的に導き出す方法である。このバックキャスティングも、企画会議に取り入れて有効活用することができる。
バックキャスティングを効果的に実践するためには、将来のあるべき姿をできるだけ具体的に描き出し、将来のあるべき姿を実現するための必要条件を、できるだけ多く洗い出す必要がある。このバックキャスティングは、中長期的な取り組みに関連するアイデア出しに適しており、短期的な問題解決には向いていないといわれる。よって企画会議の目的ごとに、バックキャスティングを取り入れるべきか吟味する必要も生じる。
(3)ファシリテーターの採用
可能であれば、議論を促進し、参加者から話を引き出すための「ファシリテーター」役の人物を用意しておきたい。アイデアが活発に交換されやすく、企画会議が成功する可能性が高まるためである。
企画会議でのファシリテーターは、司会者とは役割が異なる。司会者は、あらかじめ定められた会議の式次第に沿って、その場を滞りなく進めることが主な役割だが、ファシリテーターは、会議の参加者から意見や疑問などを引き出し、議論が円滑に進められるよう中立的な立場から取り仕切り、最終的に合意を導き出すところまで責任を負う。
(4)質問会議
その名の通り、質問とそれに対する回答のみで行われる会議のことだ。もともとは米国ジョージワシントン大学大学院のマーコード教授によって開発され、日本ではNPO法人日本アクションラーニング協会が提唱している。
質問会議では、参加者の一人が「アクションラーニング・コーチ」(ファシリテーター)として進行役を務め、役職や先輩・後輩にかかわらず自由に発言できることになっている。
会議の参加者は自発的に意見を言えないため、導入当初は欲求不満が募りがちだ。とくに役職者等にはその傾向が強く見られがちだが、上からの立場で意見を述べる人はアクションラーニング・コーチによって退場させられることもあるという。
解決策を考えるのではなく、問題がどこにあるかを考えることからスタートする。最初から自分の考えを押しつけるのでは無く、参加者全員がそれぞれの角度から考え始めることになる点が質問会議の大きな特色だと言える。
2.企画会議後の2つの技法
(1)アイデアを評価する場を設ける
ブレインストーミングやバックキャスティングで出てきたアイデアは、いくら独自性が高く、創造的であっても、そのままでは実現可能性や商品としての価値が不明確である。そこで、アイデアの実現可能性や成果性などを客観的に評価する場も設ける必要がある。アイデアを評価する手法は様々あるが、いずれにせよ、アイデアを出し合うブレインストーミングの場と、出てきたアイデアを評価する場は、切り離されなければならない。
アイデアの評価は、たとえば、次のような基準に基づいて行う。
1.新規性
そのアイデアが、どれだけ独創的で、競合他社には見られないかどうかを評価する。
2.有用性
そのアイデアが、どれだけ市場や顧客のニーズに応えられる可能性があるのか、どれだけ既存の商品やサービスに付加価値を提供できるかどうかを評価する。
3.実現可能性
そのアイデアが、現実問題としてどれだけ商品やサービスとして具体化できる可能性があるのか、可能性があるとして、実現までにどれだけの時間やコストを要するかを評価する。
4.成果性
そのアイデアが、どれだけ商品開発や市場開拓に貢献し、どれだけの収益を会社にもたらしうるかを評価する。
(2)アクションプランの作成
ブレインストーミングやバックキャスティングで出てきたアイデアを評価した後は、実際の商品開発や市場開拓のために、行動ベースで取り組めるようにするアクションプランを作成しなければならない。アクションプランとは、具体的なタスク、担当者、期限を設定し、必要な資源や予算などを明らかにした計画のことである。どんなに斬新なアイデアであっても、アクションプランに落とし込めないアイデアは無駄になってしまう。
アクションプランを作成していくためには、アイデアを「商品開発」「販売促進」などのカテゴリ分けを行って、担当者を明確にし、さらに緊急度や優先順位を基にしてランク付けし、ランクの高いアイデアから具体化していく手続きが必要である。
アイデアのランク付けには、作業時間を考慮することも重要である。中でも短時間で完了しそうなアイデアをタスクとして優先的に処理することで、より効率的に目標達成へ近づいていくことができる。
V字回復を果たしたドムドムハンバーガー社長に聞く!「思いやり経営」で結果を出す組織を作る
景気の停滞、人口減少――。さまざまな環境変化の中で、時代に合わせた事業展開をどのようにしていけばよいのか、頭を抱える経営者も多いのではないでしょうか。
今回は日本最古のバーガーチェーン店「ドムドムハンバーガー」をV字回復させた、ドムドムフードサービス社長 藤﨑 忍さんに、自身の経験から学んだ「結果を出す」経営術から、心がけている習慣、独自性のある企画を生み出すチームづくりまでお伺いしました。
39歳まで専業主婦だったという藤﨑さんが109のアパレルショップ店員、居酒屋の店主という異色の経歴を経て同社の社長に就任したのは2018年のこと。ユニークなアイデアで当時のドムドムのイメージを覆し、さまざまな施策で黒字化を実現しました。ぜひ、経営戦略や組織づくりの参考にしてみてください。
目次
· リーダーとして、具体的に行っていることを教えてください。
· ドムドムハンバーガーをどのようにV字回復させたのでしょうか。
· ドムドムハンバーガーでの経営手法について教えてください。
経営における「リーダーとしての信条」を教えてください。
私はこれまでの経験から「和をもって事を運ぶ」「尊重と思いやり」を、経営における信条に掲げています。
2018年にドムドムハンバーガーの社長に就任しましたが、その前にSHIBUYA109のアパレル店に勤務していました。当時の私は39歳の元専業主婦。それまでの人生でかかわることのなかった、いわゆる「ギャル」と呼ばれるスタッフたちとコミュニケーションを取る中で、それぞれの捉え方や考えがあるということに気づかされたのです。
固定観念に捉われず、仕事へ対する思いや「渋谷のカルチャー」を担う彼女たちへのリスペクトを伝えていくにつれ、彼女たちもまた私を尊重してくれるようになり、チームで店づくりをしよう!と積極的に参加してくれるようになったのです。その結果、売上は大きく拡大しました。
この経験から、私は「良い組織であることが、どれほど重要か」を学んだのです。性別や年齢に捉われず相手を尊重する姿勢は、組織の大小にかかわらず非常に重要となります。
リーダーとして、具体的に行っていることを教えてください。
一人ひとりとのコミュニケ―ションを大切にしています。特に社長に就任した当初は、自分自身を従業員に理解してもらうために、各店舗に足を運び、何気ない会話を積み重ねました。些細なことでも互いに言い合える関係性を築けるだけでなく、各店のオペレーションなどの改善点も明確になるので、社員とのやり取りは重要なアプローチです。
現在でも、毎朝の雑談で相手の変化を察知したり、対面でない場合は、些細な内容のメールにも必ず返信したりと、小さな積み重ねを大切にしています。
ドムドムハンバーガーをどのようにV字回復させたのでしょうか。
「ドムドムハンバーガーとはどんな会社なのか」を明確に把握したうえで、これまでの概念とは異なるイメージを打ち出しました。声優やアパレルブランドとのコラボイベントを企画した際は、社内の各所から反対意見が相次ぎましたが、結果として企画は大成功しました。新しいチャレンジを繰り返し、新たな顧客層を獲得できたことが業績回復の直接的な要因として挙げられるのではないでしょうか。もちろん、ハンバーガー店として「おいしい」を原点に置き続けていますが、固定概念に捉われない取り組みが、今の「ドムドムハンバーガー」らしさを築いたのです。
帽子やバックパックだけでなく、ポロシャツやパーカーなども展開している
また、SNSを活用したことも大きいでしょう。ドムドムには、歴史あるハンバーガーショップとして愛着や期待を持っていただいているファンも多くいらっしゃるのですが、そういった方々とSNSを通してより親密になることで、ドムドムを一緒に作り上げていく動きが加速しました。結果として、お客さまに寄り添いながらブランドを育むことに成功し、さらなるファン獲得へとつながりました。
ドムドムハンバーガーの独創的なハンバーガーはもちろん、公式アカウントのアイコンでもある「どむぞうくん」が多くの方に愛されるようになったことには、驚きと嬉しさを感じました。現在では、企画立案は各担当者を中心に行いますが、固定概念に捉われない思考は、会社の文化として根付いています。互いを尊重し合い、従来の枠にはまらない思考を持つことこそが、売上拡大の核心にあると考えています。
ドムドムハンバーガーでの経営手法について教えてください。
ドムドムらしさを体現する柔軟な企画の数々は、各社員が担当していますが、文字通り各社員に裁量を委ねています。企画立案時に求める条件も、特に定めていません。大切なのは本質であり、企画者の熱量です。熱量があればより熟考しますから、自ずと責任感も強まりますし、説得力も増します。数字はその結果として後からついてくるものですから「考え抜いた企画がまったく売れないことはない」と、企画者を信じ抜くことが大切です。
もちろん、経営の視点では費用対効果を考慮する必要はありますが、当事者に対して売上至上主義を求めることはしません。会議においても、アイデアに異を唱えることはあっても、アイデアを出した人物を否定したり、頭ごなしに「却下」と伝えたりすることはありません。そのような環境があるからこそ、社員からは次々にやりたいこと、言いたいことが出てきます。柔軟性に富んだ企画が次から次へ出てくる企業文化を築くうえで、重要な経営手法といえるでしょう。
また、社員全員に仕事の意義を実感してもらうために、自社が今何をしているか、どういう形で社会貢献できているかを、管理部門も巻き込んで共有しています。売上はさまざまな施策の相乗効果で生まれるものです。店舗売上が増加した理由を分析すると、SNSでの施策が起因していることもありますよね。部署を超えた互いの施策のかけ算で、良い結果が出るという共通認識があれば、社内の情報共有は活発になり、一丸となって取り組むことができます。その関係性は売上を生むだけでなく、会社全体を良い方向へ導いてくれるのです。
経営課題にはどのように対応すべきでしょうか。
そもそも、ドムドムでは「課題」という言葉は使いません。数字はもちろん、社員やお客さまの声、あらゆる事象を成功へのヒントと捉え、考察後その場で指針を決定し、スピード感を持って実行します。実際に行動する際は私の意見も伝えたうえで、最終的な意思決定を担当者に委ねています。結果が振るわなくても、それは失敗ではありません。スピード感を持って常に改善を続けていけば、その道中で得た知見やノウハウは必ずあり、その集積が次につながるのです。
例えば、ドムドムのマスコット「どむぞうくん」のグッズ発売開始前日に、Twitterで情報を開示した時のことです。ありがたいことに公開後、すぐに話題沸騰となりましたが、たくさんの好意的な反応の中に「販売方法を変えたほうが買いやすい」というツイートがありました。それを発見した営業部長はすぐに社内で共有し、販売チームは指摘通りにサイトの販売方法を急遽変更して、翌日の発売開始にこぎつけました。その結果、想定した以上に大きな売上を獲得することができたのです。着手すべきという結論に至ったら、担当者が裁量権を持って迅速に対応するという企業体質がもたらした結果だと感じています。
コロナ禍を経て、改めてリーダーは何をすべきでしょうか。
今一度、自社がどんな会社なのか、自分に合う経営スタイルは何なのかを、立ち止まって考えてみる必要があると感じています。多様性の時代ですから、企業それぞれのスタイルやリーダー像があると思いますが、経営理念に反してさえいなければ、いろいろな取り組みを積極的に行ってみるのもいいでしょう。
最初から上手くはいかないかもしれませんが、事象に対して1つ1つ対策を打ち、社員を信頼して少しずつ前進してみてください。それこそが、前途洋々たる未来への近道です。きっと、できることはまだたくさんあります。1人で対応しようとせず、社員とその歩みを積み重ねていくことこそが、リーダーの在り方なのではないでしょうか。
広告運用開始わずか3か月で売上214%アップ!中小企業だからこそ活用したい「リスティング広告」とは
インターネットで何かを検索すると検索結果の一番上に時折見かける「広告」や「スポンサー」という文字。「うちの商品の広告もこんな感じで出せたらなぁ……」「でも結構お金も手間もかかりそう……」なんて考えていませんか?
「リスティング広告」と呼ばれるこのタイプの広告、実は中小企業にもってこいなのです。その理由は、予算が少なくても効率的に商品の購入へつなげられるから。ポイントを押さえてしっかり運用すれば3か月で売上を2倍に伸ばすことも可能です。
今回はリスティング広告運用のプロである、株式会社バリューエージェントの上野山 光雄(うえのやま みつお)さんに、リスティング広告が中小企業に最適とされる理由や、実際に広告を開始する手順・ポイントについてお伺いしました。
· 少額から始められる!だから中小企業にこそリスティング広告がおすすめ
· リスティング広告に適している商品・サービスの「見極め」と「始め方」
· 定期的なキーワード見直しで購入率アップへ!リスティング広告運用の極意
少額から始められる!だから中小企業にこそリスティング広告がおすすめ
そもそも、リスティング広告とはどういったものでしょうか。
一般的にリスティング広告は、別名「検索連動型広告」と呼ばれる文章広告を指します。検索エンジンで、何かキーワードを調べたとしましょう。その際に、検索結果の箇所に「スポンサー」と表示される関連サービスや商品などが出てくるのを見たことがありますか。それが、リスティング広告です。検索エンジンは、主にGoogleやYahooなどが主流ですね。
リスティング広告で期待できる効果は何ですか。
顧客になる可能性が高い「顕在層」の獲得ができます。
リスティング広告の特長として、商品やサービス、関連事象に対して、ある程度興味があるネットユーザーに直接的なアプローチができるという、画期的な点が挙げられます。
従来の広告は、不特定多数の潜在顧客に向けて情報発信し、何度も接点を持つことで購入につなげるケースが大半でした。一方でリスティング広告の場合は、対象物に対して一定数の興味値を持ったネットユーザーに、選択肢の1つとして自社製品・サービスを視認させることができますから、リスティング広告は直接的な購入につながりやすいと言えるでしょう。
なぜ中小企業におすすめなのでしょうか。
リスティング広告は、予算が少なくても、購入検討するユーザーにアプローチできる可能性が高いため、中小企業がまず取り組むべきインターネット集客の1つとして推奨しています。
大手企業は、CM打ちや雑誌での訴求など、大規模かつ長期的に仕掛ける傾向にありますよね。一方中小企業は、販促予算や人材などが限られていることも多いです。限られたリソースを活かして実績につなげる必要のある中小企業には、より効率良く顧客を獲得できるような販促施策が適しているのです。
リスティング広告で売上が伸びた成功事例を教えてください。
弊社がリスティング広告をサポートした企業さまでは、さまざまな業種で売上拡大や問い合わせ倍増などの例があります。例えば黒毛和牛の通販サイトでは、広告運用開始3か月で、昨年比214%の売上を獲得しました。人事労務管理サービスを展開する企業は、1か月の新規顧客数が平均14件だった状態から、3か月後には68件に増加しました。これらはリスティング広告だけで結果につながった例です。
商品やサービスが良いことはもちろんですが、適正な打ち出し方や運用方法で、対象物の可能性をさらに引き出すことが可能です。関連するキーワードを大きく洗い出し、テストを繰り返した結果、2社とも予想を超える実績につながりました。
リスティング広告に適している商品・サービスの「見極め」と「始め方」
リスティング広告に適している商品・サービスはありますか。
大前提として、リスティング広告を打つ商品やサービスが「検索されるかどうか」が重要です。この世にまだ無いまったく新しい商品や、ユーザーのニーズが見えてこないサービスは、そもそも関連するキーワードを検索する人が少ないですよね。そのような場合は、まずニュースリリースなどを打って、世間に知ってもらうことから始めるとよいでしょう。
逆に、その点だけを留意すれば、あらゆるものやサービスをリスティング広告で打ち出すことが可能です。一般的にはB to Cの物販をイメージされる方も多いかもしれませんが、実はB to Bのサービスや、求人広告なども相性が良いです。検索ボリュームが確立されていれば、リスティング広告は比較的どんな対象物にも適していると考えられています。
リスティング広告を始める際には、何から手を付ければ良いでしょうか。
私たちがリスティング広告を打つ際に推奨している検索エンジンは、ユーザーボリュームの大きいGoogleのため、Googleを使った導入方法を解説します。「Google広告」とインターネットで検索すると、Google Adのページが表示されるので、広告アカウントを作成してください。「キャンペーンを開始する」を選択し、指示に従って広告設定を進めると、運用開始となります。
リスティング広告は、1回クリックされるごとに費用が発生する「クリック課金」という仕組みになっているのですが、上限額を設定できるので想定外の大きな広告費がかかることはありません。その他、地域・属性などの細かいターゲティングも可能です。
ネットでリスティング広告の設定方法を調べると、たくさん解説サイトが出てきますが、下調べに時間をかけるより、実際に手を動かしながらチャレンジすることをおすすめします。Google広告の設定仕様は定期的に更新されていきますし、作成してみてわかることも出てくると思います。
定期的なキーワード見直しで購入率アップへ!リスティング広告運用の極意
検索キーワードに関しては、どのように設定すべきでしょうか。
広告設定の際に、どのような検索キーワードと連動させて広告を表示させるかを決めますが、検索キーワードの設定も非常に重要な要素です。リスティング広告には、自動で関連キーワードを追加してくれる機能があります。日々のキーワード管理が難しい時にはとても便利なのですが、その中には関連性の薄いキーワードも入っている可能性が高いです。
例えば建築関係の求人広告を打っている場合「現場監督 資格」などのキーワードを設定してしまうと、仕事を求めている人ではなく、現場監督の資格に関して調べている人に広告が配信されることになります。システム任せにするのではなく、本当に検索キーワードが商品・サービスに適しているかどうか、自身で検索して確認する必要があるでしょう。
また広告運用画面には「検索語句」というページがあります。このページに掲載されているのは、実際にユーザーが検索した語句です。検索語句から、実際に広告をクリックした回数なども表示されています。狙ったキーワードからの流入であればよいのですが、自社商品・サービスとまったく関係のない検索語句からの流入が大きいと、購入につながる確率は低く、広告の無駄打ちとなっている場合が多いです。
対策としては、次からその検索語句で広告が表示されないように、対象の検索語句を「除外キーワード」として設定することで、広告費を削減し、その分購入確率の高い広告打ちができるようになります。
これらのキーワードに関しては、日々のニュースやトレンドなどで変動します。細かく動向をチェックし、調整していくことで広告の精度を上げることが重要です。
リスティング広告を始める際に、押さえるべきポイントを教えてください。
リスティング広告は「広告見出し」と「説明文」から成り立っていますから、まずは端的に商品・サービスの強みを伝える内容を考えることが大切なポイントとなります。ネットユーザーはこの文章を見てクリックするかどうかを判断しますので、広告見出しと説明文は非常に重要です。
広告文だけが目を惹く内容であっても、実際の商品が伴わっていなければクリックされるだけで終わってしまいます。よく「クリック率が高ければコンバージョン率(商品購入などの目標値)も上がる」とハウツー本などにはありますが、このロジックは、大手企業が潤沢な予算をかけて広告運用を行う際に挙げられるものです。
限られた予算のなかで、最大限の効果を得るためには、本当に購入を検討しているネットユーザーに広告をクリックしてもらう必要があります。ポイントとしては、広告文とLP(ランディングページ=広告を経由して最初にアクセスされるページ)の内容を一致させ、広告をクリックした閲覧者を不安にさせないようにすると、購入率も上がるでしょう。
同じタイミングで、LPの内容に関しても商品・サービスの打ち出し方は適しているか、ターゲット像は明確かなど、今一度確認しましょう。
リスティング広告を運用する際のポイントはありますか。
先ほどもお伝えした検索キーワードのように、ネット検索の状況は日々刻々と変わっていきますから、リスティング広告も検証を続けていく必要があります。短い期間で修正を繰り返しても、検証に必要なデータが少ないと正確な判断ができないため、2週間に1回を目安に、検索キーワードや除外キーワードの検証を行いましょう。実際に検索してみるほか、競合他社がどのような広告を打っているのかを参考にするのも有効です。また、検証の精度をさらに上げるためには、リスティング広告を経由してLPに流入した数を明確に測定するために、LPにトラッキングのためのタグを埋め込むなどの操作が必要になります。
よく聞くのは「とりあえずセッティングしてみたものの、定期的に眺める程度の調整しかしていない」というケースです。せっかく取り組んでいるにもかかわらず、予算を消化するだけの広告になっている可能性も高く、非効率な状況です。どうしても対応が難しい、より結果を確実に出したいというケースであれば、広告運用代行などの有識者に依頼することをおすすめします。その際は丸投げではなく、実際に広告を運用する当事者と接する機会を設けてもらえるのか管理画面を共有し、検索語句などを見せてもらえるのかなどの点を確認しておくと、安心できるでしょう。定期的なレポート報告のみを行う会社もありますので、信頼できる運用代行かどうかは慎重に判断しましょう。
その他、社内で担当者をつけて運用する方法もよいでしょう。担当者に適任なのは、自社の商品・サービスをしっかりと理解し、消費者目線で打ち出せる人物です。
また、広告を運用して3か月たっても効果を感じられない場合は、広告やLPの見直しのほかに、商品・サービス自体の在り方も検討すべきです。リスティング広告はあくまでも売上促進の1つです。多方面から常に改善を続けることで、売上を獲得できるようになるでしょう。