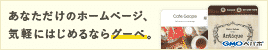インフォメーション
事業継続力強化計画が認定されました
20230922近畿第3号 令和5年9月25日
成宮 農園 殿
近畿経済産業局長 三浦 章豪
事業継続力強化計画に係る認定について
令和5年9月1日付けをもって申請のあった事業継続力強化計画については、 中小企業等経営強化法第56条第1項の規定に基づき認定する
PDFで貼り付けられるといいのですが、技術的にできないので、認定文章を転記しました。
いゆわるジギョケイと言われている計画で、ちょうど昨日9月24日の日経新聞の一面に大きく広告されていました。
中小企業版のBCP計画です。
計画を作ってから、認定されるまでに1カ月強を有しました。
ひな形はあるのですが、ひな形を丸写ししたり、単に模倣したりするだけで認定されるほど甘いものではありません。
大企業が公表しているBCP計画や、国の機関の計画を参考にしました。
当社は零細企業ですので、零細企業に合った内容で、当社ができるレベルで作り上げました。
内容はアップできないのですが、もし内容が見たいとか勉強したいという方がおられましたら、ダイレクトメールでご連絡ください。
特に報酬は頂きませんのでご安心を!!
事業継続力強化計画のHPにも掲載されていますが、この計画が認定されると国の補助金の加点項目にもなるのです。
ですので、補助金申請を考えておられる方なら、取得しておいて損はない計画です。
もちろん万一の災害や事故の際には、その計画に沿って動けば、サプライチェーンを切ることなく事業継続できます。
そういった意味で、実務にも補助金申請にも活かせるのです。
会議時に出席者の発言が少なく、困っています。どのようにすれば良いか、教えてください。
飲食店を5店舗展開しています。月1回、すべての店長を集め店長会議をしていますが、発言が少なく盛り上がりません。どのように会議を進めていけば積極的な発言を得ることができますか。
回答
毎月の会議が経営陣から一方的な意見をいう場になってしまうと、会議自体がマンネリ化し、店長が発言を控えてしまいます。「店長会議は店長を応援する場」という認識を持ち、共同で準備をする必要があるでしょう。
【会議の目的】
会議の目的として、以下のような場の共有による情報共有があげられます。
経営陣は全社的な視点から、会社の方針や業界動向などの情報を提供し、店長はこれを踏まえ、今後の店舗運営に活かします。
店長は現場の視点から、店舗の情報を提供し、経営陣はこれを踏まえ、今後の会社経営に活かします。
店長同士の情報共有といった側面もあります。
おさえておきたいことは、なぜ会議では参加者が時間を割いて一つの場に集まるのか、ということです。単に情報をやり取りするのであれば、電話・FAX・メールですむはずです。顔を合わせて情報をやりとりするということは、情報提供者の「想い」を共有する、ということです。ここでありがちなパターンとしては、経営者がひたすら自身の「想い」のみを訴え、押し通そうとし、店長の「想い」を軽視してしまうパターンです。それが高じるといわゆる「吊るし上げ」が発生したり、経営陣の言葉の意味が伝わらなくなったりします。
【人はどのような場合に発言を控えるのか】
人は興味のない話題には発言を控えるものです。会議が経営者の「想い」のみを伝える一方通行の場になってしまうと、会議がマンネリ化します。こうなってしまうと、店長は会議自体に興味を失いますから、発言を控え、発言したとしても可もなく不可もない発言に終始してしまいます。
また、緊張すると発言は控えがちになります。業績の悪い店長を吊るし上げるようなことがあると発言は期待できません。さらに、経営陣の言葉の意味が飲み込めないでいるときは発言が少なくなりますので、一方通行になっていないかどうか確認しながら会議を進めるべきでしょう。
【日ごろの関係づくり】
会議を活性化させるには、まず、店長の緊張を解くことが必要ですが、会議のときのみリラックスできる雰囲気を醸し出そうとしても意味はありません。会議のように顔を合わせる場では、日ごろの経営陣と店長の関係が雰囲気に大きく影響します。日ごろからお互いが何でも言い合える関係を構築するために、経営陣が積極的に店舗を訪問して店長の意見を聞いたり、社内提案制度を設けたりするべきでしょう。これにより、何でも言い合える組織風土を構築することが、会議活性化の第一歩です。
【会議の進め方】
会議で店長に発表をさせる場合は、発表資料をあらかじめ用意させます。経営陣が会議開催の数日前に店長から資料を提出させ、店長の意見を聞いたうえでアドバイスを行い、より完成度の高い内容に修正させ、当日に発表させるべきでしょう。経営陣と店長が準備作業を共同で行うことは、意思疎通や店長の能力開発につながるとともに、店長の緊張もほぐれ、経営陣の考えも理解でき、会議は活性化するでしょう。
創業にあたり基本的な私の考え方
私の創業・事業経営での基本的な考え方は以下の3つです。
・「持続可能」かつ「社会課題を解決し世の中の役に立つ」事業をすること
・事業を分散させ、ストックとランニングのバランスをとること
・利益は公平に分配すること(内部留保・経営者・従業員)
見て頂いてわかるように、「どういった事業をする」ということにあまりこだわりはありません。
逆にやったことのない事業をやってみたいと思うほどです。
今当社は3つの事業展開をしていますが、この3つは、全て私が好きだからやっているだけです。
コンサル業は始めて1年ほどです。
不動産賃貸業は30年やっています。
農業は第一の会社を定年退職してから始めたので5年くらいです。
誰かにやれと言われた訳でも、やむを得ない事情でやっている事業でもありません。
いろんなことに関心があるので、すぐに他人の事業を聞くと「自分でもやりたいな」と思ってしまいます。
しかしながら時間的な制約があるので、やりたいこと全部はできません。
創業の動機は人それぞれです。
やはり自分の好きなことを事業にするのが一番良いと思います。
更に、市場の機会=追い風を受けることができる事業ならかなりの確率でうまくいきます。
事業は必ず成功する訳ではありませんが、自分が好きなことなら苦労に思えないのです。これは不思議な感覚です。
事業計画を考えているといつの間にか朝方になることがあります。それくらい一機に事業計画を書き上げます。メドがつくまでは全く眠くないのです。
アパートの下水管の掃除も自分でしますが(好んでする訳ではないですが)苦労とか思ったことはないです。
廻りの人が寝ている時間に起きていそいそと収穫に行くことも楽しいです。
2番目には、その事業のお客様が「こんなんあったらいいなあ」と思っていらっしゃること=課題を解決する事業であることです。
自分が好きでやりたいだけの事業は、よそ様から見てもなんにも価値のない事業かもしれないのです。
これをプロダクトアウトと言います。よく製造に携わる企業が陥る罠です。
3番目には、ダメだったら勇気ある撤退をすることです。撤退時期の見極めは大事です。
とことんまで行くと、次の復活の芽までなくなります。
今までの経験上「返済する資金のために運転資金を借入する状態」になった時は事業戦略の見直しの時期かと思います。
採算が取れていない事業になっているのです。
そういう状態になると目先の資金繰りに追われて的確な判断ができなくなってくる経営者も増えてきます。
永年企業様を見てきましたが、所要運転資金を上回る借入をしている企業で、復活したケースはあまり記憶にありません。
債務償還年数超過、分類債権登録とかなると簡単に再融資も受けられません。
ちょっと難しい言葉も出ましたが資金繰りは多くの企業様が悩まれますので、悩まれた時は、取引金融機関に相談されたらいいと思います。
通り一辺倒の話しかしないと思いますが、一人で悩んでいるよりましです。
金融機関も貸し手側の立場があるので、本音の話は避ける傾向にあるからです。
よそ様の事業計画をお伺いすることはとても楽しいです。自分ならどうする?と考えるだけでわくわくしてきます。
自分が好きなことを事業にしましょう!!
ご支援します。
専門家コラム「会社ブログやお店ブログにはこれを書きましょう」(2023年9月)
会社やお店の情報発信ツールにブログがあります。個人のブログと区別して会社ブログや企業ブログ、お店ブログと呼ばれています。
今回は、読まれる、反応がある、集客や商談につながるなど、手応えを感じる会社ブログの書き方、題材(ネタ)の考え方を、具体的な方法を含めてお伝えします。
1.会社ブログには顧客が求めていることを書きましょう
(1)自分が書けることではなく、顧客が求めていることを
会社やお店のブログを書こうとすると、とにかく書くことを優先してしまい、また、ブログの題材(ネタ)も、それほど考えつくものではありませんので、とにかく書けることを見つけて書いてしまうことがよくあります。ブログに関して、読まれない、反応がないというご相談が多いのですが、これが原因のひとつです。
大切なことは、会社ブログには「顧客が求めていることを書くこと」です。なお、ここでの「顧客」には「未来の顧客」も含めています。
(2)自分に書けることを顧客に寄り添うイメージで
もう少し丁寧にお伝えすると、書けることを「書いてはいけない」のではありません。書けることを「顧客が求めていることに寄せて書く」、つまり「顧客に寄り添う」というイメージで捉えてください。書けることをそのまま書くと、顧客が知りたいことと重なる部分は限定的ですが、顧客に寄り添って書くことで重なる部分は拡大します。
(3)顧客が消費者の場合は体験できることを書きましょう
顧客が消費者の場合は、商品やサービスそのものではなく、商品やサービスを利用する過程で「体験」できることを書きます。例えば旅行の場合は、目的地への移動や宿泊だけではなく、もてなしへの感動や旅先で目にしたものへの驚きなどの「体験」があります。商品やサービスを通じて「体験」できることを書くと、手応えのある会社ブログになるはずです。
(4)顧客が事業者の場合は、先方の業務上の課題解決を意識して書きましょう
顧客が事業者の場合は、御社が提供している製品やサービスの機能や仕様そのものではなく、その製品やサービスによって顧客の事業上の課題を解決できることまで踏み込んで書きます。例えば計測器を提供している場合、その性能による生産性の向上などを題材に選んで書きましょう。
2.会社ブログに顧客が求めていることを書く理由
(1)自分が書けることではいけない理由
インターネット上には膨大な情報があります。ですから顧客は、自分が求めている情報がどこかにあるはずだ、という姿勢で検索します。その姿勢を言い換えると「わがままでせっかち」です。ご自身が検索する場面を思い起こしていただければ納得していただけるでしょう。わがままでせっかちですから、記事を自分の求めていることと「照らし合わせて解釈する」ような手間はかけません。自分には相応しくない情報である、と瞬時に判断して次の情報を探します。ですから、会社ブログには自分が書けることではなく相手が求めていることまで踏み込んで書く必要があるのです。
(2)消費者は体験できることを探している
ご存知の通り、現在は商品やサービスが溢れています。消費者は商品やサービスそのものが持つ価値ではなく、それらの購買や利用を通じて得られる「体験」に価値を感じるようになりました。例えば、クルマの場合、一昔前は所有の喜びが中心でした。ところが現在では所有だけではなく、購入前の広告接触やディーラーとの対話による期待感、購入後のドライブの楽しみ、さらにアフターサービスの安心感などの一連の「体験」が価値として評価されるようになりました。先に挙げた旅行の場合も同様です。ですから消費者には「体験できること」を書くと、探しているものと合致した情報になるのです(出典1)。
(3)事業者は業務上の課題解決策を探している
顧客が事業者の場合は消費者と異なります。一昔前までは調達に関わる担当者は会社に出入りしている調達先の営業担当から、自社の課題解決のための情報を仕入れていました。ところがインターネットの普及とともに、調達先に会う前に必要な情報をインターネットで収集するようになりました。コロナ禍でリモート業務が広がるとこの傾向が一層強まりまり、現在ではインターネットに情報が載っていない会社には声がかからないとまで言われています。インターネット上にはさまざまな情報が溢れていますから、自社の課題解決に直接結びつかない情報は選ばれないことになります。
3.会社ブログの実践的な考え方と書き方
(1)顧客が消費者の場合、5つの視点で考えてみる
先に述べた「体験」には期待、感動、驚きなどの心理的・感情的な価値があります。
心の動きに関する価値は、研究では人の五感を刺激する感覚的な価値、人の感情に訴求する情緒的な価値、人の知的欲求に訴求する知的な価値、新しい体験などの行動に訴求する行動・ライフスタイルの価値、特定の集団に所属する誇りなどの社会性の価値という5つの種類があるとされています(出典1)。この視点を利用すると会社ブログの題材は考えやすくなります。
(2)共感できる情報も加えてみましょう
人が持つ感覚や情緒、知的欲求などには「共感」も関わってきます。
共感とは相手と同じ気持ちを感じることとです。研究では、共感は親しみと深いつながりがあるとされています。親しみは気持ちの距離を縮めますから来店や購買にも繋がりやすくなりますので、共感してもらえるように書くことも大事です。
共感の種類には、相手と同じ感情を共有して同じ感情を体験する情緒的な共感(大変だったね、など)と、相手の考え方や価値観を認める認知的な共感(なるほど、そうだね)があるとされています(出典2)。
この分け方を参考にすると、情緒的共感を促すには「商品の開発にともなう苦労ばなし」の紹介などが向いているでしょう。認知的共感には「商品を開発した目的や意図などの紹介」などの方向性が考えられます。
(3)事業者の場合は、生産の3要素やマーケティングの4要素で考えてみる
生産に関する課題は、品質の実現や向上、コストの削減、納期の短縮(生産の3要素)に関するものが代表的です。具体的には不良の削減、狙いの性能の達成、環境対応、材料や部品の在庫の適正化などの視点が考えられます。マーケティング(販売)に関する課題は、製品ラインナップ(品揃え)の充実、販売先の拡大、販売価格の向上、新規顧客獲得(マーケティングの4要素)に関するものが代表的です。これらの要素に結びつけて書くと、顧客に寄り添った情報になるはずです。
4.まとめ
読まれる、反応がある、集客や商談につながるなど、手応えを感じる会社ブログの書き方、題材(ネタ)の考え方を、具体的で実践できる方法を含めてお伝えしてきました。ポイントは「顧客が求めていることに寄り添って書く」ことです。
「理屈はわかったけど、やっぱり相手のことはよくわからない」という場合は、客観的な視点を持つ第三者として中小企業診断士への相談をぜひご検討ください。
出典
1.田中達雄「CX(カスタマー・エクスペリエンス)戦略 顧客の心とつながる経験価値経営」東洋経済新報社、2018年
2.山竹伸二「共感の正体」河出書房新社、2022年
(略歴)
大谷 秀樹
「中小企業・小規模事業者の活躍する社会こそが豊かな社会である」を理念に、売上向上などの課題を中心に経営支援に携わる。趣味は酒と料理と落語鑑賞。
中央支部認定 実践的プロモーション研究会 代表
ウェブサイト
https://otanihideki.com?utm_source=tsmeca&utm_medium=chuo