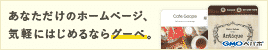インフォメーション
部下の育成につながる「正しい叱り方」
ついつい部下に怒ってしまう、思ったことがすぐ口に出てしまう……。そんな経営者や管理職の間で、今注目されているのが「怒りのコントロール」です。でも「厳しく言うのは従業員のためなのに」と、腑に落ちない方もいるのではないでしょうか。
目次
怒るのは悪いこと?コントロールが必要な理由とは
まず、怒るのはいけないことなのでしょうか?
最初にお伝えしたいのが、怒りは決して悪いものではないということです。人は、自分が大切にしている価値観をないがしろにされると怒ります。怒りが湧いたときこそ、本当の自分に気付けるチャンスです。例えば、仕事の遅い部下に腹が立ったとします。それは、あなたがスピードを大切にしているからです。
しかし、ただ怒っているだけでは周囲を傷つけます。怒るを叱るに変えて、ポジティブな影響を与えられる思考回路に導くのが、怒りをコントロールする目的と言えるでしょう。怒りが自分の感情を晴らすため、相手を責めるためのものなのに対し、叱るは相手のため、あるべき姿に導くためのフィードバックだと考えています。
怒りにフタをするわけではありません。怒りを通して自分を知り、対話することで感情をコントロールします。怒りは相手を攻撃する反応なのです。そして人は怒りを向けられると恐怖を感じて自己防衛本能が働き、心の壁を作って思考停止に陥ります。会社においては、パフォーマンスの低下によって目標を達成できなくなっていきますし、メンタルヘルスやパワハラの問題にもなりかねません。だからこそ、怒りのコントロールが必要です。
自分の実況中継をしてみて。怒りをコントロールする方法
怒りをコントロールするための方法を教えてください。
怒りの感情が湧いてきたら、自分の実況中継をおすすめします。「自分は今怒っているぞ、なぜならば部下が期日を守らなかったからだ」といった具合ですね。人間の脳は生命維持・感情・思考の三層構造になっていて、それぞれの役割を司る場所が異なります。例えば怒りなどを覚える瞬間、感情を司る「大脳辺縁系」という箇所が先に反応してしまいます。このとき自分が怒っていることにすばやく気付けると、思考を司る「大脳新皮質」が動き出して感情を抑えられるんです。つまり実況中継をすることで、自分を客観視できるということです。
先ほど、怒るのは自分の大切にしているものを疎かにされたからとお伝えしました。そんな自分を認めてあげるのも、実は怒りのコントロールに有効なのです。「大事なものを疎かにされたら、怒るのはもっともなんだ」と、自分を励ます・褒めると、気持ちが穏やかになっていきます。そうなれば怒る前に適切なアドバイスができるし、それにより部下が成長したら、そもそも叱る場面もなくなってくるのでは。
自分を実況中継する際に、何かコツはありますか?
実況中継をするときに、なるべく言葉を口に出すと、よりスムーズに感情から思考に移行できます。また、自分を俯瞰しているイメージを作るのも効果的です。もう1人の自分が上から見ていたり、カメラで自分を撮影する姿を思い浮かべるのもよいでしょう。
今すぐできる!部下の育成につながる叱り方
部下の育成につながる叱り方を教えてください。
名前を呼んで、質問言葉を使います。もし、部下が企画書の期限を守らなかったとしたら「Aさん、企画書はどうなっているの?Aさんはスピードを大事にしてるんじゃなかったかな?」と尋ねてください。名前を呼ばれると自分ごとと受け止められるし、質問に対し自発的に考えて行動できるようになります。加えて、責められていないという安心感を与えることも可能です。
さらに、部下と話すときは目を見て話すようにしましょう。人は興味を持たれた相手に関心を持つので、話の内容も伝わりやすくなります。目を合わせることで「あなたに関心がありますよ」と相手に感じてもらうことができるんです。ずっと見られていると緊張する人もいるため、時折視線をそらしてみたりとメリハリをつけるのがコツです。
部下を叱る以前に上司が注意すべきことや、ポイントはありますか?
まず、日常的にコミュニケーションを取ることです。何かあったときだけ叱るのではなく、普段の会話の中でも助言はできます。あいさつ・雑談といった、簡単なやり取りからでかまいません。それにより心理的安全性が担保され、叱りの言葉が響きやすい土壌が生まれます。
次に、会社の目指す方向と部下の目標を共有してください。そして、その道筋を外れたときは叱ると事前に宣言します。前提をきちんと伝えておくことで、何のために叱るのかをお互いに理解できるからです。
最後に、減点主義の意識はなくしていきましょう。できないところを探していると、それが目的になって「できない証明」を始めてしまいます。逆に、できるところを探していると、伸びしろのある部下だと思えてきます。部下だけでなく、自分に対しても加点主義を心がけてください。今までがんばってきた自分を認めてあげると心が軽くなります。
もし、怒りを抑えきれなかったときはどうしたらよいでしょう。
「やっちゃった」はだれにでもあります。もしそうなったら、逃げずに謝るべきです。潔さはむしろ魅力に映り、ついて行きたいというリスペクトにもつながります。リーダーとしての誇りが失われることもありませんし、仕切り直してから叱ればよいことです。
人格否定・他者比較はNG。よくない叱り方の例
よくない叱り方の例を教えてください。
「おまえは使えない」と人格を否定したり、「Bさんのほうが仕事ができる」などと他者との比較で叱ったりするのは、相手に自己防衛本能を働かせてしまいます。長時間・人前で叱るのもNGで、このような行為はパワハラにも該当します。一方で、叱れない上司も増えてきており、これは無視しているのと同じです。上司への不信感につながり、組織に対する忠誠心も失われます。
そして、最近はリモートワークが広がっていますが、メールなどのテキストメッセージで叱るのは避けてください。電話や1対1のオンラインで対応すると、本意が伝わりやすくなります。
部下との衝突を恐れず、一体感に変えていこう
「叱るとパワハラと言われるかも」と躊躇している人も多いと思います。そんな中小企業の経営者や管理職の皆さんに、メッセージをお願いできますでしょうか。
怒りをコントロールして上手に叱れると相手の成長を促すことにつながり、結果も出てくるし、売上・顧客満足度もアップします。反対に上司がいつも怒っていて雰囲気が悪く、部下の思考が硬直している会社では、自己防衛本能からミスの隠ぺいや、事故が起きやすくなるでしょう。瑕疵(かし)のある商品がそのまま引き渡されたりすると、顧客の信頼も失います。
私もそうでしたが、意識を変えさえすれば怒りのコントロールは可能です。成功のコツは、私は変わろうとしていると周囲に宣言すること。怒ったらごちそうするなどのペナルティを設けたり、客観的にフィードバックしてくれる人を決めたりするのもよいでしょう。
問題に気付いていて何も言わないのは、上辺だけのさみしい関係ですよ。組織が目標に向かっていくとき、ある程度の衝突は避けられません。それを力でねじふせるからパワハラになるのであって、きちんと向き合えば一体感を生み出す要因になります。部下が道を外れたら、きちんと戻してあげてください。今は未熟でも、いつか必ずあなたの右腕となってくれるはずです。
今さら聞けない補助金<全般>の基礎 NO2

補助金申請について
補助金申請にあたっての重要なポイントの一例(Q&A)をピックアップします。
Q:商品開発の実験で良い感触を得たので、本格的な商品化に向けて補助金を申請したいと思いますが、適切なのでしょうか?
A:〇
商品化の可能性が高い商品開発は、審査で高い評価を得られる傾向にあると思います。
Q:申請書で「お金が欲しい!」という主張をすれば良いのでしょうか?
A:×
審査されるのは事業計画自体で、その実現性等が評価されます。
単に、「お金が欲しい!」だけでは、評価は低いと思われます。 費用が「丼勘定」では認められないでしょう(実際の事業は、計画の±20%以内の経費で実施することが原則です)。
Q:事業予定期間が、1年を超えますが、大丈夫でしょうか?
A:△
多くの補助金では、事業期間が10ヶ月程度です。 事業予定期間に応じた補助金を選択する必要があります。
Q:既に実施している事業で補助金申請をしたいのですが、適切でしょうか?
A:×
審査後に採択された事業に補助されることが原則のため、既に開始している事業で申請しても採択される可能性は低いと思われます。
Q:申請書は、短期間で容易に作成できるものでしょうか?
A:△
電子申請の場合が多く、GビズIDの事前取得が必要であったり、また、業者に事前に見積をとる必要があったりと、準備に相当な時間がかかる場合が多いとお考えください。
Q:補助金に採択されれば、すぐに事業を開始してよいのでしょうか?
A:△
採択後、追加の資料を求められるなど、すぐに事業を開始できないケースがあります。
採択された後に事務局から求められる書類に不備があって、いつまでも事業を開始できない案件が散見されるようです。 補助金申請段階で、採択後のことも考えて書類を準備してください。
Q:募集要領を可能な限り丁寧に読み、要領に沿った申請書の作成を進めるのが良いのでしょうか?
A:〇
募集要領には、審査のポイントや申請書の書き方の流れが説明されています。要領に則って申請書を作成するのが、採択への一番の近道だと思います。
事業期間において注意するポイント
交付決定がされて、晴れて事業を開始できる状態になった際に、知っておくべき基礎的な知識があります。
■補助金制度で、少しでも疑問を感じたら、すぐに事務局に相談を!
「きっと、こうだろう!」と自己判断したり、「補助金がもらえなくなるのは怖いので、事務局に相談するのは、止めておこう!」というケースが、かなりあるようです。
迷わずに、すぐに事務局に相談してください!(正しい情報こそが、命です)
■事業の大半を他人任せにするのはNG
「全ての設計は外注さんがやってくれるから大丈夫!」「導入設備は業者任せだから!」というのは、NGです。部品や設備の仕様を正しく把握し、購入・導入後に要望仕様とおりで、その成果が十分にでていることを、自らしっかり検証する必要があります。
■実績報告を見据えて、伝票等は正しく用意・保管をしましょう!
事業が適性に行われていることを証明するには、事業に関係した装置の写真や会議の議事録がポイントになります。また、費用支払い等は、仕様書・注文書・請求書・領収書等の帳票類によって証明します。 どのような帳票が実績報告時に必要かを予め把握して事業を開始してください(※)。
※補助金事務局から、帳票の整理の仕方や電子データの取り扱いについて、詳細に指導していただけます。
すべてのことで写真を撮っておこう!
事業期間終了後の実績報告(精算時)の不安について
事業を実施し、所定期間内に実績報告を行います。実績報告にOKが出ないと補助金は支払われません。
「実績報告のチェックが厳しく、対処があまりにも大変で、本業どころじゃなかったよ!」
「計画事業を行ったものの、思うような成果が出そうにない・・・これで補助金が本当にもらえるのか不安だ。」
補助金申請を予定している方だけでなく、補助金採択事業者の方からも「実績報告が不安だ」との声を多く聞きます。
公募要領を正しく理解して申請を行い、事業期間中に、日々着実に帳票管理を行い、事業内容の記録(写真を含む)をしっかり残してあれば、実績報告書の作成は、それほど難しいことではありません。
また、狙った成果が十分に出なかった場合でも、真摯に事業に取り組まれていたのであれば、決して悲観する必要はないと思います。
何が出来て何が出来なかったのかを実績報告で明らかにすれば良く、課題がはっきりしたのであれば、補助事業に取り組んだ意味は大きかったと思います。
精算後(本格的な事業化に向けて)
補助金が支払われた後も、事業の進捗を所定年数、報告する義務があります。
また、補助金の執行が適切であったか、後日、国等の監査を受ける場合があります(違反行為等があると補助金の全部又は一部返還を求められる場合があります)。
今さら聞けない補助金<全般>の基礎 NO1

今さら聞けない補助金<全般>の基礎の基礎
補助金採択を目指す際に押さえておきたい補助金の基礎知識について解説します。
補助金、助成金(経営Q&A) 補助金・助成金
Question
コロナの影響もひと段落し、事業が回復しつつあるため、新たな事業に挑戦してみたいと思っています。
世間では補助金が大々的に報じられていますが、「補助金など自分たちには全く関係無い」と今まで目を向けてきませんでしたので、恥ずかしながら、補助金のことが全く分かりません。
そのような企業でも分かるよう、補助金について基礎からお教えいただけないでしょうか。
Answer
各種報道のとおり、既に多くの事業者が補助金を活用して新事業に取り組まれています。
このため、補助金に精通した方も多くいらっしゃいます。
その一方で、正しい理解に基づかない補助金申請も多いようです。正しく補助金を理解することにより、確実な補助金採択を目指されることを願うばかりです。
今回、補助金の基礎の基礎とも言える内容をご紹介しますので、補助金をお考えの際は、過去の情報に惑わされず、本コラムを活用していただけたらと思います。
はじめに
ここ数年、様々な補助金の募集があり、多くの事業者が補助金を活用しているかと思います。しかしながら、業況の悪化等により補助金を活用した新規事業や事業再構築に踏み込めなかった事業者も多いようです。それだけに、「補助金からも取り残された」と感じている経営者の方も、少なからずいらっしゃると思います。
今からでも遅くはありません。「補助金のことが全く分からない。」と恥ずかしがることはありません。
代表的な補助金(例えば、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等)に共通する基礎的な内容を説明させていただきます。
補助金には、様々なものが存在し、その1つ1つが大きく異なるルール(要綱)で実施されています。このため、補助金の共通するルールに加え、補助金ごとのルールを正しく理解して進められることを強くお勧めします。
補助金とは?
「補助金」とは、事業者が申請した事業計画に対して審査が行われ、採択された事業計画に基づいて消費された費用を、実績報告の後に支払う制度です。
つまり、申請すればすべての補助金が支払われるわけではなく、原則、採択された事業が適切に行われた後でなければ、実施事業の費用は支払われない(補助されない)という「審査制度」「精算払い方式」が採用されています。
補助金の流れ(一例)
①公募(公募要領の公開・告知・募集の開始)
該当の補助金の事務局から、公募要領(募集期間や申請条件等)が発表され、募集が開始されます。
②申請準備(申請書作成)
公募要領に則って、申請書の準備及び作成を行います。外部機関の確認・承認や電子申請のための登録が必要な場合も多いので、申請の準備は早めに開始してください。公募要領の公開前に過去の例に則って準備することは可能ですが、同じ補助金でも、募集回で条件等が変わることがありますので、ご注意ください。
補助金は、原則、事業経費のすべてを予め自ら準備する必要があります。そのため、融資等の資金調達も重要な準備です(補助率(例えば、事業経費の2/3)など、一部のみ補助対象とする場合にも注意が必要です。)。
③補助金申請
補助金申請を行います。電子申請が主流になっていますので、申請方法やデータ形式には、注意が必要です。
④採択通知
申請に対して審査が行われ、審査結果が発表されます。採択された場合には、事業の開始に向けて、次の手続き等についての指示がなされます。
⑤交付申請(補助金によっては、不要な場合もあり)
採択されただけでは、事業を開始できない補助金があります。採択後に事務局から指定された書類を提出することで、最終的な補助金額等が決定する補助金もあります。その場合は、交付決定書が交付されてから事業を開始します(この交付決定書に事業開始日や最終的な事業期間が定められている場合が多いようです)。
⑥補助事業実施
いよいよ、補助事業の開始です。採択された事業計画に則って、事業を開始します。補助金の対象となる事業期間は決して長くないため、速やかに事業に取りかかるのが肝要です。
途中、状況報告が求められたり、事務局による中間監査が入る場合があります。
⑦実績報告
補助金の支払いを受けるためには、定められた期間に事業の実績報告を提出する必要があり、実績報告に対しては、事務局のチェックが入ります。実績報告が認められるまで、補助金の支払いは行われません。
⑧精算払請求
実績報告にOKが出た後、事務局に補助金の請求を行います。
⑨補助金支払い
補助金が支払われます。
⑩事業化状況報告
補助金が支払われた後も、事業のその後の進捗を所定年数、報告する義務があります。