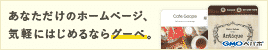インフォメーション
気候変動対策 意識に男女差
英国 フィナンシャルタイムズは、女性取締役の方が男性取締役より気候変動対策に積極的である可能性があることを発表した
今回は売上高が1460億円以上ある大企業の取締役700人にヒアリング調査した
短期的に業績に悪影響が出ても気候変動対策を進めることは大切と答えた人の割合は、男性4割、女性7割
欧米であるので、取締役になるのにほとんど男女差は無い
教育水準や報酬でも大きな違いは無いのである
なぜ考え方の違いが生じるのであろうか?
記事では「明確な答えは無い」と締めくくっている
私もなんとなく女性の方が、環境問題に関心が高いように感じる
それはごみの出し方にも現れている
またESGが大事だと答えた人の割合は、前回が64%であったが、今回は57%に下落した
またESGが業績を向上させると答えた人の割合は、前回が54%であったが、今回は45%にまで下落している
これは、企業に環境まで配慮する余裕がなくなってきた証左かもしれない
資金的に余裕があるので、ESGに取り組めるが、半年後、自分の会社がどうなっているかわからない人たちに、環境配慮を考えよと言っても、あまり効果はないであろう
これは人でも一緒。明日食べるものがないのに、気候変動対策をしながら、食べ物を探す人はまずいない。
プリントシール 四半世紀の人気継続 年200回のグループインタビューの成果
女性から支持率が高いスニーカーは「ニューバランス」らしい
「NB」はとてもかわいく、誰から見てもNBとわかる上に、色使い、デザインが絶妙なんだと
全くそんなこととは知らなかった
今度量販店に行って確認してこようと思う
イマドキ消費を動かすポイントは「かわいいか、かわいくないか」になっている
このかわいい世界を四半期以上続けているのが、プリントシール機である
代表的な略称として「プリクラ」があるが、これはセガの登録商標
今はプリ機、あるいは、プリと呼ぶらしい
どれだけデジタル化が進んでもリアルなコミュニケーションはすたれない
カラオケとプリはJKの定番であり続けている
同時にプリ機の運営会社のマーケティングもすさまじい努力
オムロン系は一機に全国に6000台配置し、年3回も新機能を更新している
JKを主な対象として、年200回を超えるグループインタビューを繰り返して、彼女らが、今何を欲しているのかを追い求めている
私も子供が小さかったころはよくプリクラで写真をとった
今でも当時の筆箱やカードの隅に張ったプリクラ写真はよい思い出である
色褪せてしまっているが、当時のおもかげはしっかりと残っている
話は戻るが、プリ機にとどまらず変化しない市場は存在しない
市場とは生き物で耳を澄ませば消費者が求めるものも見えてくる(はず)
ロシア産ガス
昨今ロシア産ガスの話題が出ない日がない
一体ロシア産ガスはどれくらいの産出量があるのか調べました
2021年ではロシア産ガス生産量は世界全体の17%を占め、米国に次いで第2位
ロシアは原油の生産量での世界3位となっており、外貨獲得の重要な資金源となっている
ロシア産ガスの最大の買い手は欧州
2021年には欧州連合が輸入する天然ガスの4割をロシア産ガスが占めた
年間1670億立方にもなるとのこと
ロシア産ガスについては、ドイツが使用全廃を目指すなど依存度を下げる方向で進んでいる
冬に向かい、どこまで欧州国民が頑張れるかにもかかっている
さてガス産出量で世界3位はイラン、4位は中国となっている
ガス産出量の半分は西側以外の国が算出しているのである
日本のエネルギーを考えるにあたっても覚えておいた方がよい事項と思う
洗濯できるシルク生地を長浜の産地組合が開発
昨日新技術で世界進出といった記事を書いたが、長浜で繊維の新技術が開発された
絹織物の産地、滋賀県長浜市の浜ちりめん工業協同組合はシルク生地を家庭用洗濯機で洗えるようにする新たな技術を開発した
有機化合物で生地を処理して分子レベルの結合を強めることで濡れた状態で摩擦によるスレやちじみ、色落ちが起きにくくなったとのこと
子供服やシーツ、枕カバーなどに絹織物の用途を拡げていく狙い
滋賀県東北部工業技術センターとの連携
YASA SILK
と名付け、同組合が生産加工を受託する
生地は地元産にこだわらず受けいれするとのこと
月間4000メートルの加工能力がある
小さい記事であったが、長浜の地場産業を大きくジャンプアップさせることができる技術にも思えるので記載した
もともとシルクの風合い、肌触りは別格のものがあり、その生地が、通常の繊維製品と同様に使えるようになるのなら、かなりの引き合いになるのではないかと推測する
私も、今から30年以上前には、浜ちりめん工業協同組合を毎月のように、仕事で訪れていた
その時からすでに斜陽化していたが、こういう記事が出ると大変うれしく思う
当時から、真面目な従業員さんが多く、懸命に働いておられたことを思い出しました
経済が成長する条件
日経新聞の連載記事に「日本経済が成長する条件」があって参考になりそうなので要約を記載します
明治維新から高度成長期までは、技術的に日本は遅れていたので、海外からの技術移転によって成長ができた
海外の技術を真似たり工夫したりすることで進歩が進んだ
海外技術の恩恵を受けることを「技術スピルオーバー」と呼ぶ
お手本があるおかげで飛躍的な成長ができた
日本市場に合わせる工夫をすれば成長できた
しかしながら1980年代に日本の技術が世界に追い付いてから急速に経済成長が鈍化した
技術スピルオーバーに頼る成長は期待できなくなった
お手本が無い状況でもチャレンジし独自の新技術を開発しなければ更なる成長は難しくなるということである
現在日本のGDPは米国の半分まで低下している
IT技術でも大きく水をあけられているのが実情
高度成長期は製造業が日本を引っ張ったが、現在は、サービス業の重要性が高まっており、製造業がGDPに占める割合が低下
しているので、模倣して大量生産するという方法で成長するのは難しくなっている
ではサービス業で模倣して追い付けるかというとそれも難しい
「ネットワーク外部性」と言って、サービス業では使う人が多ければ多いほど有用になるという原理があり、今更、Googleや
アマゾンなどを模倣しても、大きく市場シェアをとることは難しいという
ではどうするか??
新しいアイデアで独自技術を開発し、それを海外に普及させれば、ネットワーク外部性により高い収益が得られる時代だという
⇒それはわかっていはいるのですが。。。。。