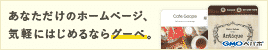インフォメーション
コストコ会費頼み脱却 効率運営で店舗の稼ぐ力向上
会員制スーパーのコストコHLDが新たな成長軌道に入りました
売上原価率9割という低価格戦略による集客力
低コスト運営
が売上高の向上でより効果を発揮
商品調達力の強化も相まってさらに向上しています
米国コストコHLDの話なのですが、売上高が前年同時期比較で+14%と堅調です。
私がびっくりしたのは、同社の財務数値です。
売上原価率9割
要は商品を売っても1割しか儲からない 通常のスーパーであれば売上原価は6割から7割くらいかと推定
売上原価というのは、あくまで売上から仕入れをひいた分ですから、残りの1割から人件費や運営費を出しているのです
(売上からは、会費収入分を除いてはいますけど・・・)
取扱商品点数 3800点
通常のスーパーの約5%ととのこと
商品種大量販売で在庫を回転させるのがコストコのやり方なのです
コストコは、その代わりに、年間4840円の会費を徴収しています
私も払っていますが、高いとは思いません
コストコはレジャー感覚ですよね
帰りに食べるピザやジュースがとてもおいしいですよね
今や営業収入の方が、会費収入を上回っているとのことなので、もしかしたら来年以降は会費が安くなるかもです(←希望的観測です)
そしたらますます来店者が増えるのでもっと駐車場を大きくしてほしいですね。
滋賀県の湖北湖東地域に来ないかな??
EV車が50万円を切る???
中国の自動車メーカーが50万円を切る格安EV車を発売して、農村部を中心に好調に売り上げを伸ばしています。
創意工夫して製造しているようです
1.回生ブレーキを使わない(減速時に車輪に回転力を電力に変換するブレーキシステム)
2.冷却システムを空冷化
3.この車ように新しい部品を特注せず、既存品だけで製造
の3つだそうです。
すべてが、EV車にとっては、常識破りだそうです
デメリットも当然あります
1.航続距離が170キロ程度 →近場か農園程度しか行かないのであればこれで十分
2.耐用年数8年、12万キロ →通常は20年間、20万キロとのことですが、新車で10万キロ乗ることも少ないですよね
3.やや壊れやすい →設計が簡単なので、壊れたモジュールごと交換で対応できる
今回の記事をみてびっくりしたのですが、リチウムイオン電池は16万円程度なんですね。しかし50万円の3分の1はリチウムイオン電池とも言えます。
その他車体、電装品全部入れて50万円切るのであれば、ゴルフ場のカートより安いですよね
大きさは、日本の軽自動車より50センチ短い程度、幅は2センチ大きいとのことです。
こんなに安いEV車が出てきたら、日本メーカーは戦々恐々だと思います。
牛乳を飲もう 21日に岸田総理が言及
年末年始に牛乳をいつもより多くの飲み、料理に乳製品を活用してほ欲しい
と21日の記者会見で岸田総理が言及するに至った、牛乳過剰問題
年末年始は給食がなく、また休業する量販店も増えるので1年で一番売上が落ち込む時期
→牛さんには年末年始関係ないし
10月末の試算では、年末に5000トンの牛乳が廃棄になる予想もあります
民間では、ローソンや雪印パーラーで特販をする予定とのこと
業界が牛乳廃棄に神経質になるのは、売上減少もさることながら、2006年の苦い経験があるため
当時生乳を廃棄し、乳用牛も減らした、生産者のやる気もなくなり畜産業者さんも廃業も増えた
ところが一転バター不足を招き、やっと回復してきたと思ったところに、コロナに重なり、またまた売上減少
実は、私は、小さいころはヤギの乳を飲んで育ちました。家では牛など大きな動物はかっていませんでしたが鶏はいました。
なので、今でもジュースより牛乳が好きなんです。
牛乳はとても安いですね。1リットル200円いけば高い部類に入ります。
濃い牛乳はほんとにおいしいと美容と健康にもいいので、夏場などは、麦茶代わりになるほどです。
ということで、値段が安くなるかどうかはともかくとして、年末年始は一生懸命に牛乳を飲むことにします。
牛乳を飲むと、胃に粘膜ができてよりお酒が飲めるらしいですし。。。
日本株より米国株
日本人が日本株を買わなくなったそうです。
政府の「貯蓄から投資」への政策がありましたが、お金の向かう先は、もっぱら海外株です。
巨額の利益を稼ぐアメリカハイテク企業と比較すると、日本企業は色あせて見えます。
かつての日本株を支えた日銀や公的資金の買いも今後は細りいずれ、売りに回らざるを得なくなります。
また米国がインフレを抑えるために金利をあげざるを得ない事情もあり、どうしてもドル高円安となり、資金はドルに向かいます。
ということで、当面日本株は弱く、乱高下を繰り返すと思います。
ちなみに米国の消費者物価指数は、前年同月比較+6.8%と39年ぶりの高水準にあります。日本は1%以下です。
岸田政権が掲げる「新しい資本主義」をそのまま導入し、金融課税を強化すれば、富裕層や起業家が海外に逃げてしまい、日本には、普通の人だけが残るということになりかねません。
21年1月から11月の公募投信の資金流入ですが、米国株へは7兆3千億円に対し、なんと日本株は4千億円マイナスとなっているのです。
海外市場が伸びているということに加え、自動翻訳ツールが普及し、英語が読めなくても投資できるようになったので、米国株への投資ハードルが一機に低くなってきたことも要因です。
日本市場の特殊要因とすれば、
日銀が年間6兆円を買い進めるという政策があるのですが、すでに日銀が日本株の筆頭株主になってしまっており、批判も多く、今年度は未だ3千円億円弱しか買えていません。
また年金機構(GPIF)も日本株の運用資産は全体の25%までという目標まで日本株を買い進めており、これ以上日本株を買う方向ではありません。
ということで、日本株を持つこと自体がリスクとなってきています。投資は自己判断で!!!
2021年宅建試験 相続 昼ドラの様相
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
- Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
- Aが2分の1、Gが2分の1
- Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
回答
被相続人Dの配偶者であるAは、法定相続人です(民法890条)。
また、Dの子であるFとGも法定相続人です(同法887条1項)。問題文に「Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。」とあります。しかし、親権というのは、子の利益のために、監護・教育を行い、子の財産を管理する権限という意味です。相続とは関係がありません。Dが親権を有しているかどうか、とは無関係に、FとGは、Dの子として、いずれも同様に扱います。
以上より、Dの法定相続人は、B・F・Gの3人です。これだけで、正解は肢1に決まります。
※Cは、法定相続人ではありません。Cは、Aの子です。被相続人Dとの血縁はなく、また、養子縁組に関する情報もありません。したがって、Cは、Dの子ではなく、法定相続人にはなりません。
※「離婚した元配偶者(本問のE)が相続する。」というヒッカケ・パターンもあります。しかし、相続開始時に配偶者でなければ、法定相続人にはなりません。
法定相続分の決定
確認のため、そして、今後の本試験対策として、法定相続分についても押さえておきましょう。
被相続人の配偶者と子(直系卑属)が法定相続人となる場合、法定相続分は、配偶者が1/2、子が全体で1/2です(民法900条1号)。ここで、Aの法定相続分は1/2と決まります。
子全体の法定相続分をFとGで人数割りします(同条4号本文)。F、Gの法定相続分は、それぞれ1/4です。
法定相続分まで検討しても、正解が肢1であることが確認できます