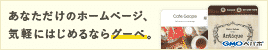インフォメーション
ROE、日本企業の考え方 続く「グローバル」との苦闘 リターンオブエクイティ
本日は大企業向けの話
東証が上場企業のROE リターンオブエクイティを引き上げる方針とのこと
ROEの基本的な考え方は「利益率×回転率×レバレッジ」で表される
煎じ詰めると採算の良い事業(高利益率)を、少ない資産(高回転率)と、抑えた資本(高レバレッジ)で営むほどROEは上がる
要は、低採算な仕事を無くし、採算の良い仕事に注力しようということ
いろいろな資料を見ると日本企業のROEは欧米のROEにはるかに見劣りしている
株主にとってはROEは高いほどいいが、従業員にとってそれがいいとは限らない
短期的な利益を追う欧米企業と、長期的な利益を追う日本企業の差が出ているとも思う
企業の「自己資本利益率(ROE)」を改めて考えるべき時だ。
東京証券取引所は、市場評価の低さを示すPBR(株価純資産倍率)が1倍未満の企業に改善を促し始めた。
一般にPBRと正の相関関係があるとされるROEの向上が「1倍割れ」対策の王道だ。
歴史をふり返れば、いかに効率的に株主資本を使っているかを示すROEは、行き過ぎた株主利益主義の象徴として批判される一方、競争力を磨くための道具として信奉もされてきた。
ROE賛否の軌跡は、日本企業がグローバル市場といかに向き合ってきたかを刻む履歴書でもある。
日本ではROEがいつから、どんなかたちで使われるようになったのか。
過去の新聞記事にヒントを求めた。記事データベースの日経テレコンで「ROE」という言葉を含む記事を検索可能な限り遡ると、最も古いのは1981年5月21日付日経産業新聞22面の「財務の履歴書」という解説記事だった。
ホチキスなどで知られるマックスが、米国の提携先から学んだ財務理論を設備投資に生かすという内容だ。
82年6月28日付同紙は、電子部品のTDKが中期経営計画で「自己資本利益率20%維持を目指す」と報じている。TDK元会長の澤部肇氏は後年、日経「私の履歴書」のなかで、小兵企業が目立つために米国の理論をいち早く取り入れようとした旨をつづっている。
80年代の日本企業のROEはおおむね8%台だった。
バブル期に8%前後に下がり、90年半ば以降は5%未満で低迷。
その後はネットバブルの崩壊やリーマン・ショックなどを乗り越えて緩やかに回復し、近年は7〜8%台が定着したように見える。
日本企業がROE改善に本腰を入れるようになったきっかけが、アベノミクス(安倍晋三元首相の経済政策)の一環、2015年からのコーポレートガバナンス(企業統治)改革であることは論をまたない。
ROEは事業の採算を示す「売上高純利益率」、資産活用の効率を測る「総資産回転率」、そして資本に対する債務のバランスをみる「財務レバレッジ」の3要素に分けて考える。
ROEが8.6%だった1985年度は、利益率1.4%、回転率1.4回、レバレッジ4.5倍。
直近でROEが同水準の8.7%だった2016年度は、利益率4.4%、回転率0.8回、レバレッジ2.5倍だ。
大きく異なるのは利益率とレバレッジ。大きな債務を抱えながら低採算の事業をしていた日本企業が、ほぼ30年かけて財務体質を改善し、採算の良い事業にシフトしてきた様子がうかがえる。
利益率を高めるのりしろは人件費や研究開発費だった。その削減がデフレや賃下げの圧力として作用したことは容易に推察できよう。
3要素に2つの伸びしろ
金融などを除く日米欧の代表企業のROE3要素(利益率、回転率、レバレッジ)の推移を比較すると、日本企業には2つの伸びしろがあることに気づく。
ひとつはレバレッジで、米国や欧州が約3倍で安定しているのに対して、日本企業はほぼ一貫して低下してきた。
財務の安定は経営の危機耐久力を高めるが、行き過ぎた低レバレッジ追求は事業リスクを株主に負わせすぎている状態と表裏だ。
過去20年でゆっくりと高まってはいるが、なお米欧勢との差は大きい。
そうかといって人件費や研究開発費をさらに削るのは経営の持続可能性を高める観点からも禁じ手だ。
長期で有望な分野への先行投資が不可欠だ。