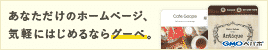インフォメーション
解禁間近の「給与デジタル払い」 八方塞がりの現在地
4月から従来の銀行振り込みに加えて、各種PAYへの振込が可能になる。
しかし未だ1社も実施する予定はない
その理由は、事業者破綻時の資金保全の仕組み
一人当たり100万円の資金保全をしなければならないとのこと
仮に10万人の利用者があればなんど1000億円もの資金枠を用意する必要があるとのこと
そんなに巨額な資金は、銀行くらいしか用意できないのでは??と思ってしまいます
ということで、私たちが頂く給料は、当分は銀行振り込みが続くと思われます
2023年4月に労働基準法の施行規則等の一部改正省令が施行され、PayPayなどのスマホ決済サービスで給与の全額または一部を受け取れるようになる
「まだ検討すら始めていない。解禁日は迫っているが、検討したくてもまだ手を付けようがない段階だと言った方が正確かもしれない」。こう胸の内を明かすのは、ある家電メーカーの財務担当者だ。彼の頭を悩ませている存在が、25年ぶりに会社員・団体職員らが給与を受け取る新しい手段として加わる「給与デジタル払い」だ。
給与デジタル払いは、「PayPay」「d払い」「au PAY」といったスマホ決済サービスを提供する資金移動業者の口座を通じて、従業員に賃金を支払うというもの。労働基準法の施行規則等の一部改正省令が施行される2023年4月に「解禁」される。
口座残高の上限額は100万円という制約があるものの、指定日に定額が残高に入金されるわけで、スマホ決済を日常的に使っている人にとっては逐次チャージする手間が減る意味で朗報だ。
一方、制度を導入・運用する企業にとっても、新制度はメリットがある。給与を銀行振り込みする場合、1件当たり振込手数料として300円程度かかっている。もし従業員が全額をスマホ決済で受け取ることを選択すれば、そのコスト負担が軽減される。スマホ決済の事業者の多くが、自社サービス内での送金手数料を無料に設定しているからだ。
にもかかわらず、冒頭の担当者が明かしたように、解禁と同時に一足飛びで普及する機運が一向に高まっていない。それはなぜか。
厚生労働省はスマホ決済を提供する資金移動業者に対して、7つもの追加要件をクリアすることを求めており、そのためのガイドライン案をまとめて準備を進めている各社に公表している。23年1月時点で資金移動業者は85社あるが、要件をクリアできなければ給与デジタル払いを扱えないわけだ。「しかも、ガイドラインの中にクリアすることが極めて難しい『超難問』がある。破綻時の資金保全の仕組みだ」(中堅スマホ決済サービス事業者の担当者)という。
具体的には、万が一破綻した場合に備えて、6営業日以内に確実に残高を利用者に弁済する体制をスマホ決済の事業者は整えなければならない。問題は、その際に一時的に生じる資金需要に対応するために、各社へ求めている資金量の膨大さだ。
かみ砕くと、給与デジタル払いを希望する労働者の数だけ、1人100万円ずつ用意しないと、審査を通過できないという内容なのだ。残高がたとえ1円でも100万円ずつ用意しなければならないわけで、仮に10万人なら1000億円、100万人なら1兆円、1000万人なら10兆円という計算になる。
銀行振込にないスマホ決済ならではの利便性を従業員が感じる環境づくりが求められるのは間違いない。例えば、振込手数料がかからない点を生かし、月に数回に分けて支払うといったスキームの導入。日本瓦斯(ニチガス)は、社員の交通費などの経費精算に限り、申請後すぐに送金する仕組みを18年から提供し、社員の間で好評を得ている。スマホ決済「pring」の付加サービスを活用したもので、残高を手数料無料で銀行口座に出金したり、セブン銀行のATMで現金として引き出したりできるようにした。毎週給与を分割で得られるといった利便性があれば、労使協定も前向きに進めやすくなるかもしれない。
銀行口座から完全に離脱する暮らしが難しい点も、今後議論を進めていく必要がありそうだ。例えば公共料金。スマホ決済でも、カメラを使って請求書を読み取ると支払えるが、銀行の自動引き落としのように定期的に簡潔に支払うことが現状できない。クレジットカードも決済代金を引き落とすには銀行口座を使うのが一般的だ。一つずつ課題を解決していかなければ、給与デジタル払いを国民の社会インフラとして根付かせることは難しいだろう。