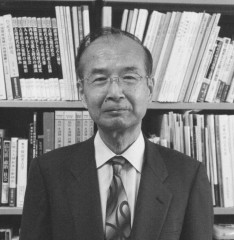◆お知らせ
第1回 講演会のお知らせ
2024年6月1日(土)
演題:須恵器から見た古代東国
講師:酒井 清治氏 駒澤大学名誉教授
酒井 清治氏略歴
1949年 岐阜県生まれ
学歴
1969年 駒澤大学歴史学科入学
1974年 駒澤大学歴史学科卒業
1976年 駒澤大学大学院人文科学研究科修士課程入学
1978年 駒澤大学大学院人文科学研究科修士課程修了
職歴
1980年 財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団
1985年 埼玉県立歴史資料館
1990年 埼玉県立博物館
1991年 国立歴史民俗博物館
1997年 駒澤大学文学部歴史学科助教授
2003年 駒澤大学文学部歴史学科教授
2020年 駒澤大学退職
学位
1999年 駒澤大学博士(日本史学)
著書
2002年『古代関東の須恵器と瓦』同成社
2003年『日本全国古墳学入門』(共著)学生社
2013年『土器から見た古墳時代の日韓交流』同成社
2018年『古瓦の考古学』(共著)ニューサイエンス社
群馬県では、榛名山噴火関連遺跡に関するガイド人材養成を目的とした
講習会を開催します
今回は、ガイドを目指す方以外も受講できます。
主催:群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員会
(事務局:群馬県文化振興課)
会場:渋川市北橘行政センター2F 活用室
(渋川市北橘町真壁2372番地1)
受講料:無料
第一回 令和6年2月18日(日)
13:00ー16:45(受付開始 12:00)
講座1.「古墳時代の榛名山噴火」
講師:右島 和夫氏(群馬県立歴史博物館 特別館長)
講座2.「金井東裏遺跡」
講師:杉山 秀宏氏(群馬県埋蔵文化財調査事業団 資料2課長)
講座3.「金井下新田遺跡」
講師:小島 敦子氏(群馬県埋蔵文化財調査事業団 資料1課長)
第二回 令和6年3月10日(日)
13:00ー16:15(受付開始12:00)
講座4.「黒井峯遺跡」
講師:石井 克己氏(元渋川市教育委員会文化財保護課長)
講座5.「榛名山噴火関連遺跡と人馬共生」
講師:深澤 敦仁氏(群馬県立歴史博物館 学芸係長)
問い合わせ先
群馬県 地域創生部 文化振興課 歴史文化遺産室 世界・歴史遺産係
(Tel:027-226-2525) ( E-mail):bunshinka@pref.gunma.lg.jp
2023年11月25日(土)
テーマ 古墳時代の東西の雄-吉備と毛野ー
第一部
演題:古墳時代の吉備
講師:亀田 修一氏
岡山理科大学 名誉教授
亀田 修一氏略歴
1953年 福岡県生まれ
1976年 九州大学文学部 史学科考古学専攻卒
1980年 九州大学大学院 文学研究科史学専攻修士課程修了
1980年 岡山理科大へ
1986年 岡山理科大学講師
1991年 岡山理科大学助教授
2001年 岡山理科大学教授
現在は 岡山理科大学特任教授・名誉教授
著書
■古墳時代研究の現状と課題(上・下)
土生田純之・亀田修一ほか36名共著 同成社
■吉備の古代寺院 共著 吉備人出版
■日韓古代瓦の研究 単著 吉川弘文館
■考古資料大観第3巻 弥生・古墳時代 土器Ⅲ 編著 小学館
講演・口頭発表等は多数に上る。
特に、考古学的資料から見た、
古代朝鮮半島と日本との交流に関しては、第一人者としての定評がある。
主たる研究テーマ:古代吉備、古代山城、古代寺院、渡来人、古代日韓関係等
第二部
演題:古墳時代の毛野
講師:右島 和夫氏
群馬県立歴史博物館 特別館長
(群馬県立博物館 特別館長執務室にて)
右島 和夫氏略歴
1968年 群馬大学入学
1972年 群馬大学卒業
1974年 関西大学大学院文学研究科修士課程修了
1977年 群馬県教育委員会文化財保護課
その後、群馬県立歴史博物館 学芸課長
群馬県埋蔵文化財調査団 調査研究部長
1995年 「東国古墳時代の研究」で関西大学文学博士
2016年 群馬県立歴史博物館 館長
現在は、同館特別館長
主要著書:
■「東国古墳時代の研究」学生社 1944年
■「群馬の古墳物語 上下」上毛新聞社出版メディア局
■「馬の考古学」雄山閣(共編著)
第三部 両講師による対談
2023年10月7日(土)
演題:幻の道を探る
ー古代東山道駅路の調査ー
講師:小宮 俊久氏
太田市教育委員会 文化財課
小宮氏の略歴
1959年 群馬県前橋市生まれ
1984年 中央大学文学部史学科国史学専攻卒業
1988年 新田町教育委員会 勤務(文化財担当)
2005年 太田市教育委員会 文化財課(市町村合併による)
上野国新田郡家跡、東山道駅路その他の発掘調査を担当
2020年 太田市教育委員会 教育部参事兼文化財課長 定年退職
2020年 太田市教育委員会 文化財課史跡整備係主任専門員
研究活動
専門分野 日本考古学(古代)
研究テーマ 古代官衙・古代交通
主要論文等
「古代新田郡の一様相」群馬文化第261号 2000年
「上野国の古代交通網と官衙」『坂東の古代官衙と交通』埼玉県考古学会 2002年
「郡家正倉の配置復元試論」東国史論第21号 群馬考古学研究会 2007年
「上野国の東山道駅路の現状と課題」『白門考古学論叢Ⅲ』中央考古会 2013年
「上野国の郡衙の構造と変遷」『東国の考古学』群馬考古学研究会 2013年
「郡衙」『古代官衙』ニューサイエンス社 2014年
「関東、東北における長舎と官衙」
ー『第17回古代官衙・集落研究報告第14冊』奈良文化財研究所 2014年ー
「上野国新田郡家の景観」『日本古代の道路と景観』八木書店 2017年
「古代新田郡の蝦夷政策における役割」群馬文化第331号 2017年
「郡家正倉の基礎地業-坂東における「皿状壺地業」の検討-」
ー『芙蓉峰の考古学Ⅱ』2020年ー
「群馬の東山道駅路とこれが解き明かした地域の歴史」
ー『上野三碑の時代 7・8世紀の都と東国』群馬県立歴史博物館 2022年ー