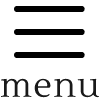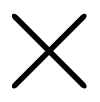一言法話
86.根を大事に
今日は春分の日、春のお彼岸の中日です。今年は3月18日から24日までの1週間が春のお彼岸になります。古来よりお彼岸はいつも以上にご先祖様の供養に努めていただく期間とされています。
ご先祖様を供養することは1本の木に水を与え、大切に育てることに例えられます。
今を生きる私達を1本の木に咲く花とするならば、ご先祖様はその木を地中で支えている根であると言えます。1本の木を何気なく眺めたならば、そこに咲く花にばかり目がいきますが、その花が咲くことができるのは、土の中にしっかりと根が張っていてくれるからです。根は土の中にあり普段目にすることはできないので忘れがちですが、だからといって、その根の部分をないがしろにし、水を与えることを怠ったならば、根は水を吸い上げることができず、その木は育たず、美しい花が咲くこともないでしょう。
お彼岸期間中は私という命を与えていただき、私という存在の根となって下さっているご先祖様に感謝申し上げ、いつも以上にご先祖様に思いを寄せ、大事にしていただきたいのです。
「自分の番」という相田みつをさんの詩があります。
うまれかわり 死にかわり
永遠の 過去のいのちを 受けついで
いま自分の番を 生きている
それがあなたのいのちです
それがわたしのいのちです
ご先祖様が脈々と受け継いでこられた命のバトンを受け取り、私たちはこの世に誕生することができました。もちろん、生きることは楽しい事ばかりではありません。しかし様々なことを経験し、感じ、そのことを噛み締めることができるのは命をいただいたからこそです。その有り難さに感謝申し上げ、自分を支えて下さるご先祖様の供養に努めましょう。そのことが、結果として自分というかけがえのない花を美しく咲かせることにも繋がるのです。
85.お陰さまの命
今日は西暦で言いますと、2023年3月11日。東日本大震災から12年が経ちました。東日本大震災は2011年3月11日の出来事ですから、東日本大震災当日に亡くなられた方は、2011年3月11日を合わせ13回目の祥月命日を迎えたことになり、今年が13回忌ということになります。
たくさんの尊い命が東日本大震災により奪われました。
人生には坂がある 上り坂 下り坂 そして突然やってくるまさかの坂
という言葉がありますが、東日本大震災で命を奪われた方は、まさしくまさかの坂から転げ落ちてしまうという不運に見舞われてしまったわけです。
しかし、このことは決して他人事ではありません。
当たり前という言葉がありますが、日常を何気なく淡々と生きていると、命あることが、当たり前ということになってしまいます。しかし、たまたま命を落とすような悪縁(病気・事故・災害)に遭わずに済み、生き長らえるだけの毎日の食事を取ることができるから、私達は当たり前のように生きていられるわけです。
ある方が「当たり前」の反対の言葉は「お陰さま」だと言いました。
私達は今現在、まさしく「お陰さま」で悪縁に遭うことなく生きています。さまざまな「お陰」によって生かされているといってもいいでしょう。しかし、このことを忘れ、私達は今ある命を「当たり前」として生きています。
3月11日というこの日に「お陰」により今現在を当たり前のように生きていられることを噛み締め、深く感謝し、東日本大震災で命を奪われた方のご冥福を改めてお祈りします。
84.ロバと親子 その2
前回「ロバと親子」というドイツのお話を紹介しました。
このお話から私達は何を学ぶことができるでしょう。
人はどのような行動をとったとしても、悲しいかな、誰かには必ず批判されるものである、ということがその1つとして挙げられます。
どうしてそうなってしまうのかといえば、人はそれぞれの都合、価値観といった色眼鏡によって、自分に都合がいいように物事を判断しがちだからです。
「ロバと親子」に出てくる老人たちは、息子だけがロバに乗っている状況を見て、年寄りを大事にしない息子だと批判します。当の親子2人にはそんな気持ちはこれっぽっちもないのですが、老人たちは自分に立場の近い親父さんの方を哀れに思い、息子の方を親を大切にしないとんでもない奴だとして見てしまうわけです。
子どもを抱いた女の人にしてみると、子どもの方にどうしても感情移入してしまいます。子どもだけがロバに乗れず、父親だけロバに乗っている様子を見ると、子どもがかわいそうで、いたたまれないということになってしまうわけです。
つまりは、人は自分の都合で物事を見て判断しがちなので、どんな行動を取ったとしても、それを批判する人は当然いるということになります。ですから周りの意見にばかり合わせ、右往左往してしまうのは愚かなことだとこのお話は諭しています。だからといって、どうしたって批判されるのだから自分勝手に何をしてもいいんだということではありません。そうではなくて、自分に信を持ち行動することの大事さをこの話はあらわしている思うのです。
お釈迦さまは最晩年にこのようなお言葉を弟子たちに残されました。
自らを灯火とし 自らを拠り所としなさい
法を灯火とし 法を拠り所にしなさい 他をたよりとしてはならない
そしてこうもおっしゃいました。
教えのかなめは心を修めることです
ここで言う法とは仏法(仏の教え)です。お釈迦さまは自分を拠り所としていきなさい、そのためには仏法を拠り所としていかなくてはいきませんよと、諭されたのです。自分というものを拠り所とするには、自分にきちんと向き合い、心を修めていかなくてはいけません。信のないご都合主義で物事を判断していては、自分を拠り所とすることなどできないからです。
83.ロバと親子 その1
「ロバと親子」という話を聞いたことがありますか。
ある親子が町の市場でロバを売るため、ロバを引いて田舎道を歩いていました。
その様子を見ていた女の子たちが、道端で親子に聞こえるような大きな声でこう言いました。
「なんて馬鹿な親子なの。どっちか1人がロバに乗ればいいのにさあ」
それを聞いた親父さんはもっともだと思い、あわてて息子をロバに乗せました。
しばらく行くと、老人たちが焚き火をしているところに通りかかりました。
老人の1人がこう言います。
「今どきの若者は年寄りを大切にしない。年とった親父さんが疲れた様子で歩いているのに、あの子はロバに乗ったまま平気でいるなんてとんでもないことだ」
親父さんは、それもそうだ、息子がそんな風に思われては大変、と息子をロバから下ろし、今度は自分がロバに乗りました。
しばらく行くと、子どもを抱いた3人の女たちに会いました。1人の女がこう言います。
「全く恥ずかしいことだよ。子どもがあんなに疲れた様子で歩いているのに、自分は知らん顔でロバに乗ってさ。可哀想な息子だねー」
困った親父さんは、すぐに自分の鞍の前に息子を乗せました。
しばらく行くと、数人の若者に出くわしました。すると1人の若者が興奮気味にこう言いました。
「あんたたちどうかしてるぜ。ロバが可哀想じゃないか。あんたたちには慈悲の心ってものがないのかい」
その通りだと思い、2人はロバから下りました。そして親父さんは言いました。
「こうなったら、2人でロバを担いでいくしかないな」
ロバの前足と後足をそれぞれ綱で縛って、その足を道端の丈夫そうな太い木の枝に通し、2人で担いで歩いて行きました。
町の人達はもがき苦しむロバを必死に担ぐ親子を見て、大笑いしながら「何やってんだい。ロバを歩かせて運べばいいのに」と言いました。
「ロバと親子」はドイツのお話ですが、これに似た話は世界中にあるそうです。このお話は一体どんなことを私達に語りかける話なのでしょうか。
話が長くなりましたので、この続きは次回お話します。
82.何事も前向きに
前回お話した通り、1年の始まりとも言うべき立春(2月4日)に当院にて星まつりを行いました。お参りいただいた皆様方にもそれぞれの当たり星(九曜星)に命穀を供養していただき、厄難消除、福寿増長を祈念いたしました。
コロナも今現在、落ち着いてきている状況であり、やっとコロナ禍前の日常を取り戻しつつあります。
この1年、少しでもいい年でありますようにというのが、誰しもの願いでありましょうが、そのためには星祭りといったようなお寺の法要に参拝していただき、仏さまに謙虚に祈りを捧げることが大事だと考えますが、同時にもう一つ大切なことがあります。
パナソニックの創業者、かの有名な松下幸之助さんは、採用試験で「君は運がいいか」と聞くことが多かったといいます。なぜ、そんな質問をしたのでしょうか。
「自分は運が強いんだと確信していれば、どんなことも受け入れて立ち向かう勇気と力が生まれてくる。人から見ると決して運がいいとは思えない状態であっても、自分は運がいいと思える前向きな考えができる人がふさわしい」と松下さんは考えていたということです。
コップに入った水を何かの拍子にこぼしてしまい、水の量が半分くらいになってしまったとします。そんな時、こぼしちゃったから、水が半分になっちゃった、ついてないなぁーと捉えるのか。こぼしたのに、まだ半分も水は残っている、ラッキーと捉えるのか。受け取り方はそれぞれですが、何事においても前向きに考えることができる人はどんなことが起きてもそこに光を見出すことができ、結果として運も味方してくれるはずです。
仏さまへ感謝の祈りを捧げ、謙虚さを持ち、何事も前向きに捉えていけるならば、きっと良い1年を送ることができます。