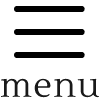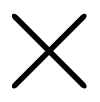一言法話
116.とらわれのない心
北海道もやっと春らしい日が続くようになりました。新しい年度を迎え、気持ちも新たにすがすがしい日々を送っていきましょう。
私の好きな話を紹介させていただきます。
ある2人の修行僧が諸国を行脚していたところ、前日の大雨で水かさの増した川に差し掛かりました。
そこで川を渡ることが出来ずに困っている様子の若い女性を見つけました。川には橋が架かっておらず、向こう岸に行くには川に入り、歩いて渡るしかありません。
片方の修行僧が、「どうされたのですか」と声をかけたところ、「この川を渡って今日中に行かなければならない所があるのですが、この辺りには橋もなく渡れなくて困っているのです」悲しげに女性は答えました。
「わかりました。じゃあ、私が背負ってあげますよ。一緒に渡りましょう」その修行僧は女性をおぶって向こう岸へ渡りました。
向こう岸で女性を下ろすと「それでは先を急ぎますので」そう言い残し2人の修行僧はその場を去って行きました。
修行僧達は、ややしばらく黙って歩いていたのですが、女性を背負わなかった方の修行僧がこう言い放ちました。「おい、お前は修行者として失格だ。女人に話しかけるどころか、体に触れるとは何事か」
すると、女性を背負った方の修行僧は涼しい顔でこう答えました。
「なんだ、お前はまだそのことを背負っているのか。わしは川を渡ったところでとっくに下ろしてきたぞ」
この話は仏教で大事にする「とらわれるな」ということをわかりやすく表しています。
2人は修行の身ですから、非難した方の修行僧が言うように女性と話しをしてはいけない、まして体に触れるなどもってのほか、という主張はもっともなことと言えます。しかし、そうであったとしても、困った人がいたら自身の慈悲心に従って手を差し伸べる行為は間違いではないはずです。
そして、ここで言えることは非難した方の修行僧はもう一人の修行僧が女性に関わりをもったということにこだわり続け、悶々としていたわけですから、結果的に修行の妨げになるような思いを自分自身で作ってしまったということです。
とらわれの心を持ち続けると、修行者にとっては修行の妨げになりますし、とらわれの悶々とした思いは自分自身をも苦しめてしまいます。
新しい年度が始まりました。とらわれのないすがすがしい心を目指していきましょう。
115.命の責任
今年は今日3月17日から3月23日までが春のお彼岸となります。今年は3月20日が春分の日で、この日がお彼岸の中日となりますが、3月21日がお大師さまの御入定の日ですので、日光院では毎年3月21日午後1時より春彼岸法要を行っています。
お彼岸はいつも以上にご先祖様のご供養に務めていただく大切な期間ですが、それと同時に自分自身の仏道修行期間でもあります。
仏道修行などというとちょっと大げさですが、自分自身の日ごろの生き方を見つめ、どのように日々を生きていくべきなのかということを考えてみる、そんなお彼岸にしていきたいものです。
十善戒という十からなる戒めがあります。戒とは仏教徒が守るべき生活の指針ともいえる生き方をあらわすものです。
その一つに「不殺生戒」があります。生き物を殺してはならないとうい戒めです。無駄な殺生などすべきではないとの思いは誰しもあろうかと思います。しかし、よくよく考えてみますと、生き物を殺さずに毎日を生きることなど、できることではありません。外を散歩したならば、蟻などの小さな虫を踏み潰すこともあるでしょう。そして何より、私達は様々な命を毎日いただいています。自らの命を保つことは、様々な命を犠牲としてはじめて成り立つものだといえるわけです。
ある小学生がこんな詩を書いています。
僕はカニを食べました
僕はカニの一生を食べました
命をいただくということはそれだけの責任を伴うことだということをこの詩は教えてくれます。
不殺生戒は無駄な殺生などすべきではないとの戒めであると同時に、自らの命は様々な命の犠牲の上になりたち、生かされていることへの気づきを与えてくれるものです。そのことを深くかみしめ、責任と感謝の日々をおくりたいものです。
114.どのような香りを
今年も早いもので2ヶ月が過ぎました。今月の中旬には南から次々と桜の開花宣言が出されていくことでしょう。まだまだ寒さ厳しい地域に住む北海道民にとっては春の桜の季節を待ちわびる今日この頃です。
お大師さまは知り合いのお母さまが亡くなってから、三七日の時に、あるご文をおくっています。その中に私たちの身と心を花に例えたこんな言葉があります。
「身は華とともに落つれども 心は香りとともに飛ぶ」
私たちの身体は花と同じようにいつかは落ちてしまう(亡くなってしまう)けれども、心は花の香りのように舞い上がり、浄土に昇っていく。
亡くなった人の香り(その人の生き様やその人が残した足跡)はこの世に残る人達の心に残るものでもあります。
この世に生まれてきた以上、誰もがいつかはこの世から旅立たなくてはいけません。
お大師さまの先ほどの言葉は、その旅立ちの時、この世にどのような香りを残せるのかということを私たちに問いかけているのかもしれません。
113.懺悔文
昨年から今年にかけ、政治家の資金パーティーを巡る裏金疑惑、大物芸能人のスキャンダル等々が巷を賑わせております。
皆からあがめたてまつられるような立場になると、善悪の判断基準が麻痺されていくのでしょうか。
仏教では因果応報といって、悪い行いをすれば、悪い報いを受け、善い行いをすれば、善い報いが返ってくると説きます。頂点に上り詰めたような人でも、その人が取る行為によっては、簡単に坂道を転げ落ちてしまうように、その地位を失うこともあるわけです。
これらのことはもちろん全ての人にあてはまることですから、決して他人事で終わらせてしまってはいけません。
真言宗ではお経の前に「懺悔(さんげ)文」という短いご文をお唱えします。「懺悔」はキリスト教では「ざんげ」と読みますが、仏教では「さんげ」です。
我昔所造諸悪業(がしゃくしょぞうしょあくごう)
皆由無始貪瞋癡(かいゆうむしとんじんち)
従身語意之所生(じゅうしんごいししょしょう)
一切我今皆懺悔(いっさいがこんかいさんげ)
「私は遥か昔から、貪りの欲や自分勝手な怒りによって、正しく物事を見定めることが出来ずに、相手が傷つくような言葉を発したり、誤った生き方を積み重ねてきたことでしょう。私は今、そのことを悔い改めます」
ついつい自分本位な生き方をしてしまう我々ですから、懺悔しなくてはいけないようなことを意識せずともしてしまっているはずです。そんな自らの行いを振り返り、正していくためのご文が懺悔文です。
112.福は内
2月3日は節分、2月4日は立春です。日光院では毎年2月4日の立春に星祭り法要を行っております。また、法要後には当たりくじの入った豆まきを行います。
豆まきのかけ声と言えば「鬼は外 福は内」が一般的ですが、日光院では「福は内 福は内」のかけ声で行います。なぜ「鬼は外」は言わないのかということについてお話します。
そもそも鬼とは何でしょう。本当の鬼を見たことのある人はまずいないと思いますが、金棒を持ち、角のある赤鬼や青鬼の姿をイメージすることは誰でもできるでしょう。「悪い物」「恐ろしい物」の代名詞として使われることの多い「鬼」ですが、仏教における鬼とは自分勝手な欲望、つまり煩悩のことを表します。
自分勝手な欲望は、そのままでは菩提(悟り)を目指す修行の妨げとなるものですが、仏教では「煩悩即菩提」という概念があり、欲望は悟りへ向かう大切な要素となります。苦しみを逃れ、本当の幸せを得たいという欲は誰にでもあるものですし、仏教がそういった欲を否定することはないのです。ただし、誰かを押しのけてまでといったような自分勝手なものであれば、それは結果的に自らを苦しめるものとなってしまうと考えます。
真言宗では大欲を目指そうと説きます。自分さえよければといった小さな欲を、周りと共に幸せになっていこうとする大きな欲に変えることができれば、揺るぎない本当の幸せを手に入れることができるでしょう。
ですから、日光院では「鬼は外」と鬼(煩悩)を追い払うのではなく、鬼とも呼ぶべき自らの煩悩を大欲にまで広げ、皆で共に福を呼び寄せられるようにという意味を込め「福は内 福は内」との掛け声で豆まきを行っています。