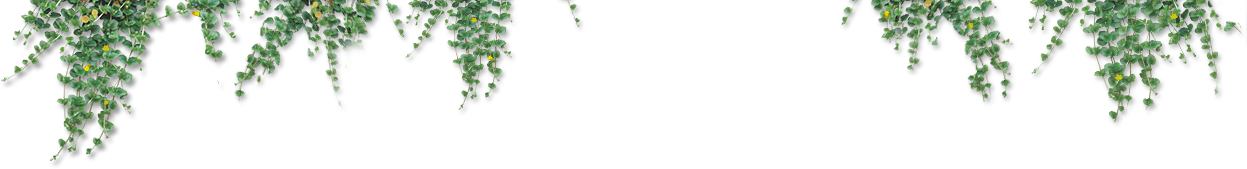親子万歳奮闘記 way to health
1.運命の出会い
僕がマクロヒ゛オティックと出会ったのは、1997年10月、僕が小学6年生の時だ。
あれから随分の月日がたった訳だ。
そもそもの始まりは、母の友人から手渡された1冊の本がきっかけだったらしい。
読み終えると、突然母は父に「ボストンへ行こう」ときりだしたという。
その頃、僕はまだ入院中で、すっかりからだはボロボロ、気分は絶望的にあれていた。
「もうオレは一生退院できないんじゃないか」 毎日、そんな事を考えていた。
入院も長引いていたある日、週末外泊の許可がでたと母がしらせてくれた。
おもいがけなかったので思わず「オレ、生きて病院からでられるの?」と聞いていた。
後から聞いた話だが、母はその僕の一言で「どーにかしなくちゃ」と真剣に思い始めたらしい。
そんな時に手渡されたのが久司道夫先生の「マクロヒ゛オティック健康法」だった。
その本を読んだ母は、先生がボストンにお住まいだと知り、
僕を連れて会いに行こうと考えたのだ。
父も同意して、さっそく先生のスケジュールを調べてもらったら
「先生は今、日本にいらしています」という。
ボストン旅行は僕の知らないところで盛り上がって、なくなった。
2日後、母は先生に会うために東京にでかけた。
講演会の前に少しだけ時間をとって、話を聞いてくれたのだ。
そして、「お母さん、息子さんは必ずなおりますよ。食事です!」
この力強い言葉と出会うこととなるのだ。
次の日、まだ興奮の冷めない母は、「すごい先生に会った」とか
「今日から病院のご飯はたべないで・・・」と言い出した。
僕の運命のマクロビオティックが始まった。
2. 久司先生と会う
母が久司先生と会ってから2週間後、
僕と母はマクロビオティックをもっと知るために、
伊豆の「クシマクロビオティック合宿セミナー」に出かけた。
僕にとっては6泊7日の楽しい旅行気分だった。
しかし、入院の名残りでかなり顔色が悪かったらしく、
駅で電車を待っていても、
近くのおばさんが「あなたちょっと顔色が悪いわよ」と
ベンチを譲ってくれるほどだった。
足も今ほど強くなく、母がヨレヨレの状態の僕を、
ひきずるようにしてたどり着いたのを覚えている。
セミナーのカンファレンスルームでは、
おばあさんに「あら、僕来たのね」と声をかけられた。
「誰だろう?」と当時は思ったが、山本祥園先生だった。
次にパトリシオさんが来たというので、僕は玄関に迎えに行った。
母から笑顔の素敵なスペイン人と聞いていたので会いたかった。
「How are you?」と声をかけた。一瞬、驚いていたが笑ってくれた。
僕はすっかりパトリシオが大好きになっていた。
みんなの温かい雰囲気に、だんだん元気になれそうな気がしてきた。
夕食前、早めに食堂に行くと、
背の高いおじいさんが誰かと話している後ろ姿があった。
僕にはその人が久司先生だとすぐにわかった。
引きつけられるように
僕は「クシせんせーい」と馴れ馴れしく肩をポンとたたいて声をかけた。
「やあ、来たね!」と優しい、ちょっとおどけた声が返ってきた。
・・・が隣で母は僕のこの大胆な行動に凍りついていた。
ついに、僕は久司先生と出会った。
先生の回りの空気は柔らかい優しさに包まれていた。
その雰囲気はすぐ僕に「がんばろう」と決意させた。
3.魅惑の玄米
初めてのマクロビオティックセミナーは、
伊豆の富士山の見える小さな旅荘で貸し切りだった。
参加者は50人位だったのでアットホームな雰囲気だった。
もちろん僕は最年少だった。
朝は、パトリシオさん指導のメリディアン体操から始まる。
朝食後はマクロの基本の調理実習だ。
お料理の講義は山本祥園先生、実習は大久保地和子先生が指導してくれる。
6人ぐらいのグループで玄米ご飯、きんぴら、切干大根、小豆南瓜などを作った。
グループリーダーはパトリシオさんで、
左手の不自由な僕に包丁の使い方を丁寧に教えてくれた。
なんだか料理が楽しくなってきた。
いよいよ昼食という頃、
久司先生も現れてどこかのテーブルに着いて一緒に食事をしてくれた。
誰かが「おいしい」という声をあげた。
僕も母もそのおいしさに顔を見合わせた。
初めて圧力鍋で炊いたそのご飯は、
底がうっすら焦げているのに上はもっちり糸をひいていた。
僕達はあまりに柔らかいそのご飯は失敗だと思っていた。
すると祥園先生が「あら、いいご飯が炊けたね」と声をかけてくれた。
「嘘だろう?」と思って食べたご飯は甘くて本当においしかった。
ミレットのランチのご飯はこのときの玄米ご飯のイメージが基本になっている。
切干大根もきんぴらもお醤油だけの味付けなのに、甘くておいしかった。
今まで母が作ってくれたものとは全然違う衝撃の味だ。
僕は「ママは料理がヘタなんだ」と確信した。
数日後、
久司先生が「お母さんのお料理、おいしいでしょ」と声をかけてくれた。
僕は、はっきり「まずいです!」と答えていた。
・・・が、このひと言が母の料理魂に火をつけることとなる。
4.本当の優しいお母さん
当時、小学6年生の僕には、久司先生の講義の内容は難しかったので、
すぐに疲れてしまい、部屋で寝ていることが多かった。
セミナーも中盤になった頃、先生は参加者全員の食養指導をしてくれた。
みんなの前に出て、それぞれの食生活や健康状態を報告して、
改善のための指導をしてもらうのだ。
いよいよ僕の番が近づいた時、
母は、僕にほんとうの病名を教えていなかったので躊躇したらしい。
先生が「僕も一緒に」ということで、僕もその場に呼ばれた。
母の極限の緊張などしるよしもない。
僕は母の口から伝えられた病名さえも耳に入ってなかった。
とにかく僕にとっては、「お肉をやめたら治る病気」でしかなかった。
セミナー最後の夕食はパーティだった。
いつもの講義の部屋は、大きな木が組み込まれて囲炉裏が作られていたり、
たくさんの料理がところ狭しと並べられて、まったく違う雰囲気になっていた。
僕は、大好きな肉や魚が使っていないパーティの料理なんてはっきり言って、
期待していなかった。
囲炉裏の鉄鍋には鯉こく、揚げそばのあんかけ、
玄米団子、セイタンの焼き鳥風、揚げ物、パトリシオさんのケーキなど盛りだくさんだった。
どの料理もおいしくて、もちろん母は全種類食べるとはりきっていた。
母が僕に揚げ物を持ってきてくれたとき、
大久保先生が「あら、あなたは油物をとめられているでしょ」と声をかけてきた。
「目先のかわいそうで食べちゃいけないものをあげるのと、我慢をさせて元気にするのと、どっちがほんとうにやさしいお母さんかしら?」
母にとって目から鱗だったのだろう。
母は「本当にやさしいお母さんになる宣言」をした。
5.お弁当の始まり
初めてのマクロビオティックセミナーを体験した僕と母は、
今までとは違う新しい世界に飛び込もうとしている自分達にわくわくしていた。
さっそく父に、セミナーで実習した玄米やきんぴらを作って、
家族全員で玄米食を始めようということになった。
父は喜んで賛成してくれた。
「本当に優しいお母さん宣言」をした母は、
まず今までの調味料をすべて処分して、
マクロビオティック対応のものに代えた。
野菜も宅配の有機栽培の野菜を取り寄せた。
そして一日のほとんどを僕のための料理に費やした。
もちろん学校にはお弁当を持っていくことにした。
最初は粗食そのもののお弁当だった。
クラスの数人は必ず僕のお弁当をのぞきにきた。
ある日、母が寝坊して玄米ご飯ときんぴらだけの時があった。
それを当時僕が好きだった女の子に見られ、
ちょっと驚いた顔をされてしまい恥ずかしかった。
母にその事を話したら、
給食のメニューに合わせておかずを作ってくれるようになった。
ハンバーグは高きびで、とんかつは車麩で、
チキンは高野豆腐を使ってと工夫してくれた。
ミレットのランチメニューはこのお弁当が原点になっている。
とにかくマクロのお料理を、僕に嫌われないように母が必死だったという。
給食にゼリーがつくと寒天でゼリーを作ってくれた。
冬はお弁当が冷たいというと、お昼にできたてを届けてくれた。
夏もいたまないように、お昼に届けてくれた。
しかし、僕の中では「みんなと同じ給食を食べたい!」という気持ちは
どんどん膨らんでいった。
母の努力には感謝はしていたが、
大変な世界に飛び込んでしまった実感がストレスとなって僕に押し寄せた。
6.アトランタ旅行
僕たち家族は父の仕事の関係で、
僕が1才半の時から小学2年までの約6年間
アメリカのアトランタで過ごしていた。
その頃はまだ母も食事の大切さなどには気がついていなかったので、
早くアメリカの食生活になじもうとしていた。
日本にいた時はごはん好きの僕だったが、
現地のナーサリーに通うようになると
強制的に母にパンのランチをもたされてしまった。
週末は庭でバーベキュー、夕食にピザが登場することも珍しくなかった。
日本人学校に通うようになって、ごはんのお弁当を作ってくれたが、
スクールバスの僕の降車地点はなんとマクドナルドの前だった。
そのまま、他の日本人の友達とマックのプレイルームで遊ぶのが日課になっていた。
そんな楽しくも恐ろしい食生活を送っていたアメリカ生活だったが、
僕にとってはそれまでの人生のほとんどを過ごしていた訳で
なつかしい第二のふるさとでもあったのだ。
僕が入退院を繰り返していた頃、退院して体調が良くなるとよく家族旅行をした。
たいていは福島や栃木など近くが多かった。
しかし、マクロと出会う直前の話だが、
母に「どこか行きたい所ある?」と聞かれて、
急に楽しかった小さい頃を思い出し「アトランタに行きたい!」と答えていた。
セミナーから数日後、僕達家族は予定通りアトランタへ向かった。
玄米、梅醤番、調味料を持参して、以前家族ぐるみでおつきあいのあった人の家にとまった。
なつかしい友達も遊びに来てくれたりして、本当に楽しかった。
僕も両親もすっかり病気のことなど忘れて、
このまま時間が戻ればいいと願わずにはいられなかった。
だが、次の入院予定日が迫っていた。
7.久司先生の電話
マクロビオティックの講演会やセミナーで、
いろいろな方の治病体験を聞いてはいたが、
僕達家族はまだ、西洋医学から離れることをためらっていた。
最初は、「病院の治療の副作用を軽くするためのマクロビオティック」
という程度にしかとらえていなかったので、
思わぬ展開にとまどっていたという言う方が当たっているかもしれない。
アトランタ旅行から帰ると、
伊豆のセミナーでお世話になった久司先生のスタッフの女の人から手紙が届いていた。
実は、久司先生にはもうすぐ入院予定があることを
話していなかったのだが、大久保先生には話していた。
すると、大久保先生が久司先生にお話ししてくださったということで、
「久司先生がとても心配していらっしゃるので、連絡をしてほしい」という内容だった。
母はさっそく久司先生のオフィスに電話をした。
その女の人は、
久司先生がアメリカで東洋のシュバイツァーと呼ばれている事、
マクロビオティックで病気を克服することが可能なこと、
アメリカのクシハウスで療養することも考えてみたらどうか?
などいろいろな話をしてくれたということだった。
最後に「マクロと西洋医学を両立させる事は難しい」と言っていたという。
また久司先生に関する資料もFAXしてくれた。
そして、久司先生が「宿泊先のホテルに電話するように」とおっしゃっているとのことだった。
母の心は揺れ始めていた。
いや、どんどんマクロビオティックに近づいていった。
数日後の真夜中、受話器にしがみつくように、
久司先生と話す母の後ろ姿があった。
翌朝、決意を固めた母に
「玄米を食べるだけで病気が治るものか!」という父の大きな声が響いた。
8.究極の選択
入院予定が近づく中、母は大きな選択を迫られていたのだと思う。
このまま入退院を続けて治療するとして、
医師に全てをまかせてしまうだけで良かったはずだ。
たとえ、病院まで片道2時間の道のりだとしても、
たいした問題ではなかったはずだ。
しかし、実際に病院の治療はまちがいなく僕の体に負担をかけていた。
治療の度に、僕の白血球は減り、もとに戻りにくくなっていた。
これからもこの治療を続けることに不安を感じているのは確かだ。
では、マクロビオティックを選んだとして、
母は、僕のためにつきっきりで、
僕の体調にあわせた食養の料理をつくらなければならないということだ。
それは、母が僕の命を預るのと同じぐらいの責任があることを意味する。
いったい、どちらを選んだ場合に、
僕の明るい未来が待っているのだろうか?
・・・究極の選択だった。
母が「入院をやめてマクロビオティックに賭けたい」と強く思い始めた頃、
父は治療をやめるなんてとんでもない」と反対していた。
母は思い余って、大久保先生に相談した。
「おふたりとも、お子さんが良くなるようにと、信じている道が違うだけで、
お子さんを愛しているという思いは同じなのよ。
ご主人の気持ちもわかるわ」という意外な答えだったという。
マクロビオティックを信じない父を、
母はもう少しで憎んでしまうところだったのだ。
母が父を説得できないまま、
父はアトランタの出張にでかけてしまった。
「あと1回だけ、治療をうけてくれ。それで俺の気持ちがすむから・・・」
ついに、入院の日がきてしまった。
僕の体に治療の準備のための点滴が入ってしまった。
9.最後の退院
母は、点滴の入ってしまった僕を見て、
とうとうがまんができなくなってしまった。
出張でアトランタにいる父に毎日電話をして説得したという。
・・・ついに、父がおれた。
そして、主治医への退院の申し込み。
今なら母の緊張がわかるが・・・
「ユウ君、今回はネ、すごく元気だから入院しなくてもいいって。あと3日で退院だよ」
突然、看護婦さんに言われた僕は
「いったいどーなってるんだ?」と信じられなかった。
が、とにかく嬉しくて点滴をつけたまま飛び跳ねて喜んでいた。
明日からあの辛い化学療法の治療が始まると覚悟していた日だった。
僕は知り合いの看護婦さん、検査技師さん、花屋さん、
会う人たちみんなに「退院です!退院です!」と言って回った。
嬉しかった。嬉しかった。
でも、本当にそれから以後
今日に至るまで病院に足を踏み入れる事さえないなんて夢にも思っていなかった。
(母) 「あと1年、うまくいって5年、生きられたとしても、このままじゃ意味がないんです。」
(医師)「普通の親なら、今退院なんて考えませんよ」
「お母さんは今、冷静な判断ができない状態のようですね」
・・・・母と医師との間でこんなやりとりがあったとは想像もしていなかった。
そんな中、僕はひとりうかれていたのだ。
その日の帰り、母は病院の駐車場からしばらく動けなかったという。
そして車の中から、
最初にマクロヒ゛オティックの本を教えてくれた秋田の母の友人に電話をした。
「これはマイナスからのスタートなんだよ。すっごい大変なことだけどがんばれ」
ついに僕達は西洋医学と決別したのだ。
1997年12月8日。
忘れられない日となった。
10.そして始まった
今回はたった1週間の入院だったのに、
家に帰った僕は、すごく懐かしい気分になった。
「お帰りー」と母は言ってくれた。
僕にとっては自由になれたことが嬉しかった。
だが、母にとっては緊張の始まりだったに違いない。
僕達は、もう一度、久司先生の食事を初めからやり直すことにした。
もちろん玄米菜食で、肉、魚、卵、乳製品、砂糖は一切許されない食生活が基本だ。
僕の症状に対する食箋は・・・
大根おろしと人参おろしに梅干1個、醤油少々を半カップ。
これを1週間は毎日、
その後2週間は隔日、
次の2ヶ月は3日に1回、その後は時々・・。
それから僕の症状に合わせたスープは、
干し大根3:干ししいたけ2:炒り玄米2を各3倍の水で沸騰してから20分煮たもので、
これを4ヶ月毎日1〜2杯飲むのだ。
そのほか注意として、
寝る3時間前には食事を終えるということだ。
豆類は少量にする。
海草は毎日とってもよく、
飲み物は三年番茶、茎茶など人参ジュースは週2回だ。
テーブルに用意するように言われたのは
12:1の割合の胡麻塩、梅干、鉄火味噌、ゆかり、のりなどだ。
母は大きな紙に書いて、キッチンに貼っていた、いや今でも貼ってある。
最初はこれさえ守りさえすれば元気になれると信じていたので、
辛い大根おろしや、味のないスープも我慢しようとしていた。
しかし、段々日がたつにつれ、
変わりばえのしない体調、執拗な母の態度、
おまけに今まで好きだったものがひとつも食卓にのらない食生活に
我慢ができなくなってしまっていた。
そのイライラはたった1週間でやってきた。
僕は「入院してもいいから何でも食べたい!」と泣き叫んでいた。
母は怖い顔をして、そしてもの凄い早さで荷物をまとめ始めた。
「そんなに食べたいのなら病院へ行こう!早く車に乗って!」と言って、
僕は外に連れ出された。
驚いた僕は、ただごとではすまない母の迫力に
「ママ、やっぱりマクロやる・・・」と小さな声で言っていた。
母は「がんばろうよ」と泣いていた。
「ママ、ごめんなさい」
でもまだ僕は「母に怒られるのは嫌だ」という思いだけで
心からマクロをやりたいと思っていた訳ではなかった。
母も父が出張中に退院の宣言をしてしまった手前、
かなり気負っていたので、僕にはとても息苦しい存在になっていた。
母との心のすれ違いはこの後もしばらく続くことになる。
11.楽しい小学校生活
僕は、勉強は嫌いだったが、学校は大好きだった。
みんなに会えるのがとても楽しみだったからだ。
実は、僕は小4の秋に、若年性の脳梗塞で左手足に麻痺がでて、
以来、少し不自由になってしまった。
そんな時も、クラスのみんなはやさしく、かいがいしく僕の面倒をみてくれた。
そして、小5の時、この病気になった時も、
治療のため髪の毛が抜けて登校したのだが、特にいじめにあった記憶はない。
母は心配して、僕に帽子をかぶせたのだが、
「実はぼくはハゲなんです!」とみんなの前でぬいでしまった。
先生もやさしくしてくれて、みんなも普通に僕に接してくれた。
頭痛に襲われて、保健室に行く時も、
かばんをもってくれる友達や送ってくれる友達がいた。
初めて一時退院で学校に寄った時も、
クラス全員が「カガヤン、がんばれ」と廊下に迎えにきてくれた。
うれしくて、うれしくて元気になれる気がした。
マクロをはじめて、お弁当になった時も、
毎日、「カガヤン、お弁当見せて」とのぞかれたけど、
そのことでいじめられたことはない。
学校は近かったが、まだ、体力がなかったので、
母が毎日車で送り迎えしてくれていた。
「おばちゃーん、乗せてってー」
いつも僕の面倒をみてくれる友達が二人、
にぎやかに乗り込んでくるのもうれしかった。
当時、一番楽しいと思える時間だった。
本当に感謝している。
・・・しかし、運命のいらずらというのか、
この二人は中3と高1の時に
突然亡くなってしまった。・・・・もういないのだ。
12.父が久司先生と会う
退院してから、2ヶ月ほど経った頃、小学校の卒業も間近になっていた。
2月には卒業旅行でディズニーランドにでかけることになった。
まだまだ寒い日が多く、学校でも頭痛に悩まされることが多かった。
そこで、母が一緒についてきた。
その日は天気がよかったので、頭痛は襲ってこなかった。
僕は久しぶりに楽しい一日をすごすことができた。
この日のことで、僕はかなり自信がついた。
「ママ、今日僕、元気だよね」と母に確認するのが習慣になっていた。
そして、僕は無事、小学校の卒業式にもでることができた。
その3日後、僕と母は2回目になる、久司先生の中伊豆の宿泊セミナーに出かけた。
前回、初めて参加した時は、母に引きずられるようにして行ったものだが、
今回は、自分でも不思議なくらいに、足取りも軽く、つらくはなかった。
何よりも楽しみだったのは調理実習で、ぼくははりきっていた。
この時もやっぱり、祥園先生と大久保先生が指導してくれた。
セミナー3日目は、3月24日。
実は僕の12歳の誕生日だった。
夕食の時、思いがけず、参加者全員で、
「happy birthday」の歌を歌ってくれた。
僕は最高に幸せを感じた。
昨年の11歳の誕生日は病院のベッドで、
母がひとりで歌ってくれたのを思い出していた。
「なんて、マクロはいいことばかりなんだ。」と思わずにはいられなかった。
そして、4日目の夜、
カンファレンスルームで久司先生の講義を聞いていた時、
突然、父が現れた。
母は父にも、是非久司先生に会って、
マクロについての理解を深めて欲しいと、誘っていたのだ。
仕事の都合で来られないのかと思っていたので、
僕はすごくうれしかった。
翌日の朝は、また、皆の前で健康カウンセリングだ。
久司先生がまた聞いた。
「お母さんのご飯おいしいでしょ?」僕ははっきりと答えた。
「はい。お母さんのご飯が一番おいしいです!」
その頃には、僕の好きな食べ物は「大根」になっていた。
帰りがけ、母に先生が声をかけた。
「ご主人は素晴らしいひとですね。」
・・・母は意味がよく理解できないように「そ、そうですか?」と答えていた。
先生のこの一言がきっかけで、母は父の良い所を探し始めた。・・・らしい。
13.久司先生との縁
セミナーも終わりに近づいてきた頃、先生の話の中で
親友が秋田にいらっしゃるという話がでてきた。
僕の両親は秋田出身なので「えっ?」と思って聞いていた。
先生の親友は秋田のあるデパートの社長で・・・・・・と話始めた時
「先生、その方は私の同級生のお父さんです!」
・・・なんと母が思わず声をかけていたのだ。
声を掛けた母も驚いていたが、周りのみんなも驚いていた。
先生は和歌山生まれということは良く知られているが、
中学、高校時代は秋田で過ごされていたのだそうだ。
その時以来の親友がその人らしい。
大学進学で、先生は東大、その人は別の大学へと
それぞれの道を選んだが、
交流は続いているとのことだった。
そして、もっと驚いたことに、
先生と僕の両親は同じ中学校だったということがわかったのだ。
つまり、僕の両親は先生のずっと後輩に当たる訳だ。
もちろん僕たち家族は急に先生が身近に感じるようになった。
その講義が終わってから、先生が近づいてきて、
「君のお父さんとお母さんは、千秋公園という
素晴らしい公園があるところで育ったんだよ。
君は行った事があるかい?」といって僕を抱きしめてくれた。
僕は以前秋田に遊びに行った時に、千秋公園を散歩して、
お気に入りの場所でもあったので、すぐに「ハイ」と答えていた。
セミナーから帰ってきて、母は興奮して、
秋田の母の親友に電話をかけていた。
最初にマクロの本を渡してくれた人だ。
すると、もうひとつ驚いたことに、
当時、先生のお母様が秋田のカトリック系の高校で
教師をしていたということなのだが、
その母の親友のお母さんはそこの生徒だったということだ。
そして、ある日、お母様の代わりに
若い久司先生が教壇にたったことがあったということも覚えていた。
いろいろなつながりがみえてきて、僕たちは鳥肌が立つような思いだった。
母は、自分が先生の中学の後輩であることがかなりの自慢らしい。
ちょっとうらやましい気もするが・・・。でも自慢になることなのか?
もうひとつおまけは、母はそのカトリック系の学校の幼稚部に通っていたということだ。
これも縁になるかな・・・
14.久司先生からのプレゼント
1998年3月24日、中伊豆でのクシセミナー3日目、僕は12歳になった。
思いがけない参加者全員のバースデーソングに、僕は、はしゃいでいた。
そして、なんとプレゼントが用意されていたのだ。
それは、久司先生からのメッセージ入りの色紙だった。
「One Peaceful World
お誕生日をお祝いして かぎりない夢を求めて
世界中で 大きな仕事を 遊んでくださるようにー!」
と書いてあった。
これは、僕の宝物になった。
いや、家宝になった。
この時の僕には、メッセージの意味なんてどうでもよくて、
とにかく先生が僕のために書いてくれた、ということだけで最高にうれしかった。
「遊ぶ」という意味はそんなに重要なこととは思えるはずもなく、
「遊んでいいんだ」ぐらいにしか思っていなかったので、それも、うれしかった。
先生はセミナーの最後にいつも参加者に尋ねていた。
「みなさん、人間はなぜ生まれてきたのだと思いますか?」
みんな、難しいことを答えていた。
先生の答えはいつも「遊ぶためです」。
先生の意外な答えに、みんな一瞬シーンとなったのが印象的だった。
簡単すぎて、「なーんだ」と思う反面、
「どういうことなんだろう?」と気になる言葉だった。
母に聞くと、「病気なんてしないで、楽しく生きようってことよ」と教えてくれた。
この意味の深さは後からジワジワ気づくものらしい。
実は、もうひとつ大きなプレゼントがあった。
廊下で先生と会った時、「君はもう大丈夫だ。ちゃんとマクロの食事をつづけるんだよ」と声をかけてくれたのだ。
退院してマクロビオティックの食事をはじめてから3ヶ月くらいたっていた。
15.左手
久司先生に「大丈夫宣言」をされた僕は有頂天になっていた。
母が、先生に「手と足のリハビリをした方がいいですか?」と聞いた時、
「いや、しなくても大丈夫でしょう。ちゃんと食事で治りますよ」とおっしゃっていた。
僕たちは、この言葉を大きな勘違いをして聞いていたらしい。
僕たちは自然に治るものと思い込んでしまっていたのだ。
だが、先生は決して「なまけてもいいですよ」とはおっしゃらなかったはずなのだ。
僕は、時々おそってくる頭痛に怯えることこそなかったものの、
まだまだ頭痛に悩まされることが多かった。
そのことに気をとられて、手や足の不自由さなど
大して気にはしていなかったのかもしれない。
足の方は、段々歩けるようになってくるのが楽しかった。
だから、学校も、行く時は母の車で送ってもらっても、
帰りは調子の良い時は、ゆっくり歩いて帰ったり、
自分なりの努力はしていたのだと思う。
走れるようになった時には、母は手をたたいて喜んでくれたものだ。
だが、問題は手だった。
左手だったので、使わなくてもすむことが多く、
もしかしたら、僕は「自由に動かせるようになりたい」と
願うこともしなかったような気がする。
母が時々、「左手使って!」と注意してくれていたが、
僕はそれさえもうるさく感じていた。
後に、いろいろな先生との出会いがあって、
リハビリに励むチャンスはあったが、
結局のところ、僕のなまけぐせが災いしてか完治には至っていない。
そう言えば、先生は父に「奥さん、最近やさしくなったでしょ!」と聞いていた。
父は「・・・・・」と首をかしげていたが、
言われてみると、あんなに怒りん坊だった母が、最近やさしくなった気がする・・・・。
やっぱり、肉食をしなくなったからなのか?
16.不安と不満
「何もかも夢だったらいいのに、
病気になったことも、からだが不自由になったことも・・・」
僕は、はじかれるようにつぶやいていた・・・・・。
退院してからずっと「母の一生懸命さ」に僕もついていこうと夢中ですごしてきた。
が、時々限界を感じるようになっていた。
母は前向きで一生懸命だった。
食事のこともそうだが、マクロビオティックのことを理解しようと、努力していた。
マクロの人たちの集まりにも連れて行ってくれたり、
それはそれで、楽しかったし感謝もしていた。
だが、毎日のように襲ってくる頭痛、入浴をするたびに起こるめまい。
手につかない勉強、学校、テストのこと。
そして、食事のこと。
以前のように自由にならないからだの事などで、
実は僕の中では不安と不満が充満していた。
その上、母のただならぬ「一生懸命さ」は
僕には逃れられない恐怖のようなものも感じさせていた。
その時の僕には、母にグチをこぼすスキさえ与えられていないように思えたのだ。
母には僕の不安が見えていないような気がしていた。
僕は、だんだん嘘をつくようになっていた。
友人の家に遊びに行くと言って、近くのコンビニやスーパーで買い食いをした。
口の端にクリームをつけて帰って、嘘がばれたこともあった。
級友にも迷惑をかけて、母は担任の先生に呼び出されたりもした。
僕はすっかり心のバランスがとれなくなっていた。
本当に僕はこの苦しみからのがれられないのか?
ある日、僕はいつものように友人の家に遊びに行くと言ってでかけた。
行き先はコンビニだ。
サンドイッチを買って、歩きながら食べていた。
「祐輔!」
父が僕の後をつけていたのだ。
しまった。
僕は父に食べかけのサンドイッチをなげつけて、必死に走って逃げた・・・。
17.外食
相変わらず、母は毎日、手を抜かずに朝から晩まで僕のためにキッチンに立っていた。
僕には母が、マクロのお料理をとても楽しんでいるように見えた。
お休みの天気のよい日には、「外食しよう!」といって、
お弁当を作ってドライブにでかけた。
祖父母は、僕が入院中に、秋田から水戸へ引越してきていたので、
いつも賑やかにみんなでお弁当を広げた。
最初は近くの公園だったが、時には車で1時間ほどの公園まででかけた。
僕はこんな「外食」が結構気に入っていた。
それから、レストランでもないのに、家のテーブルには、メニュー表があった。2種類のコースがあった。
「スーパーミラクルライス・パワフルスープ
・スクランブルベジ・ベジローフ・ヘルシーサラダ・オリジナルデザート」
もうひとつは
「パワフル玄米ご飯・おっかさん風味噌汁・まんぷく野菜煮
・ツブツブ野菜の力こぶ風・シアワセ混ぜ野菜・きまぐれデザート」という具合だ。
何のことはないきんぴらごぼうや切干大根のことなのに、
母がネーミングするとこんな風になっていた。
いかにも素食と言った感じで以前のような華やかな食卓というわけではなかったが、
なぜか楽しかった。
地味なおかずなので、だんだん母は食器にこだわって、
盛り付けに工夫をしていたようだ。
そして、良く噛むようにと、一口ごとに箸をおいていたので、
箸置きも集めだしていた。
ミレットの箸置きがたくさんあるのはその時のものがほとんどだ。
出かける時には、玄米のおにぎりと三年番茶の小さ水筒を持ち歩くのが定番だったのだが、
しばらくして後に、知り合いのうどん屋さんに、本当の外食にも行くようになった。
この時は、かつおだしや砂糖を避けるために、
母が昆布としいたけと醤油だけでたれを作って水筒に持っていった。
そして、テーブルの下でたれを差し替えて食べた。すごいスリルだった。
18.お肉が食べたい?
「ねえ、ママ。僕は一生お肉が食べられないの?」
すると、近くに座っていた男の人が声をかけてきた。
「大丈夫だ、ユウスケ。そのうちお肉なんて嫌いになって、食べたいなんて思わなくなるから」
1998年の大久保先生のお宅で開かれた新年会でのことだ。
退院して1ヶ月ぐらいの頃だ。
大久保先生や先生のお教室の人たちが用意してくれたマクロのお料理がテーブルいっぱい並んでいた。ビュフェスタイルで、好きなお料理を取って食べることができた。
どれも、普段母が作ってくれる料理よりも、きれいで、おいしかった。
でも、僕にはある期待があった。
マクロのセミナーはともかく、パーティ料理なんだから、
お肉くらいはあるんじゃないかなと・・・。
やっぱり、ない。
まだマクロビオティックを理解していなかった僕は、病気が治ったら、
またお肉や甘いものが食べられるんじゃないかと密かに思っていたのだ。
思わす不安になって口をついて出てきた疑問だった。
実は、母はこってりお肉が大好きだったので、
母もお肉を食べたいという欲望は強かったのだと思う。
「早く、お肉が食べたくないって思えるようになれたらいいね」が、
母と僕との合言葉のようになった。
そして、数ヶ月もすると、お肉を焼く臭いが本当に気になって、
食べたいと思わなくなっていた。
スーパーのお肉コーナーも避けるようになっていた。
大久保先生の家のハスキー犬の歳三君が玄米食と聞いて、
その日から、我が家のシーズー犬のアトランも玄米食をはじめることになった。
最初は「クーン」と言って後ずさりしていたが、
数日すると食べるようになった。
以来、アトランは玄米ご飯が好物になった。
久司先生は「犬も玄米食にするとおとなしくなる」と言ってたけど、
効果はあったのだろうか・・・?
19.北枕
僕がマクロビオティックと出会ってから、
日に日に元気になっていくのがわかった。
だが、まだ頻繁に頭痛に襲われていた。
セミナーでは母が久司先生に
「先生、頭痛がまだ起きるのですが、治るでしょうか?」と聞いていた。
先生は「大丈夫。そのうちに段々と治っていきますよ」と答えてくれた。
こめかみを刺すような痛みは、それからも数年僕を悩ませた。
始めは不安だったが、先生のその言葉を信じて、
「絶対に治るんだ」と思えるようになっていた。
先生のアドバイスで、「北枕で寝なさい」と言われた。
それを聞いていたほかの人が
「先生、北枕は亡くなった人にするんでしょう?」と、一瞬ざわついた。
北半球に暮らす人は北のほうからエネルギーが入ってくるので、
北枕のほうが良いのだそうだ。
亡くなった人が北枕にするのは、せめて亡くなった時だけでも、
よいエネルギーが入るようにという昔の人の直感の風習の名残なのだそうだ。
みんなは「へー」と言う感じで驚いていた。
セミナーから帰ると、早速部屋の模様替えが始まった。
実は僕も両親も真反対で寝ていたのだ。
そして、両親の寝室と僕の部屋は隣同士だったので、
壁を隔ててベッドを近づけた。
夜に頭痛が襲ってきた時には壁をノックすると、
母がすぐに飛び起きて来てくれた。
首をマッサージして、手を当てておまじないのようにしてくれた。
僕は安心していつの間にか眠っていた。
その頃は母は夜にゆっくり眠ったことがなかったという。
それから、「おうちの中に緑の木を置きなさい」とも言われた。
そういえば、うちには緑の木がない。
先生には僕の家の中がお見通しらしい。
他の参加者も「玄関の横の荷物を片付けなさい。」と言われていた人がいた。
すごく驚いた。
そして、大きな「幸福の木」がリビングに登場した。
20.スプーン曲げ
最初に、母にマクロビオティックを教えてくれたおばさんは、
母の小学校からの友人だ。
いつも「君はすごいんだよ」と僕のことを励ましてくれた。
しかも美人で、僕はこのおばさんが大好きだ。
母も頼りにしていて、何か困ったことがあると、
長々と電話して相談していた。
一度、秋田に行った時に、僕はおばさんの家に泊まりに行った。
おばさんは僕を特別扱いではなく普通に接してくれた。
そして、いろいろな話をしてくれた。
おばさんと話していると、不思議と心が開放されていくのがわかった。
翌日、母が迎えに来る前に、おばさんは「気」の話しをしてくれた。
その中で、僕にスプーン曲げをさせてくれた。
「ユウチャン、これ曲げてごらん。ユウチャンだったら曲げられるよ」
僕は素直に「このおばさんの言ってることだから曲がるんだ」と思った。
スプーンは曲がった。
そこへ母が現れた。
おばさんは、今度は母に「これ曲げてごらん」とスプーンを渡した。
母は驚いて「えー、曲がらないよ」と言った。
するとおばさんは、「大丈夫だよ。ユウチャンも曲げられんだから」と言った。
母はほっとしたようにスプーンを曲げ始めた。
「ほら曲がった。できないと思ったけど、
ユウチャンが曲げられたって聞いたら、自分でもできると思ったでしょ?」
母も見事に暗示にかかったらしい。
「絶対にできないとおもっている人はどんなに暗示をかけられてもできないんだよ。
でも、できると思ったらできるんだよ。病気を治すのも同じ。
治せると思ことが大事だよ。ユウチャンならできる。大丈夫だよ」
母の固い思いが溶けていくようだった。
そして母はその帰りに閉店間際のデパートに寄って、
安いスプーンを買いあさった。
しばらく母のスプーン曲げは続いた。
こんな単純な母を僕は嫌いではないが・・・。
それからだろうか、
頭痛の時に母がかざしてくれる手から温かいものを感じるようになった。
21.祖父母の引っ越し
僕の母には兄弟がいない。
そして、僕も一人っ子だ。
つまり、母方の祖父母にとっては僕はたったひとりの孫になる。
1996年、5月、僕が大変な病気であるとわかって、すぐに駆けつけてくれた。
手術の時もずっと付き添ってくれていた。
当時は医師から僕が退院の見込みがないと言われていたので、
祖父母は僕や両親の力になりたいと急遽、
6月には秋田の家を引き払って、水戸に引越しすることを決断していた。
急だったのにも関わらず、とても良い人に買っていただいたとのことだが、
やはり最後の日は泣いたそうだ。
大きな大根を抜いた庭の隅の畑、高いポールに泳いでいた鯉のぼり、
僕の好きな「母が育った家」は、もう僕の遊びに行く家ではなくなってしまった。
こうして祖父母たちの水戸でのマンション暮らしが始まった。
僕が入院していたのは栃木だったので、
母が面会時間が終ってから水戸に帰るのは9時を過ぎていた。
祖父母の家で、父と夕食をご馳走になるのが日課だったそうだ。
祖母が作る煮物は最高においしい。
僕も外出許可の日は、祖母の家に食事に行くのが楽しみだった。
いつも賑やかな食卓で僕を迎えてくれた。うれしかった。
ところが1997年秋、僕達がマクロビオティックの食事を知ってから、
母と祖母の仲がこじれ始めてしまった。
祖母は僕に料理を作るのをとても楽しみにしていたのだが、
マクロに料理にこだわっていた母が
「油は使わないで、お肉は入れないで、ナスは使わないで、トマトはダメ、卵もダメ・・・」と
うるさく口出しするので、
わけのわからない祖母はすっかり機嫌をそこねてしまったのだ。
僕達は、しばらく祖母の手料理を楽しめなくなってしまったのだ。
ある日、母が倒れてしまった。
久しぶりに我が家を訪れた祖母は、
もともと痩せている母がもっとやせ細って寝ていたので、
驚いて「こんなに痩せて、、、もうこんな玄米菜食なんてやめてちょうだい!」
と言って母を叩きながら泣き崩れてしまった。
22.中学校入学
1998年4月、僕は中学へ入学した。
担任の先生は優しい女の先生だった。
クラスには小学校の時に僕を助けてくれた友達もいて心強かった。
新しい生活が始まった。
入学式の後で、担任の先生、保健の先生を交えて
僕の病気のことや手当てのことについての話し合いがあった。
最初は、先生達も戸惑っているようだったが、
何かあったら母が駆けつけることになった。
もちろん、お弁当の話しもクラスのみんなには先生から話してもらった。
学校は今までより遠くなったので、朝は母が送ってくれた。
帰りは体調のいい日は歩いて帰ることになった。
暖かい日には最後まで授業を受けることができたが、
やはり寒い日には体調が悪くなることが多くて、
保健室で休んでいることがまだまだ多かった。
母が梅醤番茶を持って駆けつけてくれた。
早くも僕は保健室の常連となって、保健の先生と仲良くなっていた。
卒業までこの状態は続いた。
5月には、校外学習で上野動物園と国立博物館に行くことになった。
母が一緒についてくることになって僕は安心した。
早朝から長い一日だったが無事全工程を元気にすごすことができた。
楽しかった。嬉しかった。そして、かなりの自信になった。
僕は元気になっていく自分を実感した。
次の週にはスポーツテストがあった。それにも参加することができた。
とにかくできることはやってみようと張り切っていた。
中学では何か部活に入らなくてはいけなかったので、僕はパズルクラブを選んだ。
今までの友達はみんな運動部で忙しくなってしまい段々話す機会が少なくなった。
僕は少し孤独感を覚えるようになった。
23.孤立無援?
僕たちがマクロビオティックにのめりこんでいくということは、
今までお付き合いのあった人たちとは距離をおくということでもあった。
友達同士で出かけることも、友だちのお母さんと一緒に食事にでかけることもなくなった。
マクロビオティックのすばらしさを話せば話すほど「理解できない」とみんな離れていった。
ちょうどその頃は宗教的な事件も取りざたされていたので、
ある意味世間では「セミナー」という言葉にさえ敏感になっていた。
母の友人は「だまされているんじゃないの?」と凄く心配して電話をしてきたほどだ。
僕たち家族は孤立感が募るばかりだった。
病院にもいかず、食事だけで病気を治そうなどというこの無鉄砲な家族に、
誰もが疑いと、心配とで距離をおくようになっていたのだ。
母も苦しい胸のうちを相談する人が身近にいなくなってしまったのだ。
僕のための食事作りを楽しんでいるようにみえた母でさえ、
当時は「本当に自分の作る食事で僕が元気でいられるのか?」と
不安に襲われたりすることもあったと言う。
夜中にお弁当の下ごしらえをしながら泣いていたこともあったと
最近打ち明けてくれた。
そんな中で、父はただ、黙って見守っていてくれていた。
僕は、お風呂に入るとよく貧血を起こして具合が悪くなったりしていた。
心配した父はしばらくの間一緒にお風呂に入ってくれて、からだを洗ってくれた。
会社から帰ってくると着替えもそこそこに僕の勉強をみてくれた。
あんなに反対していたのに、母と僕を信じて協力してくれたのだ。
この頃の僕たちは、世間から離れていったが、家族は一致団結していたのだと思う。
それでもやっぱり共通の話しができる人たちに会いたい。
僕たちはひたすら久司先生のセミナーを楽しみに一日一日を耐えて過ごしているようだった。
24.3回目のセミナー
1998年7月19日、
待ちに待った久司先生の宿泊セミナーの日がやってきた。
今回は蓼科の横谷温泉郷にある大きな旅館だった。
前回のように貸切ではなかったので、一般のお客さんもたくさんいた。
実際、山本祥園先生のお料理の本がセミナーの参加者以外の人たちに飛ぶように売れていた。
旅館は本館と新館に分かれていて、
新館の方は壁や床に炭の粉を練りこんだ素材が使われていたり、
テーブルも椅子もこだわった素材が使われているとのことだった。
なんでもこの旅館のご主人が体調を崩した時に
久司先生の食養指導により回復したとのことで、
すっかりマクロビオティックびいきになってしまったらしい。
セミナーの参加者はリピーターも多かったので僕たちは常連さんになっていた。
前回から参加した僕と同年の女の子も参加していた。
彼女は家族全員糖尿病で、お母さんと二人で来ていた。
母たちはお互いに苦労していることなど長々と話し込んでいた。
話し終わった母が「Cちゃんのおうちはお母さんが忙しいから、
毎日きんぴらごぼうと玄米ご飯だけだって」と言っていた。
僕は「ママがお料理好きでよかった」とホッとしたのを覚えている。
リピーターの中に若い男の人がいて、僕はこの人と仲良くなった。
マクロビオティックのレストランのレストランを立ち上げるために勉強に来ているということだった。後のクシガーデンのスタッフの人だ。
気功をやってるケーキ屋さんもいた。
先日、健康に関する雑誌に活動の様子が紹介されていた。
今回は男の人が多くて僕はその人たちに遊んでもらえるのが嬉しかった。
学校にいる時の孤独感からは比べ物にならないくらい楽しい開放感だった。
有頂天になっていた。
僕はついにハメをはずした。
貸切ではない旅館では、もちろん普通にお土産屋さんも開店していた。
お菓子の試食品もたくさんでていた。
僕は母の目を盗んでは口に入れて走り回っていた。
「コラコラ、まだ早いよ」っと声をかけられた。
「しまった・・・。」
僕はとんでもないところを久司先生に見つかってしまった。
25.調理実習
前回の伊豆のセミナーでは母と二人部屋だったが、
今回の横谷温泉では大きな部屋に10人くらいの女の人と一緒だった。
なんと、祥園先生も一緒の部屋だった。
でも先生は夜遅くまで食事の後片付けや明日の仕込をして、
そして朝早くまた食事の支度へと出かけられるので
「私はここでいいのよ」と部屋の入り口の隅の方で寝ていたらしい。
睡眠時間は4時間くらいだ。
当事の僕達には超人のように思えた。
宿泊セミナーの朝はいつも通り、メリディアン体操から始まる。
一階の大広間に集まって、
壇上でちょっと恥ずかしそうな顔をしたパトリシオさんが指導してくれた。
ラジオ体操とは違う、体のマッサージのような体操だ。
頭、顔、耳をこすったり、胸や背中をたたいたり、
静かに体が起きてくるような感じで気持ちが良かった。
まだ、朝が苦手な母と僕はいつもギリギリの参加だったが、
がんばって毎日参加していた。
からだがすっきりするとお腹がすいて朝ごはんが待ち通しかった。
食堂に行くのは一番のりだ。
食器を並べたりするお手伝いも楽しかった。
みんなで食べるご飯やっぱりおいしいと思った。
9時からは調理実習だ。
今回の調理実習の先生は山本祥園先生と藤形先生だった。
祥園先生のマクロビオティックのお料理についてのお話のあと早速実習だ。
毎回基本のメニューで同じなので、僕はもう圧力鍋で玄米ご飯を炊くことができたし、
3回目となると自信がついていた。
そして、今回はついに母とは別のグループで実習することになった。
男の人が多いグループで、初めての人がほとんどだ。
僕はちょっと先輩ぶって得意げだった。
母が心配して時々のぞきにきていた。
だが、この時母は他のグループのリーダーになっていて、
台湾では有名な先生らしい日本語の通じない人たちと
具合の悪い方の中でいっぱいいっぱいで頑張っていたのだ。
食事の支度ができた頃、
久司先生が現れてどこかのテーブルについて一緒に食事をしてくれるのだが、
気がつくとなんと先生は母の隣で食事をしていた。
母は緊張して食事は上の空だったらしい。
26.生きるチャンス
僕が自分の体の異常に気がついたのは、
1996年5月のことだ。僕は小学5年生だった。
その日は、宿泊学習で、グループに分かれて宿泊施設まで
それぞれで行くことになっていた。
その時に僕は目がよく見えないことに気がついたのだ。
周りの景色、看板がみんな二重に重なって見えたのだ。
翌日、すぐに保健の先生から母に連絡がいき、病院に検査に行くことになった。
そして、その日のうちに栃木の大きな病院に入院が決まった。
父もかけつけていた。
その展開の早さに誰もが何が何だかわからない状態だった。
僕だけはまだのんきに、同じ年代の子ども達とお泊りできるのをちょっと楽しんでいた。
それが、大変な事態の始まりだとは予想もしていなかったのだ。
入院して1週間後、僕の頭痛は始まった。
そしてすぐに化学療法が始まった。
点滴を入れるための血管確保の時にはあまりの恐怖に暴れていた。
いったい何が起ころうとしているのか?朝、枕にはごっそりと髪の毛がついていた。
ひっぱるとおもしろいほど抜けてきた。
ついに僕の頭から髪の毛はなくなってしまった。
母は帽子を買ってきてくれた。
それでも僕は楽しいことだけを考えようとしていた。
3時の面会時間になると必ず母が片道2時間かけて会いにきてくれた。
同じ病室の友達もできた。
週末になると、血液検査の結果がいいと、外泊許可がでて家に帰ることができた。
1997年2月、落ち着いていたかにみえた病気が再発した。
今度は6週間、実に69回もの放射線治療が始まったのだ。
伸びかけていた僕の髪の毛はまた抜けてなくなった。
やがて僕の気力や体力さえなくなっていった。
遠い病院で学校の友達も会いに来てはもらえない。
しかも14歳以下は病室には入れない。
寂しさと恐怖が押し寄せてきた。
ゲーム機を壊したり、金魚の水槽をたたいたり、問題児になっていった。
僕は壊れ始めていた。
それからも入退院は繰り返されていた。
そして10月、ついに母は久司先生と出会いマクロビオティックを知った。
12月、僕は逃れるように退院した。
余命1年と宣告をを受けてから1年半が過ぎていた。
病名は脳腫瘍。
このマクロビオティックとの出会いは、きっと生きるチャンスに違いない。
27.久司先生の体重
「またつまみ食いしたでしょ!」
突然母が血相をかえて僕を捕まえにきた。
今回の横谷温泉でのセミナーでは、
日本にフランス料理を紹介したことで有名な花田美奈子先生もいらしていた。
先生が母とトイレで会った時、僕に注意したことを母に伝えたらしい。
ホテルの売店の甘いお菓子が食べたくてしかたなかった僕は、
母の目を盗んではつまみ食いをしていたのだ。
この前はクシ先生に注意されたというのにまったく懲りていなかったのだ。
その頃の母は、桜沢先生の本に
「病気の時には、リンゴの一切れでさえ命を左右する危険がある」
ということを読んでいたので、
僕の所業にはとてもショックを受けたらしい。
僕はまた母を泣かせてしまった。
マクロビオティックの意味も、食養の意味もよく理解していなかった僕には、
こんなに元気になったのだから「食べたっていいじゃないか!」
という気持ちが持ち上がっていた。
「君にはまだ、売店のお菓子は早いよ」
とクシ先生は優しく注意してくれていたが、
母は容赦はしなかった。
そんな僕がもっとも楽しみにしていたのが
最後の日の夕食パーティだった。
みんな講義の時の服装とは違って、きれいな服を来て集まっていた。
お料理は、花田先生プロデュースということもあって、
今までよりも華やかで、すごい品数だ。
大きなザル豆腐やコーンスープ、黒米のデザート、
カボチャの中に玄米のピラフが入っていたり、お焼きもあった。
どれも美味しくて食べきれないほどたくさんだった。
みんなリラックスして楽しんでいた。
参加者の中から進行係りの人が選ばれていて、
その人がクイズを出していた。
その中で、クシ先生と体重をあてるクイズがあった。
クシ先生は身長が高いので、みんな多目に答えていた。
誰も正解者がいなかった。
先生の体重は確か50㎏といっていたと思う。
みんな、先生の体重が少なくて驚いてしまった。
次に、ビンゴゲームだった。
一番の賞品は「横谷温泉ホテル無料宿泊券」だ。
なんと僕はこのチケットをゲットしてしまった。
離れて座っていた母が走って飛びついてきた。
後に予約をしたが、車のトラブルでこの券を使うことはなかった・・・。
28.梅醤番茶の威力
セミナーも終りに近づいてくると、さすがに僕は疲れてきた。
久司先生の講義を聞いていた時、急に頭が痛くなって複視が現れた。
先生が縦にずれて重なって見えてきたのだ。
それまでずっと調子が良かったので僕は驚いて母に話した。
「講義が終ったら久司先生に相談してみなさい」と言われ
「先生、目が変なんです」と急いで声をかけた。
すると先生は「あ、そう。梅醤番茶を作ってもらって飲みなさい」と言われた。
そして、母は祥園先生にお願いして、厨房に行って、梅醤番茶を作ってきてくれた。
梅醤番茶は、梅干の実と醤油、生姜を合わせて番茶で薄めた飲み物だが、
練り合わせてビンに入ってできているものがある。
それを番茶で薄めて飲ませてもらった。
僕はゆっくりそれを飲んだ。
しばらくして、頭痛も治って、複視も消えていた。スゴイと思った。
それからは頭痛がおきると、母は梅醤番茶を作ってくれるようになった。
不思議と症状はよくなった。
僕はもう頭痛や複視がおきても怖くなくなった。
セミナーの最後の日の朝、講義が終わると、必ず先生は僕達にパワーをくれる。
先生の方へ手のひらを向けて両手を挙げて目を閉じていると、
何やら先生が何かを振っているような音がする。
「はい、目を開けて」先生は、息をハアハアさせていた。
みんな、手に熱いものが来たとか、ビリビリしびれたとか騒いでいた。
僕には、手が熱くなったような気がしたのに、
母は「わかんない」と言っていた。僕は少し得意気だった。
すると後ろの方でザワザワしていたので振り向いてみると、
女の人が倒れて祥園先生が介抱していた。
どうやら、先生のパワーが強すぎたらしい。
スゴイ!と僕はまた思ってしまった。
今度は、葛で溶いた梅醤番茶をぐったりしている人にスプーンですくって飲ませていた。
その後、駅でその人が歩いているのを見かけて、
「大丈夫ですか?」とみんなで声をかけた。
その人は元気になっていた。
恐るべし、久司先生のパワーと梅醤番茶・・・。
29.1998年夏休み
マクロビオティックを始めて最初の夏休みが来た。
7月のマクロビオティックセミナーに参加して、
久司先生からは、白身の魚は週に2回、揚げ物は週に1回は食べていいと言われた。
プールの許可もでた。
「もう大丈夫だから、しっかりマクロビオティックの食事を続けるんだよ」と声をかけて頂いた。
本当に段々元気になっていく自分を実感できた。
僕は小学2年の時に水戸に引っ越してきてから
「水戸こどもの劇場」の活動に参加していた。
こどもたちに観劇や遊びを通して
創造力や積極性を養うための活動を提案してくれる場所だ。
毎年、子ども達が中心になって計画する夏のキャンプがある。
サバイバルさながらのかなり大変だが自由で楽しいキャンプだ。
縦割りの学年を超えたグループでの活動だ。
もちろん食事の支度も子ども達が中心だ。
夏休みの楽しみのひとつだったが、
まだ厳格なマクロビオティックの食事をしなければならない僕には参加は無理な話だった。
しかし、当時の僕には仲間や友達と言うものの存在に
とても飢えていたような気がする。
僕はどうしても参加したいという気持ちをおさえられなかった。
両親に相談すると、宿泊は無理だとしても遊ぶだけならいいということになって、
遠いキャンプ場まで連れて行ってくれた。
一緒に食事はできなかったが、それでも楽しかった。
早く元気になりたかった。
夏休みは気分も落ち着いていて、
頭痛や複視も少なく順調な日々を過ごすことができた。
そして、中学1年2学期の始業式。
なんと全校生徒の前で、2学期に寄せる抱負を発表した。
残念ながらその時の原稿は見つからないが
1学期の終りに、先生が発表したい人を募っていた時、
僕は手を挙げていた。
生きている実感とこれからも生きられることへの希望と期待で、
僕の気持ちは充実していた。
30.母の決意
マクロビオティックの食事も慣れて、僕の体調も少しづつ良くなっていった。
すると、今度、母は「勉強!勉強!」とうるさく言うようになった。
体調が良いといっても、まだ、体力もなかったし、
頭痛や貧血に悩まされることも多かったので、
その頃の僕には少々荷が重いことでもあった。
でも、母の努力のおかげでここまで元気になれたのだと思うと、
僕は母の期待に応えたかった。
だがなかなかうまくいかない・・・。
その頃の母は、今の母よりずっと厳しくて怖かった。
僕には母が僕の体調やマクロビオティックのことにしか興味がないように思えた。
母には僕の心は見えていない。
そんな風にも感じていたが、当時の僕にはそれを伝えることなんてできなかった。
ずっと前向きな僕を演じていたのだと思う。
それにも、限界がきた。
「ママの食事のせいで僕は病気になったんじゃないか!」
僕の中でくすぶっていたものが、ついに口をついてでてきてしまった。
しまった・・・と思ったがもう遅い。
母は泣きだしてしまった。
「ごめん、ごめん、泣かせてごめんね」と僕はひたすら謝りながら、
自分のそんな気持ちを封印していった。
「何もかも夢だったらいいのにね。
病気になったことも、体が不自由になったことも・・・」
僕はつぶやいていた。
その後も幾度となく母との衝突は繰り返されたが、
母のマクロビオティックへの熱意は冷めることがなかった。
ただ、その時をきっかけに母の僕に対する接し方が少し変わってきたように思う。
そして、別の意味で、母は強くなっていったと思う。
母のマクロビオティックに対する決意は固い。
1998年秋、母は、山本祥園先生に勧められていた、
クシマクロのリーダーコースへの参加を決めていた。
僕しか見ていなかった母の目は、もっと広い世界を見ようとしていた。
「周りの人を気遣う目を持ちたい!身近な人を助けられる知識を持ちたい!」
いつしか、それが母の口癖になっていた。
31.日曜日の朝は・・・
1998年、秋。
僕たち家族がマクロビオティックをはじめて1年が過ぎようとしていた。
母は張り切ってクシマクロのリーダーコースのセミナーに
出かけるようになっていた。
僕のためだけのマクロビオティックではなく、
もっとたくさんの人に伝えたいと思い始めていたのだ。
母がセミナーで留守をした時に、
僕が玄米ご飯を炊かなければならなかったのをきっかけに、
何か母に出来ることはないか?と考えた。
毎日、僕のために朝早く起きてお弁当を作ってくれている母に
週末くらいは楽をさせてあげようと思ったのだ。
日曜日の朝、ひとり早く起きて圧力鍋で玄米ご飯を炊いていた。
「玄米ご飯が炊けたよ~」と声をかけると
母が起きてきて喜ぶ顔をみるのがうれしかった。
まだ包丁がうまく使えなかった僕は具のない味噌汁も作ったりしていた。
母を喜ばせるのがとても楽しみになっていた。
昔は、母が起きるのが遅くて、
日曜日はたいてい父と僕は朝マックに行っていたものだった。
朝はなかなか起きれないし、体力がなかったのか寝てばかりいた印象がある。
そのことを思うと、母は元気になっている。
お肉が大好きな家族だったが、
母はいつもお腹を壊していた。
そして、痩せていた。
「太りたい」と言って、お肉を食べていた母だが、
もともと胃腸の弱い母には負担が大きかったのだろう。
そして、反対に僕と父はどんどん太っていっていた。
1年前とは大違いの僕のうちの食卓風景だ。
マックのおまけの話しで盛り上がっていた我が家は、
今では今朝の玄米の炊き上がりの話で盛り上がっているのだ。
そして、父も1年で10キロほど体重が減った。
母は最初の頃は痩せ続けて周りのみんなが心配したものだが
少し体重が戻りつつあるとのことだった。
一度余計なものは排泄されて、
良い細胞のものでからだが作り変えられるのだそうだ。
だいたいあんなに朝起きるのが苦手な母が
毎日お弁当を作ってくれているのだから
玄米のパワーはスゴイ。
32.風邪とキャベツ
母がクシマクロのリーダーコースから帰ってきた。
マクロビオティックが全然わからない父と二人で過ごす3泊4日は、
何だか不安で僕にはとても長く感じられた。
僕は精一杯気を張っていたのだろう。
次の日、学校へ行くので靴を履こうと屈んだ拍子に僕は吐いてしまった。
母の顔色が変わった。
僕自身もたいして気持ち悪くなかったのに
吐いてしまったので、戸惑っていた。
僕の病気が発覚したきっかけは頭痛や吐き気だったので、
母はいやな予感にあせったのだと思う。
すると母は、「クシ先生はまだ次のセミナーで蓼科のホテルにいるはず!」
とホテルに電話をして先生を呼び出していた。
「先生!ユウスケが吐いちゃったんです・・・」
クシ先生はゆっくり「大丈夫ですよ。カゼでもひいたかな?」
とおっしゃっていたという。
母はすがるように「先生・・・再発ではないですよね・・」
と恐る恐る聞いていた。
隣の部屋で僕はその答えは聞きたくないな・・・と思った。
しばらくして母のホッとしたような明るい声が聞こえてきた。
「わかりました。ありがとうございます」
そして、その夜、
クシ先生がおっしゃっていた通り、僕は熱を出した。
やっぱりカゼをひいてしまったらしい。
熱は39度にもなり、
ついにセミナーで教わったお手当てを実践する時が来た。
母はキャベツとお豆腐を買いに走り、
キャベツの中身をくりぬいて小麦粉とお豆腐を混ぜたものを詰めて
僕の頭にかぶせたのだ。
その時は苦しかったので、おかしいとも思わなかったのだが・・・。
とにかく気持ちがよかったのは覚えている。
38度に下がるとお豆腐パスターは冷えすぎるというので
キャベツの葉を頭の下にしいて温かくなると取り替えた。
母はつきっきりで看病してくれた。
夜、父が仕事から帰ってきた。
キャベツに埋もれた僕を見て
「何これ!」と引きつっていた。
次の日、熱が下がっていた。
そして、カゼだったことにほっとした僕は
「もう再発はないな・・・」と確信した。
33.笠間の丹さん
僕たち家族がマクロビオティックを続けていく上で、
どうしても必要なのは農薬を使っていないお野菜だった。
ある日、祖母が
脱サラをして有機野菜を作っている人が紹介されている
新聞記事を見つけて、祖父と訪ねてくれていた。
ところがその人はちょっと遠かったので、
笠間の有機農業の先輩という人を紹介してくれた。
それが、丹さんだった。
とてもやさしそうで気さくな人だった。
マクロビオティックという言葉は聞いたことがあると言っていた。
母は簡単に説明をして、今は食事療法をしているので
「じゃがいも、ほうれん草・・・」はなるべく入れないようにとお願いしていた。
旬の季節になるととても採れてしまう野菜なのでちょっと困っていた。
最初は虫との闘いで慣れない母は
お野菜が届くとよく騒いでいたものだが、
今では「あら、あなた居たのね」と話かけるまでになっている。
僕は畑が見たくなった。
お野菜はどんな風に生っているのだろう?
と興味を覚えた。
いろいろな種類の野菜が植えてあった。
ところがひとつの区画のキャベツが全滅になっていた。
「いいんです。あそこはもう虫に明け渡しました」
と丹さんは笑っていた。
また、ある日は丹さんの奥さんがお野菜に虫がついているのを見て、
「いいんです。この時期どうせこの虫は長くは生きられないから・・」
とほっといている。
僕はとても意外だった。
というか、虫を敵と思っていないことに驚いてしまった。
丹さんの畑は有機といっても動物性の肥料は使っていない。
腐葉土やぬかなど植物性だけの有機栽培だ。
僕はすっかり有機農業に魅せられてしまった。
中学の時の体験学習では、丹さんの畑を選んだ。
ごぼうを抜いたり、芋をほったり、
土をさわっているのは気持ちがよかった。
この時から僕は将来農業をやりたい!
と思うようになっていた。
後に、母がFMぱるるんの取材で丹さんに尋ねた。
「なぜ、脱サラして農業を始めたのですか?」
丹さんの答えは
「東南アジアに出張に行って、日本人は本当に幸せなのか?
と考えたら有機農業に行き着きました」
丹さんのお野菜は力強くて
そして優しい味がする。
とにかく美味しい!
TBSラジオの「耕せニッポン」にもでていた。
ちょっと有名人だ。
34.お料理教室スタート
僕たちがマクロビオティックと出会って半年が過ぎ、
ちょうど、母がセミナーで習ったお料理だけでは、
レパートリーが少ないと嘆いていた頃だった。
いつも買い物をしている自然食品のお店で
マクロビオティックのお料理教室の案内を見つけた。
月に1度、つくばから先生が来て
近くの公民館で教えているとのことだった。
母は祖母を誘って出かけていた。
参加者は10名ほどだったそうだ。
ロールキャベツや炊き込みご飯、
抹茶と小豆のケーキもあった。
母が持ち帰る試食のお料理が楽しみだった。
・・・が、
半年も過ぎた頃、突然先生が辞めてしまった。
理由は、よりエコロジーな生活がしたいと
車を売ってしまったので水戸には来られなくなってしまったというのだ。
そこで、困った母達が、
せっかく縁あって出会ったのだから
お料理教室は続けたいということで、
驚いたことに、
セミナー参加経験者ということで母が先生役をやることになっていた。
母はそれから自宅でお料理教室を始めることになってしまった。
その時知り合った方とは
ミレットを立ち上げる時には相談にのっていただいたり
お手伝いをお願いしたり、いまだに縁は続いている。
母のお料理教室の原点は
意外なスタートだった訳だ。
稲本豆腐店さんとはこの先生の紹介で
お取り寄せしていたのがきっかけだ。
いろいろな方たちとの
ご縁が始まって行った。
35.幻の船中泊
中学2年になると、船中泊といって
大洗港から北海道へ行く船の修学旅行がある。
僕はまだ食事療法の最中だったので、
みんなと同じ食事をする旅行は危険だと判断した母は、
家族で行く北海道旅行を企画してくれた。
父も賛成をしてくれて、
学校の行程とほぼ同じコースをまわることになった。
宿泊するところは、「玄米酵素」という会社の宿泊施設で
洞爺湖の湖畔にあった。
玄米を勧めている会社なので、食事はもちろん玄米だった。
湖が見えて景色もよくて、
朝、家族で散歩をしたら、冷たい空気が気持よかったのを覚えている。
僕たちはレンタカーを借りて出かけた。
とにかくお昼ごはんを食べられるところを確保しなくてはならなかったので、
本で調べて玄米菜食のできるお店を探した。
本格的な外食は初めてだったので、ワクワクした。
母は写真をとりまくっていたのでお店の人が変な顔をしていた。
札幌の大通や時計台も見ることができた。
でも、6時の夕飯までは帰らなくてはならないので、
大急ぎで回った感じだ。
洞爺湖を拠点とすると移動にかなりの時間がかかった。
小樽にも行った。
ガラス館が印象に残っている。
最終日だったろうか、羊ヶ丘に行ったら、見覚えのある顔があった。
クラスのみんなだ!みんなに会えた!
ちょうど自由時間で少しの間みんなと話すことができた。
みんな楽しそうだった。
みんながメロンやアイスをほおばっているのがうらやましかった。
僕は食べることができない。
諦めかけていた時、
「メロン、半分こして食べようか?」
と思いがけず母が声をかけてくれた。
あの、スリルまじりの甘くてせつないメロンの味は忘れることができない。
ほとんどの時間を
果てしなく続く畑や牧草地帯の中を駆け抜けるのに費やした北海道旅行になった。
でも、気分は
「Boys Be Ambitious!」だ。
36.秋田へ(1999年6月)
北海道の旅行中、偶然久司先生の講演会が秋田で開かれることを知って、
母は北海道から申し込みを済ませていた。
それから3週間後、
母と僕、祖父母、そしてアトラン(当時飼っていた愛犬)
を連れて秋田へと向かった。
行きは雨だったこともあって
朝6時半に水戸を出たのに秋田に着いたのは3時半にもなっていた。
母にとっては初めての長距離運転だった。
本当にその頃の僕たちは、
久司先生に会いたい一心で動いていたのだと思う。
早速、お世話になった母の友達のところに寄った。
すごく元気になったことをとても喜んで、そして褒めてくれた。
「君は本当にすごい子なんだよ」っと、
何回も言ってくれた。
次の日、快晴に恵まれ、講演会会場へと向かった。
100人位の入れる会議室のようなところで、
それでも席に余裕があったほどだった。
今では信じられないほどの贅沢な講演会だ。
僕たちは聞く気満々で先生の真ん前の席を陣取った。
途中の休憩時間に先生は僕たちに気がついて、
「よく来たね~」と言って
僕の顔がぐしゃぐしゃになるほど抱きしめてくれた。
後半、先生は、マクロビオティックを実践している人の紹介ということで、
僕と母に前に出てくるようにおっしゃった。
突然のことで驚いていると、
今度は先生は、母に
「息子さんのことについて簡単に皆さんにお話してあげて」っと、
ますます驚く展開になっていった。
母は戸惑いながらも、
僕が余命宣告された病気からマクロビオティックと出会って、
こんなに元気になったことを簡単に説明していた。
聞いている人の中には涙を流している人もいた。
話が終わると拍手まで沸いている。
元気になって本当によかった。
久司先生に出会えて本当によかった。
その後、望診に選ばれたのが秋田に住んでいる父方の祖母だった。
腎臓が硬くなっていることを指摘されていた。
いい機会だからと、
母が玄米を勧めていたが食事を変える様子はなかった。
食事を変えるということは、元気な人ほど難しいのかもしれない。
僕を救ったのは、まさに「病気」だったのだ。
37.奈良、京都へ
そのころの僕たち家族は
久司先生に会える日を心待ちに過ごしていた。
先生のスケジュールをチェックしてその予定は絶対だった。
東京で講演会があると聞けば、
お弁当を持って出かけた。
先生の顔を見るだけで、それだけでよかった。
安心できた。
蓼科の宿泊セミナーの時には、
母を理解しはじめていた祖父母が、
同じホテルに宿泊してくれて、
しかもスタッフの計らいで
僕たちと一緒に食事を摂るようにと誘ってくれた。
祖父母が久司先生にあいさつをしていた。
「マクロの人たちはやさしい」というのが祖母の印象だったらしい。
久司先生と話をして、
僕たちの行動を心配しながら見守っていた祖父母たちが、
一気に安心してくれて、
マクロの食事に興味をもってくれるようになった。
やはり、久司先生の力は大きい。
母が一番ホッとしたに違いない。
そして2000年、
僕が中学3年の関西方面の修学旅行をあきらめた時、
丁度先生が奈良で講演をされると聞いて、
父も一緒に旅行を兼ねて出かけてくれた。
奈良のセミナーでは久司先生がひとりひとりの名前の音から
その名前の意味を説明してくださったのが記憶に残っている。
隣が東大寺だった。
奈良の大仏にも会うことができた。
夜は先生を囲んでうどんすきを食べた。
先生がテーブルを回ってひとりひとりに声をかけてくださった。
この時、僕たちは初めて中先生にお会いした。
若くて颯爽として、僕は「かっこいい」と思った。
当時、中先生はすしテックという玄米のお寿司屋さんを開いていた。
僕は「パンフレットください」と声をかけた。
母は山本祥園先生に「リマクッキングに通われたら?」
と声をかけられていた。
自宅で細々とお料理教室をやっていたが、
ちゃんと勉強したいという気持ちと、
たぶんまだ僕のことが心配で、
家を空ける気になれなかったのと、揺れていたのだと思う。
翌日、満足した僕たちは京都に移動した。
父が大学時代を過ごしたところだ。
食事は玄米菜食の食事ができるお店をマークしておいた。
ところが、夜、やっとたどりついた店は
「本日貸し切り」
ぼくたちは途方にくれた・・・・。
38.母のシナリオ
2000年、中学3年の春、
修学旅行が終わると、
クラス全体に受験にむけての緊張感が漂うようになっていた。
そんな中、日々の体調と格闘していた僕には
受験も高校も見えてきてはいなかった。
「今日は学校から歩いて帰ってこられたよ!」と
今ここにある出来事に喜びを感じることしか考えていなかった。
僕が自分の将来について、
他人事のようにいたってのんびり過ごしていたのに対して、
父と母たちはまずは僕の進学についていろいろ話し合いが繰り返されていたらしい。
父は普通の高校に通わせたいと思っていたらしいが、
母は反対していた。
普通の高校では食事をコントロールしていくのは難しい。
まだ、普通の学生として生活するのは早いのではないか?
また、一番怖いのはストレスだ。
だから、定時制か通信制の高校を選ぶべきだというのが母の考えだった。
そして、秋、ようやく自分の進学について考え出した僕の希望は、
「農業高校へ行きたい・・・。」
中2の時に体験した丹さんの畑や
水戸の農業高校の収穫祭を見て、
農業をやりたいと思い始めていたのだ。
母は、はっきりとは反対はしなかったが、
それとなく僕に不利である条件を並べたてていた。
そして、職業訓練校や通信制の高校を何校か回って
話を聞きに出かけたりもした。
僕の気持ちは変わらなかった。
しかし、母の中ではもっとすごいシナリオが出来上がっていた。
「自然食のお店をやりたい!」
またもや爆弾宣言だ。
僕がずっとマクロビオティックから離れずに生活する方法として、
通信制の高校で勉強しながら、
お店を手伝い、卒業したら本格的にお店に関わるという考えらしい。
確かにその頃、
母は、自然食の通販で取り寄せた食材を
お料理教室に来た人たちに分けたりしていたが・・・。
ついに、合格発表の日が来た。
「番号がなかった」
とがっかりする僕に
「残念だったね」と
ニッコリする母がいた。
39.リマクッキングへ
母は父を説得すると、早速動き始めた。
まず、僕は通信制の高校に通うことが決まった。
そして、母のシナリオ通りに事は進んだ・・・かに見えた。
母は物件を探し出し不動産屋、内装屋、仕入先の確保など
着々と準備をすすめていった。
お店の名前も考えた。
最初の候補はお客さんがたくさん来るように
「come come」。
コメとも読める。
「米を噛む」・・・ダジャレな好きな母らしいネーミングだ。
そして、
いよいよ保健所に手続きの用紙を取りに行った帰りの駐車場で
運命の電話がなった。
「申し訳ありません。あの物件は他の方に決まりました。」
理由は、母に事業経験がないことだった。
母は、その場にしゃがみこんでしまった。
一度は落ち込んだ母だが、復活も早かった。
通信制の高校はプリントの自宅学習がほとんどで、
スクーリングといって月に一度、学校の授業があるだけだった。
時間はたっぷりある。
「ユウスケ、一緒にリマに通おう!」
2001年4月、
僕と母は東北沢にあるマクロビオティックの本拠地ともいうべき
「リマ マクロビオティッククッキングスクール」に通うことになった。
毎週水曜日にバスと電車を乗り継いで、
片道3時間はかかる。
母は師範コースまで通うと意気込んでいたから、
これから2年ぐらいはこの生活が続く予定だった。
その間、ゆっくりお店の物件を探して、
開店にむけての細かい準備をしていこうということになった。
1日目、慣れない乗り物と東京の空気が息苦しくて、
教室につくとすぐに僕は具合が悪くなってしまった。
また、頭痛が始まったのだ。
僕が青い顔をしていたら、
近くにいたリマの先生が醤油番茶を勧めてくれた。
頭痛はすぐに治まった。
「ここなら具合が悪くなっても大丈夫だね」
と母は心配してくれる様子はない。
その日は玄米ごはんの炊き方とゴマ塩だけだった。
久司セミナーや家で実践していたので僕はちょっと得意げだった。
40.鍼灸との出会い
僕たちの新しい生活が始まったころ、
また、母の秋田の友人から電話があった。
「スゴイ人と出会った!」
僕の左手と足の麻痺が治るかもしれないから、
鍼灸をためしてみない?」っということだった。
なんでも、そのおばさんが急に体が動かなくなって、
どうにかしようとたどりついたのがその鍼灸師さんだったというのだ。
劇的な回復を得て
次に脊椎を痛めて歩くこともままならなかったそのおばさんのお父さんも
動けるようになったというのだ。
母は迷っていたようだった。
当時の母の頭の中にはマクロビオティックを信じることしかなかったからだ。
しかし、マクロビオティックに出会ったことは
健康への原点に立ったにすぎないのではないか?
もっと、ほかの世界も受け入れて試すべきではないか?
と説得されたという。
そして、母の僕に対する精神的な拘束の影響をとても心配していた。
当時は仕方がなかったのかもしれないが、
「母の言うとおりにしなければ生きられない・・・」という恐怖と、
母の執着から逃れようとする
僕の心のひずみをこのおばさんは見抜いていたに違いない。
「舞台の上にあがってスポットライトで照らされたユウスケだけを見るんじゃなくて、
舞台の隅の暗い部分も一緒に見なくちゃ
その劇の全体を見たことにはならないよ」
この言葉が母を動かしたらしい。
もっといろんな人と関わりを持とう・・・。
いろんな人の助けを必要としよう・・・。
またまた母は父を説得して、
僕とアトランを乗せて秋田へと車を走らせた。
何かが起こりそうなそんな期待に吸い寄せられるように長い道のりを急いだ。
鍼灸。初めての経験だ。
41.視力があがった!
僕は緊張して鍼灸の先生の前に座った。
すると、いきなり小さな針を僕の目の上に刺し始めた。
母は不安そうに僕を覗き込んでいた。
耳の回りにもたくさん刺していった。
不思議と痛くなかった。
次に小さなもぐさに火をつけて、
背中、お腹、足、手とお灸をされた。
これは熱くて逃げ出したい気分だった。
僕の体中にポツポツと小さな火傷のようなものがついていった。
次は母の番だ。
先生は母が痩せているのが気になったのか、
最初に脈をとった。
すると、先生は
「なんだこりゃ!あんたは玄米食べてる人の脈じゃない!」と、
大きな声をだした。
母のからだは小さい頃からの虚弱の体質がぬけていないのと、
長い間の緊張とでガタガタの状態だったのだ。
「こりゃ、お母さんの方も大変だ!」といわれてしまったのだ。
母が落ち込んでいくのがわかった。
とりあえず、僕たちは父方の祖母の家に1か月お世話になって、
鍼灸に通うことになった。
当時、僕の視力はかなり悪くて
黒板の字がほとんど見えていなかった。
久司先生に相談した時に
「メガネ・・・もうちょっと先に考えましょう」
と言われていたので、
メガネのことは母には言えないでいたのだ。
それに、まだ複視があったので物が部分的に二重に見えたままだったのだ。
ある日、鍼灸の先生に
「このカレンダーを見てごらん・・・」
と、言われた。
が、僕には数字がよく見えなかった。
先生は足に針を打ち始めた。
すると、・・・不思議なことに数字がよく見えるようになっていた。
しかも、数字がちゃんとひとつになって見えるのだ。
僕は久しぶりに世の中がひとつになった気がした。
母の顔も、先生の顔もちゃんとひとつだ。
なんてすごいことなんだ。
僕はもしかしたら手も治るんじゃないかと期待した。
鍼灸の先生は桜沢先生の本も読んでいてマクロビオティックを知っていた。
しかし、O-リングテストで
「君は玄米は合わないね。白米を食べたほうが合ってる」
と言われてしまった。
僕は正直白米のほうが好きだったので少しほっとした。
が、母は玄米の力を信じて、ゆるがなかった。
42.障害者
なんで、マクロビオティックをやっているのか?
と秋田の鍼灸の先生に聞かれて
僕たちはうまくこたえられなかった。
「健康で長生きするため・・・」と細々と答えたが
「そんなことになったら人が増えすぎて地球が落っこちるぞ」
と言われてしまった。
本や久司先生の言葉から
うまい答えをみつけようとしたが
どれも今の自分たちには実感の伴わないものばかりだ。
世界平和なんて考えられない、
幸せという言葉にも縁遠いような気がしていたころだった。
「我慢だ、努力だ、リハビリだ」と、
今まで自分が障害者だという自覚をもっていなかった僕には、
先生の口から何度も障害者という言葉がでてくるのが正直いやだった。
それでも、1か月もたつとなんとか左手で指を折って
カウントができるようになり、
ご飯茶わんが持てるようになった。
それなりにうれしいとは思ったが、
なかなか思い通りには動いてくれない左手がもどかしかった。
食べたいものも我慢して、
熱いお灸も我慢して、
リハビリをさぼると怒られて・・・
だんだん左手なんて使わなくてもいいやと思うようになっていった。
僕にとってのマクロビオティックは
「もう病気になりたくないから、生きていたいから」
ただそれだけでしかなかった。
2001年、高1の夏、
まだ僕は生きている喜びや幸せを実感するまでには至っていなかった。
43.リマクッキングスクール終了
月に2回の通信制の高校のスクーリングや
鍼灸を受けるために秋田に行ったりしながらも、
僕は母と一緒に東京のマクロビオティックの料理教室「リマクッキングスクール」へ
毎週水曜日に通い続けた。
生徒が30人くらい、若い女の人がほとんどだ。
僕はなるべく母と離れて動いていた。
包丁はうまく使えなかったので、
炒め物や揚げ物には積極的に取り組んだ。
車麩のカツを揚げていた時、気がつくと僕の周りには誰もいなくて、
必死になって揚げものと格闘していたが
どんどんきつね色が濃くなっていった。
尾形先生が「ちょっと、誰かサポートに入って!」と叫んでいた。
母はハラハラしながら手伝うのをがまんしていたらしい。
試食会もいろいろな人と話ができるので楽しみだった。
おそらく最年少でしかも男となると
やっぱり、みんな僕がマクロビオティックを始めたきっかけに
興味をもっているようだった。
僕は「将来は、自然食のお店をやりたい」と話たりしていた。
僕と母は無事、初級コースを12回受けて終了した。
母は中級へ進み、週末コースを選んだ。
日曜日は6時前には家を出ていた。
父が駅まで送って行った。
「この苦労が報われる日は本当に来るよねぇ・・」
日曜日の朝の母の口癖だった。
そして、母が師範クラスをめざして走りはじめ、
中級クラスも中盤となった秋のある日、
運命の電話はなった。
「お店、やってみませんか?」
前回断られた不動産屋さんからだった。
また、運命が動きだした。
44.店舗発見
当時住んでいた家とは車で15分ほどの距離の所だった。
あえて言えば、祖父母のマンションに近かった。
が、ほとんど通ったことがない道だった。
が、実は以前、僕たちはたまたま通りかかっていた。
僕たちの前に現れた新しそうなマンション。
その一階の道路に面したほうに、
オレンジと白のストライプのオーニングがはりだしているカフェが見えた。
「ねぇ、ユウスケ。ママがもしマクロのお店をやるとしたら、
こんな感じのカフェっぽいお店にしたい。どう思う?」
「あぁ、いいんじゃん」
こんな会話をしても、本当にお店をだすことになるなんて
想像もしていなかったから、僕は適当に答えていた。
その後も母の中でどんどん妄想が膨らんでいたなんて驚きだった。
数ヵ月後、
そのマンションの一階一番奥のテナントがまだ空いていることを聞きつけた母が動き出した。
そして、その時は見事に散った訳だったが、
あきらめきれない母は不動産屋さんに
「何年でも待ちます。この御茶園通りで物件を探してください」
と、お願いしていたのだ。
あれから半年。
まだ、始めて一年程しかたっていない、
あの最初に見たカフェが閉店することになったのだ。
「お店やってみませんか?」
一度は消えかかった夢だったが、
思いも寄らない展開の早さで現実味を帯びて近づいてきた
45.夢の実現
不動産屋の人に案内されて初めてその店内を見て驚いた。
時々、母とお店について夢を話し合っていたことがあったが、
まさに夢で描いていたような店内の作りだったのだ。
ほとんど母がひとりで切り盛りするわけだから、
オープンキッチンでなければいけない。
お客様とお話ができるように客席はカウンターで、
残りのスペースは自然食の商品を並べられるようにしたい。
いわゆる居抜きということらしいが、
ほとんどリフォームをしないで使えそうだった。
輸入雑貨も扱っていたので壁には棚が設えてあった。
それも、商品を並べるのに使えそうだった。
まるで僕たちの夢をかなえてくれるような店の雰囲気にみんなが興奮した。
今までも何軒か空き店舗を探したことがあったが、
今回は家族全員が乗り気になった。
「よし!ここに決めよう!」
残る問題は資金だった。
最後の難関は金融関係だ。
融資をお願いするにあたり、
貯金通帳、久司先生のマクロビオティック認定証・・・
あらゆる資料をもちこんで担当者の説得にあたった。
事業の経験もなく、貯金もそれほど多くもなかったので、
かなり厳しいことも言われたそうだ。
・・・だが、母は負けなかった。
「絶対、これからの世の中に必要な店なんです!」
・・・そして、ついに審査は通った!
父は積極的に応援していた。
僕はまだ夢と現実の区別がつかないまま
母の気迫に押し流されていたようだった。2001年秋のことだ。
46.開店準備
一日も無駄にはできなかった。
いったいどのくらいの品物が必要なのか?
どのくらい棚に並べられるのか?
ランチのメニューは?営業時間は?仕入先は?・・・・・
考えなければならないことがたくさんあった。
まず、お店の名前はどうしよう?
母がこの半年で温めておいた名前があった。
「ミレット」なんてどう?
父が「う~ん、喫茶店みたいな名前だな」
すると母が「ミレットってね、雑穀のことなんだよ。
寒い土地でも育つといわれる生命力とか、
一粒から広がるたくさんの実。
一粒万倍っていうんだっけ?
なんか縁起が良さそうじゃない?」
でも、なんか足りない。
母も、もうひとつ踏み切れずにいた。
まだ、マクロビオティックという言葉があまり知られていない頃の話だ。
マクロビオティックとつけるのはちょっと・・・ということで、
「食の提案スペース ミレット」と決定した。
「日本古来の食生活を見直して
マクロビオティックという新しい食生活として提案するスペース」
という意味をこめている。
看板のデザインも母がノートに簡単に描いていたものを
看板屋さんがデザインし直してくれたものだ。
看板の色は実はハロウィン好きの母が
とっさの思いつきでカボチャをイメージして
オレンジとグリーンと電話で答えたものが実際の物となって仕上がってきたのだ。
もう、後戻りなんて考えることはできなかった。
着々と準備は始まっていった。
みんな夢中で、期待とか不安とかさえも口にする余裕もなかった。
次に考えなくてはならないのが
どんな商品を仕入れるかだ。
僕たちの食生活(マクロビオティック)に沿ったものだけを扱うお店として
動物性の物、乳製品、砂糖が入っているものは除くことにした。
それまで母が信頼して取り寄せていたオーサワジャパンの品物を中心に
揃えていくことにした。
豆腐はもちろん、つくばの稲本さんの無農薬のお豆腐を入れたい。
小売店に卸したことはないとおっしゃっていたが
快く応じてくれた。
母はどんどんヒートアップしていった。
47.お米とお水との出会い
肝心のお米はどうしよう?
母は、有機食材を掲載した本を買ってきた。
「あ、ここ!ここに電話してみる」
母の出身地である秋田の有機玄米「あきたこまち」に目がとまった。
母は早速、大潟村で天日干しの有機玄米を作っている
生き活き農場の井手さんに電話をした。
「新しく自然食のお店を開きたいんですが、
そちらの玄米を仕入れることができますか?」
僕は隣にいて、母の鼓動が聞こえるようだった。
「あなた、マクロビオティックを知っていますか?」と聞かれて、
「はい、知っています。実践しています」と母は答えた。
すると、井手さんは「久司道夫先生を知っていますか?
私はアメリカに行って久司先生のところで勉強してきたんですよ」
母は興奮して、
「はい、私も久司先生の指導で
マクロビオティックを実践しています。
私が秋田出身なので、ぜひ井手さんのお米を扱わせてください」
こうして奇跡のような出会いでお米が決まった。
初めて井手さんのお米を食べた時、
今まで食べていた玄米と全然違う!っと思ったくらい
「おいし~い」と驚いて笑いが止まらなかった。
父も「これなら美味しい」と言って、
家族で夢中で玄米ご飯を食べた。
今はもう天日干しの玄米は届かなくなってしまったので
幻の玄米になってしまったが、機械乾燥でも十分おいしい、
ミレットのご飯の原点だ。
次の問題は水だ。
浄水器は絶対必要だ。
いったいどれを選んだらよいのか?
なかなか決まらなかった。
ある日、知り合いのお店に遊びに行くと、
「お水ここに置くね」と
ボトルに入ったお水をたくさんテーブルに置いて行く人がいた。
母は「そのお水はなんですか?」とくらいついた。
「このお水ねー。すごいお水なのよ。
実験してあげるからウチにいらっしゃいよ」と、
そんなに知っているかたでもなかったのに
おじゃますることになってしまった。
そのお水に野菜や肉を漬けておくと味がよくなって日持ちもするらしい。
とにかくエネルギーの高いお水らしいが
僕は甘くて柔らかいお水の味が気に入ってしまった。
「絶対これがいい!」なんだか絶対譲れない気分になった。
48.ついにオープン
お店の開店にむけて、着々と準備が進んで行ったかのようだった。
お店を借りてから2ヶ月半という短い間にオープンを目指して動いていた。
猫の手も借りたい時に、父は長期の海外出張で手伝えなくなってしまった。
商品の棚は母と祖父が組み立てていった。
そして、夜になると母はひとりで商品の値段付けと陳列に出かけて行った。
僕はちょうど学校のテストがあったり、
手伝うことができなかった。
だが、お店のことが気になって、
気持ちはそれどころではなかった。
あと1ヶ月と迫った時、
そろそろランチの試作やメニューも決めていかなくてはならないのだが、
今度は頼りにしていた祖母が脳梗塞で入院してしまった。
祖母は、「肝心な時に手伝えない」と泣いていた。
自分のことより母のことを心配しているようだった。
母は動じなかった。
「お店を開くのは私!お母さんはゆっくり休んで!」
お店の準備、祖母の見舞い、祖父の食事の支度、
やることがどんどん増えていったのに、
母は不思議なほど前向きに動いていた。
「いろんなことがあるほどなんだかお店がうまくいくような気がするの」
むしろ、楽しんでいるようにさえ見えた。
僕はこの勢いに圧倒されながら、
レジの練習に励んでいた。
「もうやれることしかできないから、
ランチは一種類だけにする!
丹さんの冬大根が甘くておいしいから大根ステーキでいく!」
それと、おにぎりセット。
いろいろ試作していたが結局、
シンプルなメニューに決めたらしい。
新聞の広告、チラシ配り。
看板も掲げられていよいよオープンが目の前に迫った。
緊張の中にもまだ呑気に迎えた
2002年2月5日。
ところが10時オープン待たずして、
お客様が外に並んでしまった。
開店祝いのお花も次々に届き、
母はランチの準備どころではなくなっていた。
初めて、母の笑顔が凍りついた瞬間だった 。
49.大盛況
自分たちの予想を超えた反響に母も僕も戸惑っていた。
嬉しいことに連日いらしてくださるお客様が
「玄米ご飯が美味しい」と言ってくれた。
ご飯は玄米100%のものと
玄米に黒豆、黒米、小豆、金時豆、ひよこ豆、大豆を
混ぜて炊いた紫色のご飯と2種類炊いた。
始めはお客様にどちらのご飯にするか選んでもらっていた。
ところが、ほとんどのお客様が「どちらも食べたい」とおかわりをするので、
結局お茶碗に半々に盛り付けることになった。
甘く、もっちり炊けたご飯は一押しの自慢のごはんだ。
たくさん食べていただこうということで、
おかわりは自由ということになった。
毎日ご飯が完売するほどの盛況ぶりだった。
数日後、たまたま通りかかったという東京新聞の記者の人が
ミレットランチを食べて
「記事にさせてください」
と言って取材をして行った。
お店がオープンしたばかりと知ると驚いていた。
やはり、お肉やお魚、卵、乳製品、砂糖を使わないお料理で、
しかも玄米というメニューのお店は珍しく興味をひいたらしい。
一見シンプルでボリュームに欠けるように見えるおかずなのに、
ご飯もきっちり食べると、ちゃんとお腹と心が満たされる
不思議な魅力をわかってくれている人のようだった。
後で、新聞に載った自分のお店の記事を見て、
益々僕は、お店をオープンさせてしまったコトの重大さを実感していった。
その頃の母は、朝の7時半にはお店に出かけて準備を始めていた。
僕は後から祖父に車で迎えに来てもらって9時ごろ出かけていた。
まだ、一日中立って仕事をするほど体力がなかったので、
ランチの忙しい時間が過ぎて自分たちの食事が終わってから4時位には、
また祖父に迎えにきてもらって家に一足先に帰っていた。
母はひとり残って、ランチのお皿など洗い物の片づけが終わらないまま、
お買いもののお客様の接客をしていた。
洗い物やデザート作りは7時の閉店後にならないと始められなかったので、
母が帰ってくるのは夜9時を過ぎていた。
寒さも本格的な2月のことだ。
僕たちはいつも冷たくなったご飯をストーブの前で
しがみつくように食べていた記憶がある。
それでも、「明日もがんばるぞ」思えたのだから、
夢中だったのだろう。
初めての定休日、
母は朝からビクとも動かなかった。
ひたすらうずくまって寝ていた。
ご飯も食べられない様子だった・・・。
50.脚力
お店を始めた頃の僕は、まだ体力がなかったので
忙しいランチタイムが終わると、
歩いて10分ほどの所にある祖父母の家に休憩に行っていた。
その時に、ランチの残ってしまったおかずを届けるように、
時々母は袋に入れて僕に持たせた。
ほんの軽い荷物だった。
左半身に軽い麻痺のある僕はうまくバランスがとれずよく転んだ。
あまりにも見事に転んで、通りすがりのおばさんに
「大丈夫?」と声をかけられたりした。
袋の中のお皿は割れていた。
「転んで割れました~」と背中まで土まみれになってお店に戻ると
母は「あれ~」と言って笑っていた。
僕は内心怒られると思っていたのでホッとした。
そんなことが何度か繰り返された。
ある時は顔から倒れて前歯を折ったり、
手を擦りむいたり、膝を擦りむいたり・・・
今思うと本当によく転んでいた。
母は歩き方の特訓だと言って、
暇を見つけてはお店の中を何度も往復させて
転ばないようにとあれこれ注意してくれた。
その甲斐あってか、気がつくと転ばなくなっていた。
その頃の僕の好きなおかずは「きんぴらごぼう」だった。
それは、久司先生のセミナーで
「ゴボウを食べなさい。足が強くなるから」
と言われたこともあった。
セミナーの実習で習った「きんぴらごぼう」は細くて柔らかい。
お醤油だけの味付けなのにゴボウも人参も甘くて美味しい。
母も「足が強くなるから」とよく作ってくれた。
本当に段々足が強くなっていった。
ある日、お店で僕は母とけんかになった。
我慢できなくなった僕は隙を見てお店を飛び出した。
転ぶなんてことも考えていなかった。
とにかく逃げたかった。
一目散に自宅へ向かって駆け出した。
夢中で2時間近く歩きとおしてしまったのだ。
母はそれを聞いて怒るのを忘れていたようだった。
自信をつけた訳でもないが、それからも僕はよく脱走した。
最初はあきれながらも喜んでいた母だが、
回数を重ねるうちにさすがに怒られるようになったのは当然だ。
それから8年たった。
僕は家から離れて栃木の若者自立支援塾で暮らすことにした。
はじめからひとりで自立を試みるのには
少し自信がなかったからだ。
だが、なんとなくこのままではダメなんだという思いで
家から離れる決心をしたのだ。
塾の一大イベントとして30キロウォーキングというのがある。
いまだかつて脱落者がいないと言われるそのイベントに
挑戦できるまでになった。
緊張した。
笑っていられたのは最初だけ。
辛く、長い道のりだった。
他の塾生たちの励ましのおかげで歩き通した。
母に報告すると「おめでとう!」と言ってくれた。
脱走が培った脚力かもしれない。
車いすを覚悟したり、
イチゴ畑で走ってみたら
母がうれし泣きをしたこと・・・
そんなことがみんな、過去の出来事になった瞬間だ。
51.2013年夏 親子万歳終了の日
僕ににとって
新しい生活が始まろうとは
夢にも思っていなかった日々だった。
母と二人三脚で始めたお店は
優しいスタッフにも恵まれ
2008年には
またまた、母が思い描いた通りの
同じ御茶園通りに
店舗兼自宅にできるような
家と出会い引っ越しをした。
現在のミレットだ。
僕は僕で本格的に
マクロビオティックの勉強をしたいと
スタッフやお客様たちと
取手で開校したばかりの
大久保先生のところへ通い
クシマクロの資格を取得したりした。
僕自身も
気持ちを新たに
張り切って
スタートした形だった。
その年の暮れ
そんな僕を見届けたかのように
愛犬のアトランが逝った。
やがて
僕自身の中から
「体調を崩す」
という言葉は
消えていった。
気が付いたら
発病してから
17年も経っていた。
それからも
たくさんのお客様に
支えられ
励まされ
母とは
泣いたり、笑ったり、
けんかしたり、なごんだり・・
親子漫才と言われながら
ミレットでの
毎日は続いていた。
実は少し前から
僕自身の中で
くすぶり始めていたことがあった。
もう、ミレットで働くのはやめたい。
ここにいたら
病気だったことを
忘れようにも
忘れられないじゃないか・・・
そういう、タイミングで
ちゃんと
こういう言葉が降って来るんだろう・・・きっと
元気になろう・・・で始まったミレットが
誰かの役に立てたらいいね・・・になって
でも、
それは、ある意味
病気を克服した、
病気だった
「かわいそうなユウスケ君」
「がんばったユウスケ君」から
逃れられなかった訳で・・
段々自分自身の
ポジションが
苦しくなってきていた
僕が望んだことは
病気だったことを知らない
普通の人との関わりの中で
生きて行くこと
それこそが
僕の中の「完治」であったのだと思う。
車の免許も取得して
2013年夏
ご縁をいただいて
就職をした。
なにもかもが
奇跡のようなできごとだ。
新しい僕の人生が始まった。
52.冒険物語の完結
2014年2月
いつも僕の味方をしてくれていた
祖父が亡くなった。
まるで僕がしっかり生きられるようになったのを
見届けて安心したようだった。
2015年
元気に仕事を続けている。
基本的に
僕はミレットで働くのは
好きだ。
仕事が休みの時は
手伝っている。
不思議なほど
息苦しさはない。
これでよかったのか
わからないが
充実した日々を
送っているのは
確かだ。
マクロビオティックを
広げよう!とか
世界平和に貢献しよう!
なんて、大きなプラカードじゃないが
たしかに
「奇跡のごはん」
であったことは間違いない。
超お気楽家族が
たどり着いた
マクロ的夢パラダイス
「ある意味、冒険物語!」
はここに完結する。
本当に
いろいろな方との出会いに
感謝だ。
本当に 感謝 だ。