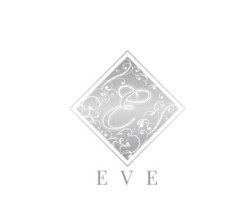行政書士事務所村瀬総合法務
当事務所は、2011年に練馬区の閑静な住宅街で開業しました。現在では東京都豊島区(池袋)に事務所を構え、外国人採用に伴う在留資格及び労務コンサルティングを通じて、これまで延べ150社以上、累計1,800件以上のご相談・ご依頼を賜り、日本の企業や外国籍の皆様をサポートしてまいりました。年々増加する外国人在留者、時代に応じて変動する「出入国管理行政」が、私たちの専門分野であり舞台です。現在、数多くの専門家が日本には存在します。そんな中で、当事務所を訪れてくださったご相談者様に、
あの事務所にいけば
きっと何とかなる
と感じていただける事務所を創りたいという想いは2011年開業時からずっと変わりません。当グループで一緒に活動する専門家と力を合わせ、日々研鑽を怠らないことを誓います。
代表行政書士 村 瀬 仁 彦